金融業務
Videos
動画コンテンツ
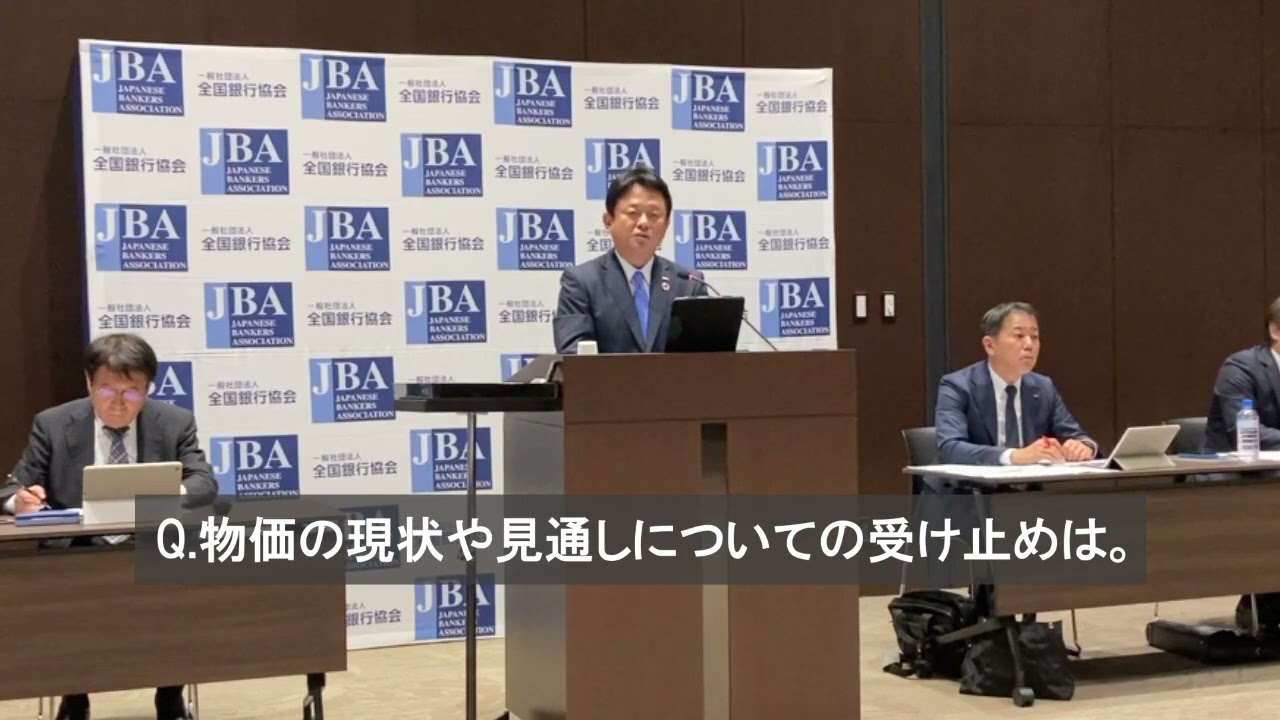
2023/6/15 全銀協会長会見質疑応答(前編)
この動画はプレミアム会員限定です。登録すると動画をご覧いただけます。
Q.米国金融政策への現状の評価と、国内金融機関のPBR改善に向けた取り組みについて。
まず一つ目のFOMCの評価でございます。今お話しいただいたように、昨日の会合では市場の予想通り据え置きが決定されたということであります。今後、FRBにおきましては、適切なペースで行われてきました金融引き締めの効果というのを見極めながら政策判断をしていくというふうに考えております。FOMCの参加者の年内の政策金利見通しについては、前回から0.5ポイント引き上げております。この背景につきましては労働市場の逼迫を受けて、特にエネルギー・食品を除くコア物価がなかなか下がってこないことに対する警戒感の一つの表れというふうに我々は受け止めております。やはり雇用インフレというのはなかなか下がらない、ということじゃないかなと思っております。今後FRBは金融引き締め効果のラグや金融・経済の上昇を考慮しながら、追加利上げの必要性を慎重に判断していくものとみております。
一方で、一連の銀行破綻はいったん沈静化しておりますが、急ピッチの利上げの悪影響が何かしらの形で顕在化するリスクというのは残存しております。極めて先行きの不透明感が強い中で、米銀の金融政策は岐路を迎えております。依然として予断を許さない状況が続いております。金融不安再燃のリスクにも配慮しつつ、景気への悪影響を最小限に抑えながら、インフレを鎮静化することができるか。FRBには慎重なかじ取りを期待したいと思っております。引き続き、米国の経済・金融市場の動向を注意してまいりたいというふうに思います。
2点目のご質問、銀行界のPBR1倍割れについてでございます。こちらにつきまして、PBR1倍割れにつきましては銀行に対する投資家の皆様からの現在の評価として真摯に受け止めて、企業価値向上に向けて不断の努力を続けることが必要だというふうに考えております。PBR1倍割れの問題は、銀行に限ったことではございませんが、少子化・高齢化に伴う内需の減少、低金利環境下における預貸利回りの悪化、運用難など、我が国の銀行を取り巻く経営環境は大変厳しく、銀行株のPBR1倍割れというのが常態化しているというのは皆様のご認識の通りであります。改めて銀行の存在意義とは企業の海外事業支援、地域経済の活性化支援、個人の資産形成支援、日本の経済活動を金融サービスの面から支え共に成長する、これが私は銀行の存在意義だというふうに思っております。大きな視点で言えば、日本経済の成長と銀行の成長の好循環が、持続的な成長を生み、PBRの改善に繋がっていくと、こういうことじゃないかなと思っております。
転じてPBRを改善させるための具体的な活動を考えますと、PBRの向上には高い資本収益性、高い期待・成長性、安定した収益構造、この三つが重要だというふうに考えております。これらを実現するには、高い成長率が期待される領域、例えばカーボンニュートラルに向けたトランジションを初めとするGX、SXの領域にリスク・リターンを踏まえた上で、適切な経営資源を振り向けビジネスに貢献していこうということ。また、そういった新しい分野でのビジネスを創出できる人材を育てるべき人的投資をしっかりと続け、社員と企業がともに成長する好循環を作ること。こうしたことが必要だと思っております。加えまして、こうした成長戦略を投資家を含むステークホルダーに丁寧に説明し、成長期待を感じてもらう。また、株主還元などを通じて、その果実を共有することも重要だと考えております。その際に大切なことは、お客様や市場・社会などステークホルダーの課題や期待を的確にとらえ、そのソリューションがステークホルダーの課題解決、成長に資することかと感じております。
資本規制を初めとする金融規制や、長きに渡る日本の低金利環境など、銀行業界特有の構造的な厳しさはありますが、政府からの金融サービスの高度化に繋げるべく、業務範囲規制などの緩和を政府が進めていただいております。金融機関の競争力強化はサービスの質の向上を通じて、お客様の利便性向上、ひいては日本の経済成長に資すると考えており、政府には更なる規制制度の緩和、環境整備をお願いしたいというふうに考えております。
Q.物価の現状や見通しについての受け止めは。
日本の物価の現状見通しということでございまして、コアCPIの前年対比というのはご案内の通り今年1月時点で4%を上回っておりましたが、政府の物価高対策の効果もありまして、2月以降は伸びがやや鈍化しております。しかしこれまでの資源高、円安を背景といたしました仕入れ価格の高騰を受け、食料品を中心に値上げの動きが高まっていることから、足元でも3%を上回るインフレが続いております。さらに6月からは電気料金の値上げも決まりました。加えてこれまで相対的に物価上昇の動きが鈍かったサービス分野においても、人手不足に伴う人件費上昇等を背景に外食や宿泊等の物価上昇率というのが高まっております。
今後に関しましては海外経済の減速に伴う資源価格の低下などを受けまして、輸入コストの価格転嫁圧力は弱まっていくものと予想しております。当面は過去のコスト上昇分を転嫁する動きが続く可能性がありますが、2023年後半にかけて輸入物価の低下とともに、コアCPI前年比は鈍化していく可能性が高いというふうに考えております。
中長期的には政府、日銀が目指す安定的な2%物価目標の達成には、賃金の持続的な上昇が不可欠であります。銀行としても持続的な賃金と物価の好循環を実現すべく、引き続き構造的賃上げに取り組んでまいります。
市況や為替動向は短期的な物価変動要因にはなりますが、基調的な物価を見る上では、私は労働市場の逼迫度であるとか、来年の賃上げを左右する今年度の企業業績などに注目していきたいというふうに思っております。
Q.市況が好調な要因についての受け止めは。
今日もあまり下がっていないと聞いていますね。日本の株価でございますが、株価の先行きに関しましては全銀協の会長としてのコメントはあまり相応しくないので個人的見解ということでお話させていただきたいと思います。今後も企業の経営改革への期待、そしてその取り組み、またグローバル対比で遅れていたインバウンド需要の回復を受けまして日本株は今後も底堅く推移していくものと期待をしております。足元の日本株は円安割安なバリエーション、諸外国と異なる緩和的な日本の金融政策に加え、インバウンド需要や東京証券取引所の経営改革要請を受けた各企業の構造改革、株主還元策などへの期待を受け、特に海外投資家からの買いが、株価上昇を牽引しております。株価上昇速度も速く、期待先行の側面もあることから、一時的な株価調整局面には注意が必要であると認識しております。
また、FRBによる金融引き締めを受けた米国経済の鈍化、あるいは米地銀の破綻の際に見られたような一連の信用懸念が起きた場合、実体経済、金融市場を通して日本株の下押し圧力になる可能性にも注意が必要です。引き続き市場動向を注目していきます。いずれにいたしましても、今後の株価上昇には日本企業の構造改革がいかに進んでいくかが重要だと理解をしております。お客様の経営改革およびビジネスをしっかり支えてまいりたいと思っております。
Q.銀行界のサイバーセキュリティ―への取り組みと、地方税一部税目のQR化について足元の利用状況は。
ご案内の通りだと思いますが、地政学上の要因もございまして、サイバー攻撃による被害件数というのは世界規模で増加傾向にあります。日本においても、例えば病院であるとか製造業等におけるランサムウェアの被害というのが報告されております。あらゆる企業においてサイバー攻撃の最新の傾向を踏まえたセキュリティー対策を検討する必要があると認識しております。特に金融機関は重要なインフラ事業者として、より一層強靭なサイバーセキュリティー対策を講じる必要があります。全銀協といたしましても、会員銀行のCIO、CISOといった、担当役職員向けにサイバーセキュリティーセミナーを開催する等、会員行のレベルアップと共助を促進する取り組みを推進しております。
また各行においても、サイバー攻撃を重要な経営課題と位置づけて、全社を挙げてサイバーセキュリティー強化施策に取り組んでいるものと承知しております。共助の観点では、高度化するサイバー攻撃に対抗するために、金融機関を会員として設立された「金融ISAC(アイザック)」に加盟し、金融機関同士が情報交換を行う等の業界横断的な取り組みを実施しております。全銀協として、銀行全体のサイバーセキュリティーに対する対応体制の強化を目指し、会員間の成功事例の共有など各種取り組みを進めていきたいというふうに思います。
続きまして2点目の地方税のQR化につきましてでございます。税公金の納付収納に関わる社会的な手間やコストこれは大変大きくありまして、ご案内の通り全銀協においては関係者と協議の上、QR納付というのを進めてまいりました。このような中、先ほどご質問いただきましたように、この4月から地方税の一部税目においてQR納付が始まり、4月・5月の2カ月間で約900万件の税金が納付者に金融機関等の窓口にお越しいただくことなく、スマホの読み取りで納付されております。
また、金融機関の窓口で納付された税金につきましても、そのうち約2400万件は、金融機関がQRコードを読み取ることで収納通知済書の仕訳であるとか、地方公共団体への運送といった後工程や地方公共団体における納付情報の消し込みや延滞確認等の業務が電子化、自動化されており、大変効果が上がっております。このように税公金の納付・収納の効率化については、納付者、金融機関、地方公共団体にとって三方良しの取り組みであります。今後QRで納付可能な種目が他の税目あるいは公金に広がることで、社会全体として効率性・利便性がさらに高まることが期待されております。我が国の人手不足が深刻化する中、業務の効率化、生産性向上、手間やコストの削減は極めて重要な課題であります。こうした認識のもと、全ての税目や公金へのQR拡大や、納税通知書、納税請求から納付・消込まで全ての処理が現実的に行われる社会の実現に向けて、引き続き地方公共団体や、関係省庁等と連携してまいりたいというふうに思っております。
Q.米国で広がる銀行規制強化の動きへの受け止めと、性的マイノリティーへの銀行界の対応について。
米地銀破綻を受けた銀行の規制強化と、こんなテーマだと思っておりまして、私は先日全銀協会長といたしまして、バーゼル銀行監督委員会のエルナンデス議長が来日された時に面談をさせていただきまして色々な意見交換をさせていただいておりますので、やはり会長として、今後の規制動向には大変注目はしております。ご案内だと思いますけど6月6日に開催されました、バーゼル銀行監督委員会の会合においては、直近の銀行セクターの混乱要因を棚卸して、得られた教訓を継続検討することが合意されております。監督の実効性を強化することの重要性というのが示されております。今後は監督、流動性リスク、金融リスク管理の有効性強化について検討を実施していくものというふうに考えております。また一方先日のG7におきましても、金融システムが強靭であることが再確認されて、金融危機以降に合意された金融制度改革をしっかりと実行していくことが示されております。シリコンバレーバンクの破綻であるとか、クレディスイスの急激な信用悪化というのは、ALM管理の失敗、業績不振、内部統制の問題であり、個社特有の事象であると私は理解をしております。そうした観点から言えば、必ずしもバーゼルⅢなどの規制変更や強化を前提とした議論が進んでいくわけではないというふうに理解をしております。
今回、米地銀で発生したことを振り返り、各金融機関における流動性管理を含めたALM管理や個別行に対する監督の十分性の点検や確認が必要となるということも考えております。また、SNSやインターネットバンキングの普及を背景としたデジタルバンクランという新たな課題への対応も必要です。金融システムの安定は極めて重要である。一方で過度な規制は、銀行の与信活動の消極化や、保有資産の圧縮を招く懸念もあります。規制強化による金融安定化と適切なリスクテイクによる円滑な信用強化のバランスが重要だというふうに考えております。
続きまして2点目に移らせていただきたいと思います。LGBT法案におけるマイノリティー対応ということでございますが、LGBT理解増進法案の議論を通じまして、多様性に関する理解が進み、全ての人が自己実現できる社会となっていくということは大変望ましいことだというふうに思っております。金融機関としても持続的な成長していくためには、多様なバックグラウンドや価値観を持つ役職員が活躍できる環境整備をすることが不可欠です。そういった環境の中で全銀協といたしましても、ジェンダー平等を実現しようと、SDGsの目標として掲げております。会員向けに人権啓発を目的とした講演会の開催や、会員行の新入行員向けに「みんなの人権を守るために」を毎年発行し、LGBTQ+を含めた人権の諸問題への取り組みを行っております。個別行の取り組みで大変恐縮でございますが、みずほにおいては国籍や性別、性的アイデンティティに関係なく多様な人材の成長と活躍を実現するダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを推進しております。
具体的には、採用や昇進、昇格等といった人事運営において差別的な扱いがなされないことを明示すること。人事制度、福利厚生等において、同性パートナーを配偶者と同等に扱うことなど、全ての社員に平等の権利を保障しております。また、社内外相談窓口の設置、ファシリティー面での対応を進め、社員の理解・啓発のための研修も継続的に実施しております。また2021年度からはLGBTQ+アライ企業として、同じ思いを持つ複数の銀行が連携し、私達から変えていくをメッセージとして掲げ、動画の発信や多様性理解のための研修なども行っております。このような取り組みを進めていく中で、銀行界として、共生社会実現を進めていきたいというふうに考えております。
Q.商工中央金庫の民営化に対する受け止めと、脱炭素など環境問題への銀行界の取り組みについて。
商工中金の民営化についてです。商工中金につきましては、22年の3月に終了した中期経営計画に基づく経営改革におきまして、事業性評価に基づく融資などの新たなビジネスモデルは概ね確立をされ、同時にガバナンス強化も進めてきているというふうに評価をされておりました。その上で昨日ですね、6月14日には改正商工中金法が成立いたしまして、公布から2年以内に政府保有株式が売却される見込みであるというふうに承知をしております。一方で当面は、商工中金法の存知や特別準備金、危機対応準備金の維持といった方針が示されており、財務・制度面で一定の政府関与が残るものと理解をしております。私どもは、政策金融機関については民業補完の原則のもと、民間金融機関との適切な競争環境と適切な役割分担が重要であると申し上げてきております。商工中金においても、直接・間接の政府関与が残るのであれば民業圧迫回避や民間との連携、協業深化に配慮した制度設計が必要です。民間金融機関との意見交換の場の設定、商工中金からの客観的なデータ提供などによりまして、適正な競争環境の確保、連携・競合の履行状況が確認できる体制や枠組みが構築されるような丁寧な議論を求めてまいります。同時に今後、商工中金法を廃止して、完全民営化する方針は維持されていると認識しております。
コロナ禍においては、官民金融機関が連携してお客様の資金繰り支援を行ってまいりました。足元では、アフターコロナへの移行が段階的に進んでいますが、資源・エネルギー価格の高騰やゼロゼロ融資の返済本格化など、お客様にとって厳しい経営環境は続いております。完全民営化については、こうした経済環境に配慮しつつ、商工中金の新しいビジネスモデルの定着、特別準備金などの自己資本の状況、危機対応業務の実施状況などが、慎重に見極められた上で適切に判断されるべきものというふうに考えております。
続きましてNGOの株主提案に受け止め方ということでございます。我々みずほフィナンシャルグループのみならず、他メガや商社に対しても、環境NGOから定款の変更要請がなされた報道については承知しております。個社の提案へのコメントにつきましては差し控えさせていただきますが、一般論で申し上げますと、定款は会社の基本的事項を定めるものであります。変更についてはその必要性および機動的な業務執行への影響を鑑みながら、各社で判断するものと考えております。一方で、環境NGOの求める2050年炭素排出ネットゼロ実現は、持続可能性のある地球を次の世代に繋ぐために大変重要なものと認識をしております。銀行のGHG排出量の対象は投融資を通じた排出すなわちスコープ3が占めており、顧客企業のカーボン・ニュートラルへの公正な移行を金融面からしっかりと支えていくことが喫緊の課題です。
個別行だけではなく、全銀協といたしましてもカーボン・ニュートラルの実現に向けた全銀協イニシアチブを策定し、中期的な視点に立って産業界、関係省庁とも連携しながら、お客様の移行支援に向けた会員各行の取り組みをさらに加速させていくための施策を講じています。
具体的には、顧客の移行支援に向けたエンゲージメントの充実、円滑化、移行計画の妥当性、信頼性を判断するための評価軸、基準の整理です。また、移行に必要な資金をしっかりと供給するためのサステナブルファイナンスの裾野拡大、発展途上にある投融資を通じた排出量把握も含めた開示の充実、銀行のリスクを把握・管理するための気候変動リスクへの対応を進めてまいります。これらの取り組みを進めることで、社会経済全体の2050年カーボン・ニュートラル、ネット・ゼロへの公正な移行に貢献していきたいというふうに考えております。
Q.銀行界でPBR1倍割れが続いていることの受け止めは。
PBR1倍割れということですが、PBRは株価に対する一つの尺度で絶対的なものではございません。従ってPBR1倍割れというのは資本収益性の低さであるとか、投資家に成長性を感じていただけないということの一つの表れでありましてですね、やはり我々銀行といえども上場会社でございますので、そういった点について私は真摯に向き合うべきだというふうに考えております。
社会分野とおっしゃっていただきましたけども、銀行の主要業務の預金、貸し出し、決済、こういった社会インフラ、言い換えれば我々としては幅広いお客様にご利用いただいてるということであります。利便性の向上、あるいは効率化、あるいはその付帯ビジネスを通じて、いわば収益性、成長性を高めるチャンスがあるという形でございます。なかなかそういう形で幅広くお客様と接点を持てる業界ってなかなか少ないと思います。そういう意味で言うと公共性を有しているということであるとか、あるいは社会インフラであるということをPBRの低さの言い訳にしてはいけないんじゃないかというふうに考えております。
一方で銀行業には、業務範囲規制であるとか資本規制など、銀行界特有のビジネス上の制約が課されているというのも事実でございます。銀行は社会インフラを担っているからこそお客様の利便性を高める必要があります。政府からは銀行業を取り巻く業務規制範囲、規制等の緩和を進めていただいておりますが、更なる規制緩和、環境整備をお願いしたいというふうに考えております。
お客様に対するサービスの向上を通じて、事業成長を続け、投資家の期待に応える与えるべき努力を続けてまいりたいというふうに思っております。
異業種連携

2023/6/13 SMBCグループとCCC グループの記者会見、新ポイントサービスに関する質疑応答
この動画はプレミアム会員限定です。登録すると動画をご覧いただけます。
関連記事:6月13日、ニッキンONLINE
Q.資本提携やポイント名称に関する交渉や検討の経緯について。
(三井住友FG・太田純社長)
交渉は極めてスピーディー、円滑に進みまして、我々色々なパートナーシップで色々な交渉をしましたけれども、増田会長を初めCCCの皆様ともスムーズにいった。もちろん色々な検討はあったがお互いの信頼関係と将来に対する展望で解決をしてまいりました。やはりなぜCCCさんかというと、やっぱりTポイントと、それからVポイントの統合したときのメリットということが一番多かったというのがございます。お互いに不足しているところを補い合って、これが一緒になると本当に貯まりやすく使いやすい、経済圏に捉われず自由に使っていただけるポイントができるということで、このメリットが一番大きいとお互いに感じたというところです。
Vポイントの名称につきましては先ほど増田会長からもご説明があった通りですけれど、この交渉の中でですね、VISAが直接出てきたということはございません。ただしVISAのグローバルネットワークを使えるという意味で、従来から使ってましたVポイントという名称をそのまま新しく使うということになった次第であります。
(CCC・増田宗昭会長)
皆さんと一緒にやろうということは今日皆さんプレゼンした通りで、新しい顧客価値が作れそうだと。特にポイントはポイントとしてではなく決済と紐づかないといけないということがありましたので、決済のVISAをお持ちの住友さんとというような判断でしたけれども、私どもの判断は元々TSUTAYAもフランチャイズで始めていますし、Tポイントもアライアンス企業の皆さんとやっている。つまり、事業会社の人と色々ビジネスを組み立てるという点で、私どもが経験してきたことで大事なこと。それは「好きか嫌いか」ということです。あんまり嫌いな人とやってもうまいこといったこともないので、太田さんと会った時に関西弁で言うと「おもろいおっちゃんやな」と思って、一緒にやりたいなと思って始まりました。
(CCC・髙橋誉則社長兼COO)
大西社長と私もですね、最初4人でご一緒した時から本格的な話し合いに入った。確か記憶しているのが8月に入って結構過ぎてからだったと記憶しております。そこから1カ月足らずですね、基本合意という形まで本当にスピード感を持ってご対応いただきましたことに本当に感謝しています。
(増田氏)
ちなみに、こういう大きな会社と提携するときは大体時間もかかりますし、後から後から色々な人の意見が出てきて、今更そんなこと言うのってのがよくあるケースだと思いますけれども、今回の提携に関しては、ほとんどそういうことはありませんでした。
(三井住友カード・大西幸彦社長)
私からも一言。大きな方向を増田さんと太田で会話した後で実務的には髙橋さんと私の方で進めましたが、非常に前向きにお互いがコミュニケーションして非常に早かったと思います。VISAにつきましては、一番最初に私どもがVポイントをリリースする前段階では、VISAの世界の中でもこういうVという名前を使ったポイントっていうのは世界で例がないものでございますので対応して進めました。今回はその我々が作ったVポイントを展開していくということですので、交渉は我々でやらせていただいたということです。
Q.今後の加盟店開拓について具体策は。
(髙橋氏)
こちらにつきましてはもう既にですね、パートナーシップのもとにSMCC様、もしくはSMBC様も含めてご一緒に営業を開拓というアクションですね。本当にチームを組んでご一緒させていただいております。それが色々な加盟店様にとってみてもバリューアップに繋がるような内容でご提案をさせていただいておりますので、もう既に現在進行形でご一緒させていただいています。
Q.各社の囲い込み競争が激しくなる中で勝ち抜くための戦略は。
(増田氏)
経済圏というのは、基本的に企業のエゴだと思います。やっぱり決めるのはお客さん。お店に来られる人もカードを使う人も、モバイルを使う人も決めるのはお客様。だから、私どもの考えはどこよりも価値のあるサービス、それを作り上げること、この一点が競争戦略だと思っています。詳細はまた改めてお話させていただけると思いますけれども、そういうふうに考えています。
(太田氏)
私も全く同じ考えでして、利便性が高くて、かつお得感があるポイントサービスを提供する。それが例えば決済だとかそういうのと結びついて非常に日常生活で溶け込んでいくと。そうなると自然と、例えばオリーブを使っていただける方も増えてくるでしょうし、それが結果としてビジネスの拡大に繋がっていくということでありますので、全部取り込んだ中で囲ってしまうというよりも、増田さんおっしゃったように、より良いサービス、より安いサービスを提供することによって、結果としてビジネスが伸びていくということを考えていきたい。
Q.「Tポイント」の名称が来春なくなることについての思いは。
(増田氏)
こう言ったら怒られますけど、こだわりっていうのはあんまりなくて。僕が見てるのはいつもお客さんです。お客さんにとってどうあるべきか、今回は、明らかにVISAさんを核とした「V」がお客さんにとって価値があるし、今やろうとされていることは、絶対これお客さんに伝えなきゃ駄目だと。その伝える方法が「T」で伝わるのか「V」で伝わるのかと。一時はVTポイントやろうかみたいな話も巷ではあったようでありますけれども、そういう企業エゴではなくて、本当にお客さんにとって価値のある名前が何なのかっていう視点で私は判断をしました。
Q.Tポイントの現状の価値についての受け止め。
(増田氏)
ぶっちゃけ相対的に価値は落ちたと思います。絶対的価値が毀損したとかっていうことではなくて、やっぱり世の中の環境が変われば価値は相対的に変化します。僕らのカード以前はスタンプカード。スタンプカードに何か貼ってポイント貯めたりした時期あったじゃないですか。それを僕らは磁気カード使ってデータを使ってお客さんに便宜を提供しましたけれども、今スマホっていうツール、あるいはキャッシュレスというツールがあったことにおける疑似通貨のあり様というのはそういうのではないし、それから僕、これからお札っていうのは、喋るお札に変わるっていうふうに思っています。そういうふうなことを考えたときに、僕らが単独でやるのがいいのかどうかということを考えたときに、もうお願いするしかないというふうに決めました。以上です。
Q.ポイント還元競争で事業者負担が生じている点について。
(髙橋氏)
ありがとうございます。確かにポイントの事業者が増えれば付与・還元競争というような形が起こるかもしれませんけれども、私どもで申しますと、従前来のポイントのアライアンス加盟店さんに、またクレジットを中心とした三井住友カード様の基盤、これは少し種別が違うインフラだと思っております。私どものTポイント加盟店様でお使いいただくときの、大体この付与の金額のベースというのが1000円以下の決済が非常に多いです。クレジットなので三井住友様でいうと当然数千円、数万円といったような規模でのいわゆる決済に対してポイントが付与されていくという形になります。また、お客様にとってみてもその使える場所も広がるというような形なので、他の事業者様と比べてどうというよりかはですね、お客様にとっての使えるバリエーション、貯まるバリエーションが増えていくことが私どもの価値だと思いますし、そこをすごく大事にしていきたいというふうに考えてます。
(大西氏)
それでは私からカードの観点から申し上げますけれども、お客様から見たお得感と便利だ、安全だ、というのがとても大事。私どものカードとかオリーブも、お得感と同時にアプリの機能やオールインワンになっているかとか、フレキシブルペイへの機能などに非常にこだわってやってまして、他のカードと違う便利さがあるというのが一番大事。ポイントについても同じことで、ポイントの使い方の便利さというのを可能な限り考えていって新しいペイを作りたいということではなくて、ポイントの便利さを究極まで追い求めようとすると、やはり決済アプリの機能も一体で合った方が良いなとか、そういう形で考えております。これからもお得感は必要だと思うんですけど、それだけじゃなくて、便利さと安全性というのを重視していきたいと思います。
Q.ポイント事業の変遷や将来のビジョンについて。
(増田氏)
まず名前についてはですね、よく旧姓っていうのあるじゃないですか。旧姓を覚えている人って少ないと思うんですよね。結局は名前の問題よりも価値のない、その人が本当に素敵だったり、その会社が本当に素敵だったり、サービスが素敵だったら「そのサービスの名前なんていうの?」というふうに生活に定着していくと思います。それを「俺は誰誰なんだ」っていうところになんの価値もないんじゃないかな、というふうに思っています。ですので名称については今みたいな考え方で、やっぱり価値を作ることが僕らの仕事であって、その価値が伝わる名称は何がいいのかという視点が大事だと思っています。
(1983年に創業、2003年にポイント共通化を開始、2023年にVポイントとの統合を発表したことについて)今お聞きしていて僕も改めて思ったんですが、確かに20年ごとなんですね。それは知りませんでした。今後20年ということを考えると多分僕は生きてないと思いますけれども、今回ここでキックオフをさせていただいたこの会場から20年経った時にどんなふうな生活が、日本や世界に定着していくのか。そういうふうなことを考えると、今日、色々具体的な施策もお話させていただきましたけれども、こういうことを本当にやることができれば、きっともっと世の中を面白くなると思います。競合がどうのこうのってことは僕はあんまり関心がありません。以上です。
Q.SMBCとしてマーケティングの面ではどのような展開に期待しているか。
(太田氏)
SMBC、SMFGの立場から申し上げますと、オリーブの会見でも申し上げたんですけれども、我々国内のリテール業務については徹底的にデジタル化をしていこうと思っておりまして、そのための方向性としてオリーブを立ち上げた。オリーブの中では銀行取引、クレジットカード取引、証券、保険あるいはコンシューマーファイナンス、いろんな機能を一つのアプリで提供しています。これは今後の我々のスタンダートになってくると思っているのですが、ここで一つだけ足りなかった機能がポイント機能なんですね。Vポイントは当然あるんですけれども、まだ知名度という点においても、あるいは使われ方、貯め方ということで十分に機能をしてはいなかった。増田さんにお目にかかって、Tポイントと一緒になるということで、この最後のミッシングリンクを埋めることができたと。ですから、いろんな金融サービスに加えて、そういうポイントを付け加えることによってこのポイントが非常に魅力があって、かつ利便性に富んだポイントになるということによって、これまでつながらなかったところにつながる。それによって、リテールとしては究極のサービスが提供できるというふうに思ってますので、ご指摘の通り私どものマーケティングに果たす役割といいますか、貢献度は非常に高いというふうに期待をしています。
Q.Tポイントにアクセスする際のログインの共通化に関して
(髙橋氏)
ご質問ありがとうございます。現時点におきましては特にサービスの変更というのは、予定はしておりませんので、今のご質問に対してお答えすると、特段、今は変わらないということであるということです。
Q.ポイントカードを提示しない「ワンオペ」で加盟店や顧客に変化は?
(髙橋氏)
はい、ありがとうございます。こちらにつきましてはそのようなサービスを開発して世の中にお出しすることができればですね、加盟店様にとってみてもですね、店頭での当然お客様とのやり取りの接客時間というのは短ければ短いほど、私もお客さんになる時がありますが、大変お客様にとってはバリューアップするということでございますし、またそういった意味でいろんな仕事をですね、接客以外の時間にも向けられるというところでの効率化といったところも含めて、加盟店様にとって非常に価値があるんだろうなというふうに思います。
(大西氏)
私からも、いわゆるポイントと決済が別々に動いてたところがありまして、なのでなるべくいろんなプロセスを一体にしていこうというのがキャッシュレス時代では重要かなと思っています。そういう意味でワンオペというのも申し上げましたし、アプリを見て支払い履歴にクリックしていってポイントを後に付けるというふうな機能もご用意する。この辺りはどんどん新しいサービスを開発していきたいと思います。
金融業務

2023/5/15 3メガバンクG決算会見、質疑応答④ 人材採用について。中途採用が活発化する中で求める人材は
この動画はプレミアム会員限定です。登録すると動画をご覧いただけます。
三井住友FG
新卒採用については、やはり安定的に採用していくことが大事だと思っています。どこかで採用数を大きく下げる、減らしたいということではなくて、しっかりと人員構成をメンテナンスしていくためにも安定的に採用していく方針に変わりはないです。今はいわゆる旧一般職を採用していないため、総合職と総合職リテールコースの2種類の人数については今後も安定して採用していこうと思っています。
一方でご指摘があったように離職者の比率が増えているのは確かです。加えて求められる人材が多様化していて専門人材も必要になってきていることから、中途採用や外部採用についてはこれまで以上に数が増えていくと思っていますし、例えばいったん転職した人が帰ってくる人も含めて多様な人材を採用していきたい。したがいまして外部採用や中途採用の人数は今後も増えてくると考えていますし、しっかりと戦力化したうえで戦略に沿った人員配置を効率的に行っていきたいと思っています。
みずほFG
注力領域において専門性を高めていく必要があることですので、当然、注力領域の人材を増やしていきたいというのはあります。去年は採用人数は570人ですね。ですから前年度から飛躍的に拡大した。実はみずほは厳しいんじゃないかっていうのがあったんですけれども、実際にはかなり中途のマーケットでは、みずほは積極的にとっているのと、入っていただいて仕事がしやすい環境だという認識でわりかし人気が出てきてるかなと思っています。
従って中途については、やはりどうしてもですねこれから生産年齢人口は減っていくということがあるので、中途採用を積極的に活用しながら人材の質を上げていくということをやりたい。そういうふうに思っています。
経営資源は人間ですから、やはりそのビジネスとして注力というか、しっかりと資源を投入して、企業価値を上げていくことが極めて重要だというふうに思います。一方でやはりビジネスだけではなくて、ご説明した基盤みたいなところもすごく重要だというふうに思っています。(資料から)企業風土の変革・DX・人的資本・ITの改革・安定的な業務運営、この五つは極めて重要で、ここをしっかり進めながら、我々の企業価値を高めていきたいと思っています。
MUFG
いわゆるキャリア採用は、当たり前のことになっていますし、去年は年間の採用数の4割ぐらいはいわゆる中途採用で、新卒一括採用が6割という構成だった。かつ新卒一括採用もコース別採用と一般採用があって、コース別採用は3割ぐらいありますので、そこもある意味で専門性ということで、専門的な人の採用が増えてきているというのが今の状況で、我々もやはり専門性が必要になってきているということですし、またそれをどんどんみんなにも発揮してもらうということ進めていますので、そういう方向になっていると思っています。
まずシリコンバレーバンクからの採用は20人ぐらいで、5人位はいわゆる主要メンバーと言われる人で20年近くとか20年以上シリコンバレーバンクで活躍していた人達です。我々は3年ぐらい前から、いわゆるエマージングとかミドルマーケットのテクノロジー企業向けの銀行事業を強化しておりまして、米州トップのケビンもかなり力を入れている分野で、そこの強化につながるということです。それから我々は、マーズ・グロース・キャピタルという、シンガポールでイスラエルのAI企業と一緒に組んで新しいスタートアップ向けのビジネスを始めて2年半くらいが経ちます。この辺りも含めてスタートアップ向けの融資は重要だということで進めております。
金融業務

2023/5/15 3メガバンクG決算会見、質疑応答③ PBRに関する分析と今後の方針について
この動画はプレミアム会員限定です。登録すると動画をご覧いただけます。
三井住友FG
PBRにつきましては、東証の指摘もあってPBR1倍を目指していくには、というロードマップについて(資料にも)書いている。株価を伸ばしていくことは我々の力だけではどうしようもないことがある。マクロの環境が大きく関係してくることのため、今後の環境変化に期待したいところだが、我々としてできることはやはりきちんと計画を示してそれを実行、実現していくことが一つ。
もう一つは情報の透明性を高めること。つまり、投資家の皆さんとの情報格差を是正していく。それから、非財務情報を含めて情報量を増やしていくことによって投資家にとっての資本コストを下げていく。この二つ位しかやりようがない。PBR1倍を目指すに際してそれをしっかりとやっていく。繰り返しになりますが、(資料にも書いてあるが)PBR1倍を実現するには外部環境の変化も必要で、我々としては出来る限りのことをやっていきたい。
みずほFG
PBR1倍以下っていうのは、それでいいとは到底思わないですね。したがって、中計の3年後、最終年度のROEが8%超なんですけれどそれで満足するものではないし、もっと上げるべきとそういうふうに思います。
一方でご説明した通り、ディスカウント要因があるんですね。みずほが自分の努力によって解消できることはやりたい、しっかりやりますけども、日本全体のマクロ要因は私どもだけで何とかできるものでもないですね。ただ、今回の中計の中では、そこに対してもやっぱり積極的に働きかけていこうと。例えば私どもとして、日本の企業の時価を上げていくための努力していこうじゃないか、成長支援をしていこうじゃないか、もっともっとですね。そういうことによってPBRを上げていきたいということなので、なかなか自分たちだけでできないんですけれども、そういったところにも働きかけをしようっていうのが今回の中計ということです。
MUFG
東証のPBRについては、これはもう私の就任の時からやっぱりPBR1倍を割れているのは経営として非常に大きな課題だということで、我々自身いろんな形で、成長性をどう見せるか、ここが一番重要だというふうに思っていますし、まずは我々としてはROEとPBRに極めて相関が高いので、ROE を上げるいうことからまずはちゃんとしていくということで、今中計で7.5%、それから中長期で9~10%という目標を立てています。このROEをきちんと上げていくというが極めて重要で、足元それぞれのリスク・リターンの改善を進めていくということに尽きると思います。
金融業務

2023/5/15 3メガバンクG決算会見、質疑応答② 欧米やアジアなどの海外向け貸出戦略について
この動画はプレミアム会員限定です。登録すると動画をご覧いただけます。
三井住友FG
昨年度は特にアメリカにおきまして、債券市場がまず金利高になったものですから、お客様はボンドの発行よりも銀行借入に頼られたということがあります。それを中心に米州における残高が増えております。これはひと段落していてこの状況がずっと続くとは思っていません。ただ、一般論で言いますと引き続き、内外の資金需要は決して悪くないという情勢になりますので、一定程度の比率で着実に残高が増えていると見ている。一方で、景気を初めとして金利動向等不透明感があることは確かですので、クオリティ、与信の質についてはしっかりと見定めながらアセットをコントロールしていきたい。
みずほFG
一つはやはり米州の社債マーケットが昨年は低調だった。その調達が間接金融である貸出に来たということだと思います。第4クォーターに若干残高落ちてますね。それはキャピタルマーケットに回避していた人が貸出を返したことによるものです。一方で私どもはグローバルの観点から採算性をかなり意識した運営を再度強化しようと思っています。従って貸出については、貸出先じゃないんですけれども、低採算先については、そこに張り付いている資本を落としていくので、無尽蔵に増やしていくことではないということです。
それから欧州はものすごく難しいマーケットです。従ってここは軽量化と効率化を進めるやり方でやりたいというふうに思っています。
MUFG
(海外貸出は)まず4.5兆円、為替を除いて減っているという表示があったと思います。ただユニオンバンクの分が7.5兆円あって、実質は3兆円増えている状態です。なので海外貸出は3兆円増えています。それから我々自身は3年前からリスク・リターンをどう向上させるかということで、非常に利回りの低い、利ざやの低いものについては売却したり、入れ替えたりしましたので ここにきて入れ替えも終わりつつあるので、今からはリスク・リターンの高い貸し出しを増やしていく。比率をもってリターンを上げていく。量を増やしながらも、利ざやも伸びていく、まあそういう形ができてくるのかなと思っています。
金融業務

2023/5/15 3メガバンクG決算会見、質疑応答① 海外の金融不安が残る中でのリスク認識について
この動画はプレミアム会員限定です。登録すると動画をご覧いただけます。
三井住友FG
シリコンバレーバンク以降ですね、カリフォルニアにおける地銀の経営破綻については現状ではこれから大きく広がって金融システム不安につながるというところまではいっていないと認識している。FEDが非常に素早く対応したこともあって、当面の騒動は沈静化しつつあると思っていますし、我々の業務に与える影響は極めて限定的であります。ただし、ご指摘があったようにそれが米国のマクロ経済にどのように影響していくか、あるいは彼らが得意としていたスタートアップにどういう影響を与えるのか、更なる危機の序章につながらないかは引き続き慎重に見極めていく必要がある。したがって、注意は継続していくが今すぐ大きな事態が発生してきているという認識ではないということです。
みずほFG
シリコンバレーバンクとか、ファーストリパブリックで起きたことが相似形のように私どもの米州で起きるかということは多分それはないかなと思います。
スタートアップ等々の預金、私どもの米州の場合、日系企業さんとか大企業さんなので、基本的にはそのバンク・ランが起きるような先ではないかなというふうに思います。ただ一方でこれで終わったかどうかと、これからのリスクはまだまだ一旦ちょっと収束したように見えますけれども、米銀の中堅どころの破綻というのはこれからも続くかもしれないし、さらにいうと、地銀さんの問題はまず氷山の一角で、思えば金利がこの1年で0%から5%に急速に上昇したんですね。それはいろんなひずみが生じてるはずなので、やっぱり私どもといたしましては、やはり取るクレジットとかそういったことについては、十分注意していくことが必要かなと思います。
MUFG
(米国について)バンク・ランについては、もちろん日本の場合は預金保護の考え方がかなり違いますし、SNSでいわゆる噂が広がるということと、インターネットバンクのような、いわゆるデジタルバンクですぐ引き落とせるということの二つがある。我々としてはいろんなストレステストを見ているなかでその辺もカバーしていますが、いずれにしてもこれまでと違う形でのスピードみたいなのが、特にSNSの情報のスピードが非常に速いので、この辺りは我々も注意していく必要があると思います。
金融業務

2023/4/21 楽天銀行 東証・プライム市場 上場記者会見
この動画はプレミアム会員限定です。登録すると動画をご覧いただけます。
Q1.上場の意義と上場の先に目指すことは。
今回の上場につきまして、私どもの企業価値の向上を加速させるという意味で上場を申請させていただきました。具体的に申し上げますと、27年3月期までの中長期ビジョンを発表させていただきましたが、これを実現するためには少し現状の資本では足らない。ですから私ども今回、上場にあたって公募増資をさせていただきましたが、27年3月期までに皆さんにお示ししている成長戦略を実現するために必要な支援を調達する。これが一つ目です。
二つ目ですが、今後ビジネスをやっていく上でさまざまな資金調達の必要が出てくる可能性がある。上場しておくことで選択肢が増えるということがございます。我々としてはできるだけ柔軟な資金調達を実現したいと考えております。そういう意味で、将来のオプションを増やすという意味で今回上場させていただいた。
それから三つ目。27年3月期までに向けて、今後成長を加速していくにあたって、我々は今でも楽天グループの子会社として消費者の皆様から一定の認知をいただいておりますけれども、今回上場することによって、さらに楽天銀行の認知度が上がる。この認知度の上昇を活用して、成長を加速させたい。これが三つ目。いわゆるこの三つとも、我々が今後、企業価値を上げていくに当たって必要な要素であろうというふうに考え、今回上場する申請させていただき、お認めいただいて今日上場ができたということでございます。
Q2.海外機関投資家の貴行への興味に関しての受け止めは。
海外投資家の方が特に興味を示されるのが、我々が楽天エコシステムを使って事業の成長をこれまで実現してきた。今後ともその可能性、ポテンシャルが非常に高い。ここでございます。いわゆる、これだけの大きなエコシステムを活用できる銀行というのは、グローバルに見てもそれほど多くはない。いわゆるユニークな事業展開をしている企業であり、それが将来に向けて成長の可能性が高いということが海外投資家の皆様から一番興味を持っていただいたであろうと思っています。
Q3.自動車・リテール・住宅とのBaaS戦略を検討しているのか。
これについてはストレートに言いますと、お話をいただいたことがあるもの、というふうにご理解ください。この中で、引き続き検討しているものもあれば、お断りしたこともあるということは事実ですので、この全てが今生きているパイプラインかと言われればそうではないということです。しかしながら、逆に言えば、例えばある業界のA社さんがそういうお話をいただいたということは、ある業界のB社さんからもお話をいただける可能性があるということであり、もしかするとA社さんでお断りしたけれどもB社さんではお話を進めさせていただくという可能性もあります。そういう意味で、こういう形でお示しをさせていただいております。
Q4.配当性向など株主還元に関する考え方は。
まず、我々の目の前には大きな成長のチャンスがあります。その実現のために今回公募増資をさせていただきました。そういう意味で、短期的には私ども成長戦略の遂行に周知をさせていただきたいと考えておりますので、配当については無配という形で考えております。しかしながら、数年経った段階で成長戦略が予定通り実現できているのか。もしくはそのときに投資家様から見られたときの要求水準というのが今と同じなのか違ってるのか。環境は当然変わると思いますので、数年経った段階では当然レビューをして、そのときの状況を踏まえて、引き続き無配の戦略でいくのか、もしくは配当の支払いを含む資本政策をやっぱり考え直すべきなのかということはその段階で再度判断するということですが、短期的に言うと無配でいかせていただきたい。
Q5.楽天エコシステムの在り方とコストに関する考え方について。
まずエコシステムの活用ということですが、これについては先ほどエコシステムでどういうところからメリットを得ていますかという一番最初のところになりますが、新規のお客様、これが多分一番大きなポイントになります。ご存知の日本の人口1億2500万人位の中で、楽天会員というのは1億人を超えてますので、個人のお客様を獲得するためにリーチすべき顧客基盤という意味では、極端な言い方をすれば、エコシステムだけをカバーしていてもほぼ全ての日本のお客様にリーチができる。そういう意味で我々エコシステムを最大限に活用してということを申し上げております。
一方で例えば、今でも非金利収益のうちのエコシステム、いわゆるグループのサービスから得ている非金利収益は我々大体25%ぐらいで、75%ぐらいは外から得ている。つまりどういう構造になっているのかというと、楽天の会員の中から新規のお客様を獲得して、そこはエコシステムの活用ということを言ってるんですけどもね。そこから実際にそれをマネタイズする場合っていうのは別にエコシステムの中だけに依存しているわけではない。ただし、エコシステムの活用の意味でお客様の獲得後の話について申し上げると、グループのサービスと連携した便利なサービス、例えば楽天証券と連携したマネーブリッジのような連携など便利なサービスを提供することによって、お客様は楽天銀行に対するロイヤリティが上がります。
そういう意味で言うと、ロイヤリティを上げることによって、お客様はもっと我々のサービスを使って外部から得られる収益も増える。ですから、ご質問に対しては、我々は新規の顧客獲得はエコシステムにかなりの程度依拠している。しかしながら、その後の収益の獲得という意味では、エコシステムのみに依拠しているわけではなく、今でも大半が外から得られる収益ことであり、かつ、新規のお客様については、エコシステムに依拠することによってほぼ日本のコンシューマーにはリーチができますということですので、あえてエコシステム外の新規のお客様を取りに行く必要があるかというと、そこは効率が悪くなるだけではないかと考えています。
次にお金をところですが、これについては、我々にとって一番お金がかかるのはシステムコストなのですが、私ども実は日本の銀行では珍しいと思いますが、自社の社員がシステムの開発をして運用し保守をする、全てをコントロールする。多くの日本の銀行さんの場合ベンダーさんに依存しているとかかなりあるわけですけど、我々は社員が全てコントロールする。そういう意味では、実は同じシステムを作っても、他の銀行さんよりかなり安いコストで作れるし、運用コストも低い。
システムは確かにお金がかかるのですけど、毎年投資をしてきているっていう。今後例えばどこかでシステムコストが膨大に膨らむかって言われると、いや、毎年コンスタントに投資をしていくことが大事であって、どこかで大きく膨らむことは多分その必要はないだろうと思っています。そういう意味では、現状プラスアルファぐらいの投資は今後ともシステムについてはしていきますけれども、多分お知りになりたいことはどこかで大きな支出がいるんじゃないかとか、そういうご質問の趣旨だとすれば、我々としては現状の時期投資戦略の延長線上で全てのものはまかなえるだろうと考えています。
Q6.親子上場に関する考え方と投資家への説明について。
親子上場については、やはり最大の問題は、特に株主様の視点で少数株主様の利益が守られるのか。これが非常に大きなこと。そういう意味では逆にもう少し具体的に言うと経営の独立性はどうなるんだ、とこういうことだと思います。
実は私どもの場合は、元々楽天グループ株式会社100%子会社でしたが、金融・行政面でいうと経営の独立性を従来から求められます。すなわち、楽天グループ株式会社は従来100%の親会社ではあったものの、銀行の経営に指示をしたり口出しをしてはならんということで、加えて、その独立性を守るための仕組みも既に実際に我々の中で構築され、長年運用してきたという実績がございます。
これを運用していくことによって、十分に私どもについては少数株主様の利益を害するようなことがない事業運営および意思決定ができると考えています。
一方で様々な投資家さんとお話をすると、少数株主様の視点から見ても、楽天銀行が経営面ではなくてビジネス面で楽天エコシステムを活用して事業を拡大し収益性を高め企業価値を上げていけば、少数株主様の利益にもかなうということで、これについては少数株主さまの皆さん、多くの方からもご賛同いただきます。
そういう意味でいうと、大事なことは、ビジネス面では楽天エコシステムとのシナジーを追求するが、しかしながら経営面では従来通り、経営の独立性をきちっと確保する。これをやっていくことによって、親子上場の問題については解消できるのではないかと思います。
Q7.公開価格や公募増資等について証券会社とどのような議論があったのか。
株価ですが、これについてはもちろん私どもの業績がベースになり、我々の成長可能性がどのぐらいあるかということは当然材料になる。しかしながらその中で、その時々の株式マーケットがどういう状況かということであったり、投資家様のセンチメントがどうであったりとこういうことが影響して、総合的に判断されるのだと思っています。私どもについては、例えば、最初に目論見書に価格を記載させていただいていくらだったとか。ブックビルディングのときいくらだったとか。ブックビルディングの結果いくらに決まったとか。今日の初値がどうだっだなどそれぞれあるのですけれども、我々としてはこれについては私どもの業績や将来の成長可能性については、これは我々がきっちりと責任を持ってやっていく。株式マーケットの状況や投資家様のセンチメント等については、これは我々ではコントロールできない問題なので、その時々で証券会社のご意見を伺いながら、最も適切な価格を決めていくということであろうというふうに思っております。そういう意味では、それぞれのタイミングで適切な価格を決めた結果として、ある時点である時点を比べたら上がったとか下がったとかこういうことあるんでしょうけども、我々としてそれはいつのタイミングでも起こりうるものだろうというふうに考えています。
Q8.今後増資を考えた場合、配当を増やす考えはあるか。
もしかすると発音が良くなかったかもしれないので正確にお伝えしますけども、上場で申し上げたことが三つありまして、一つ目は公募増資です。これは明らかな増資です。二つ目は、将来資金調達が必要になったときに、そのための柔軟性オプションを確保する。
資金調達の中には当然資本調達を含みますが、デットの調達も含みますので、必ずしも資本だけのことをお話したわけではない。私の発音が悪かったとすればお詫びを申し上げたいと思いますが、まずそういう趣旨だということをご理解ください。これが一点です。その上で、そうは言ってもその中には資本調達が入ってるんだろうと言わればその通りです。ただ、最初の公募増資で私どもが既にお示しさせていただいてる27年3月期までの中長期ビジョンを達成するために必要な資本を調達するということが今回の目的であり、そのために公募増資をさせていただきました。すなわち、27年3月期までの現状の成長シナリオを実現する上では、今回の公募増資の金額で必要な調達はできているということですから、そういう意味ではこの成長戦略が何か大きく変われば別ですけれども、そうでなければ、27年3月までの必要な資本調達は終わっていることをまずはご理解下さい。
次に、その先も含めてということであれば、当然資本調達の可能性はゼロとは申し上げません。ただそのときに、配当するかしないかについては、逆に言えば、我々としてはそのとき何のために資本調達が必要になる。その資本を出していただく投資家さんの立場から見たときに、配当を払うことが合理的なのか、配当を払わずに、その資金を成長に回した方が合理的なのかっていうことは、投資家様との話し合いの中で決めていくべきことだろうと思いますので、我々としてはそれはその時、何のために資本調達が必要なのかによって、もしくは投資家様のそのときの考え方によって配当の有無はは変わってくると考えています。
Q9.口座数に占めるメイン口座比率が伸びている理由、他行との比較、口座振替が占める割合は。
なぜメイン口座が伸びてるか、もしくはメイン口座比率が上がってるか。我々の場合、口座数が増えてますのでメイン口座比率と口座数の増加を掛け合わせるとメイン口座でかなり大きく増えるという構造にあるわけですけども、それはなぜか。それは、私どものサービスをお客様に実際に使っていただくと、どれだけ他の銀行よりも便利かということをお客様が実感している。これが一つ。もう一つはお客様がサービスを使えば使うほどポイント差し上げる、楽天ポイント差し上げる。そうするとお客様からすると他の銀行のサービスを使うよりも、楽天銀行のサービスを使えばポイントがもらえるから得だということになる。すなわち、利便性と経済合理性。この二つが揃うことによってお客様はより我々の口座を使う。そうなってくると、だったら給与をここに入れれば色々なサービス使うことが簡単じゃないかと。他のところに給料を入れていると、そこから銀行に振り替えた上でサービスを使わなきゃいけないわけですが、そうではなく、ここに給料が入っていればそのまま使えるから一番いいんじゃないかとか。ご自身の生活の中で電気代、ガス代、水道代、もしくは携帯電話代金だとかクレジットカードの支払いだとか様々なものがございますけれども、そういう引き落としについては、楽天銀行に集約した方が便利だよねと。こういうことになってメイン口座が増えている。
二つ目に他の銀行数と比較ですが、多分他の銀行さんできちっとメイン口座比率を出されてるところは非常に少なくて、加えて銀行によって定義も全く違うので比較不能だというふうには思ってますので、ここについてはお答えできるだけのデータが世の中にないということでご理解をいただければと思います。
それから三つ目ですが、メイン口座の我々の定義は、給与振り込み口座もしくは口座振替口座ということでございます。その中でこの内訳ということですが、内訳は開示させていただいておりませんが、しかしながら口座振替口座の方が現時点で給与振込口座よりも多いということはお伝えをさせていただいておりますので、そこについてはそういうことでご理解いただければと思います。
Q10.上場のタイミングについて。
私どもとしては昨年の7月に上場申請をさせていただいて、そこから東証の審査を受けてきたということです。東証の審査と併せてマーケット状況を見ていたことも事実で、その中で結果として、東証さんからOKをもらい、マーケット状況もまずまず揃ったところがこのタイミングだったということです。
Q11.親会社も含めた将来的な資本政策について。
公募増資については先ほど申し上げたように、27年3月までは今の計画を前提とすると必要な資本調達はできていますのでこれ以上の公募増資は現行計画を前提とすると27年3月までは必要ないというふうに考えています。一方、売り出しについては親会社が決めることなので、我々が決めるわけにいきません。しかしながら、楽天グループ株式会社は今回のIPOに当たり、楽天銀行を連結子会社のステータスを維持した上で上場させるということを発表しておりますので、それを前提と考えるとですね、楽天グループ株式会社として、ここから売り出しをすることについてはちょっと現時点で私としてはあまり想定はしていないということですが、最終的には親会社の判断だということは思います。連結子会社で今63%ぐらい多分持ち分があると思いますので、そういう意味ではいいところなのかなという気はしております。
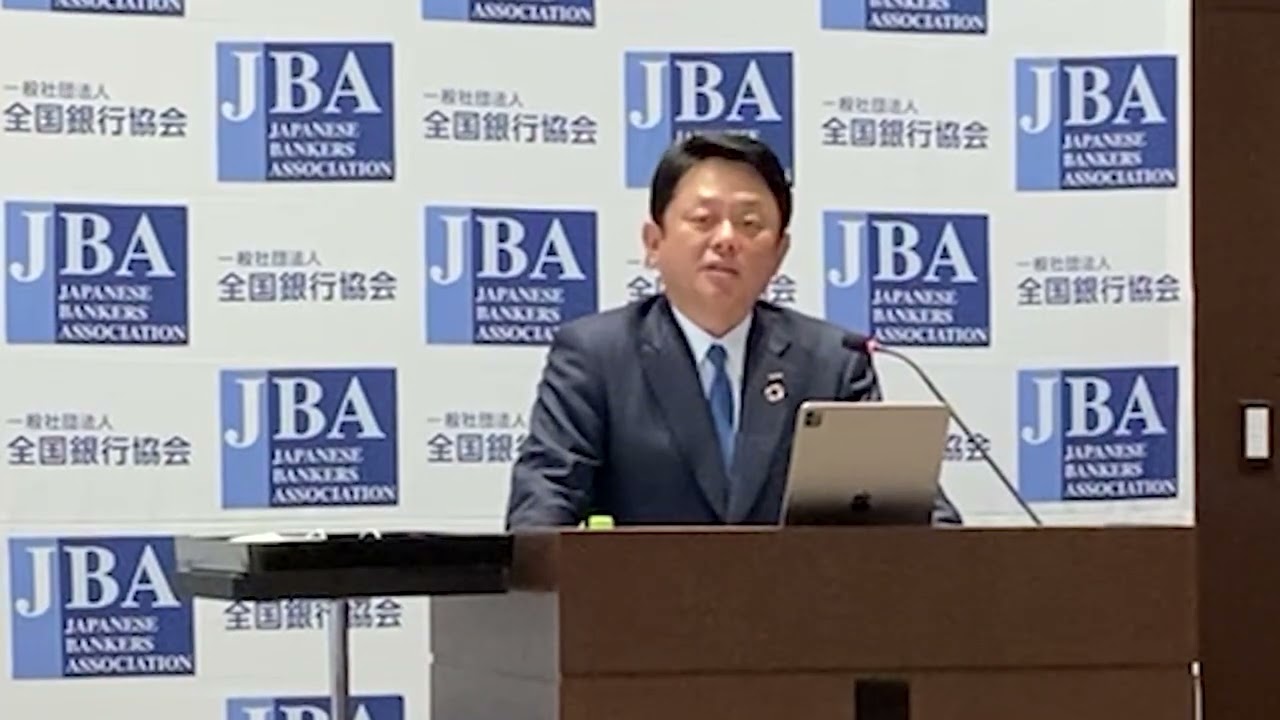
2023/4/3 全銀協会長会見 ゼロゼロ融資と銀行界の人材確保について
この動画はプレミアム会員限定です。登録すると動画をご覧いただけます。
2023.04.04 18:52
Q.ゼロゼロ融資いわゆる中小企業の資金繰り支援については。また、銀行界の人材確保について。
ご案内の通り、銀行界はコロナ禍における資金繰り支援を最優先に取り組んでおります。2022年度12月の全国銀行の貸出残高は約565兆円ということでありますが、コロナ前の2020年と比較すると57兆円増加しているんですね。そういう意味ではまだ依然として増加傾向にもあります。非常にしっかりと対応しているということでありますし、足元、コロナの感染法上の位置付けの見直しが予定されておりまして、ウィズコロナへの移行が段階的に進んでおりこの部分は明るい見通しだというふうに思っております。
ただ一方で、原材料やエネルギー価格が高止まりして、いわゆるゼロゼロ融資の返済が本格化するということでございます。コロナ禍で大きな影響を受けた飲食や宿泊業、こういったサービス業は、今かなり改善の方向にありますが、やはり資源高の影響を受けやすい運輸業であるとか、建設業をはじめとする幅広い業種でお客様の資金繰り負担に注意が必要であると認識しております。実際に東京商工リサーチの調査によると、23年2月の企業の倒産件数は577件ということでありまして、22年の4月から11ヶ月連続で、同年同月を上回っており増加傾向になっております。このような環境にあって銀行界としては資金繰り支援というのは最優先に行っていく方針に変わりはございません。
本年1月に民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のための保証制度、いわゆるコロナ借換保証、こういった公的な整備も準備されております。また全銀協においても、本年2月に資金需要に柔軟かつ積極的に対応し、金融仲介機能の発揮に全力を挙げて取り組むことを各会員行で申し合わせたところであります。同時に、お客様の持続的成長を支えるためには、お客様と金融機関が一体となった早期の事業再構築の検討であるとか、収益性改善のためのビジネスマッチングの提案、事業承継に関するコンサルティングといった非財務面での支援も欠かせないというところであります。なお、今申し上げた事業再構築に関しましては2022年4月に中小企業の事業再生等に関するガイドライン、いわゆる事業再生ガイドラインの提供が開始されております。これは事業再生における中小企業者、金融機関のそれぞれの役割を明確にするとともに、迅速かつ柔軟な事業再生等の手続きを定めたものであります。適用開始後、各会員行においても本ガイドラインの活用事例が徐々に積み上がってきております。今後、事業再建に取り組む選択肢として一層活用されるべく、銀行間で事例や課題の共有を図っていく予定であります。今後も、引き続き資金繰り支援に万全を期すとともに、お客様の事業環境を丁寧に把握し、その経営課題に一つ一つ向き合っていくことで、金融面から我が国経済、地域をしっかり支えていきたいというふうに思っております。
2点目は人手不足について銀行としてどういう対策があるかということです。銀行のみならずやはり人手不足、働き手不足に悩まれている経営者の方が多いと思います。銀行界にとっては、そういう意味で言うと課題として二つあると思っていまして、銀行自身の人手不足、あるいはお客様、お取引先の人手不足ということだと思っていす。これらの課題に対して全銀協で取り組んでおりまして、デジタル技術を活用した省力化について2点ほど事例をご説明させていただきます。
一つ目は地方税のQRコード納付です。この4月から自動車税や固定資産税など一部税目について、納付書にQRコードが記載されます。これによりまして、お客様はスマートフォン等を使っていつでもどこでも納付ができるようになる。加えまして、銀行サイドも銀行の事務処理が減ります。さらに地方公共団体においても消し込み作業が自動化できる、いわゆるその三方良しの取り組みであります。もう一つは手形小切手の電子化です。手形小切手も税金と同様に複数の関係者間で紙が流通して、それぞれにおいてその処理が行われておりますので、これを電子化することによって企業、地方公共団体、銀行の人手というのが省力化することは期待できるものです。なかには現状の業務フローを変えることに抵抗感を持つケースもありますけれども、銀行界としては、サービスの利便性向上や周知活動、手数料の見直し等の取り組みを通じて、しっかりと電子化を推進していきたいというふうに思っています。
この他にも、各個別行においてもそれぞれテクノロジーの活用による効率化であるとか、成長分野の効果的なリソースアロケーション、こういったことをビジネス戦略を踏まえて人手不足の中でも最大限のパフォーマンスの発揮に取り組んでいるという状況かと思います。この施策を進める上で重要なことは人への投資であるというふうに考えております。デジタル競争の激化やサステナ対応など急速な事業環境の変化に対応し、付加価値を創造できる人材を育てるというのはやはり継続的な研修教育が必要だということであります。加えまして個々に置かれた事情により、働きたいのに働けない人がいることは社会全体の損失でもあります。企業には多種多様な人が柔軟に働ける職場環境作りが求められるということであります。また、そうした経済面も含めて企業が社員を支援することで社員のエンゲージメントを高めて、企業の持続的な成長に繋がっていくとも重要であると考えております。
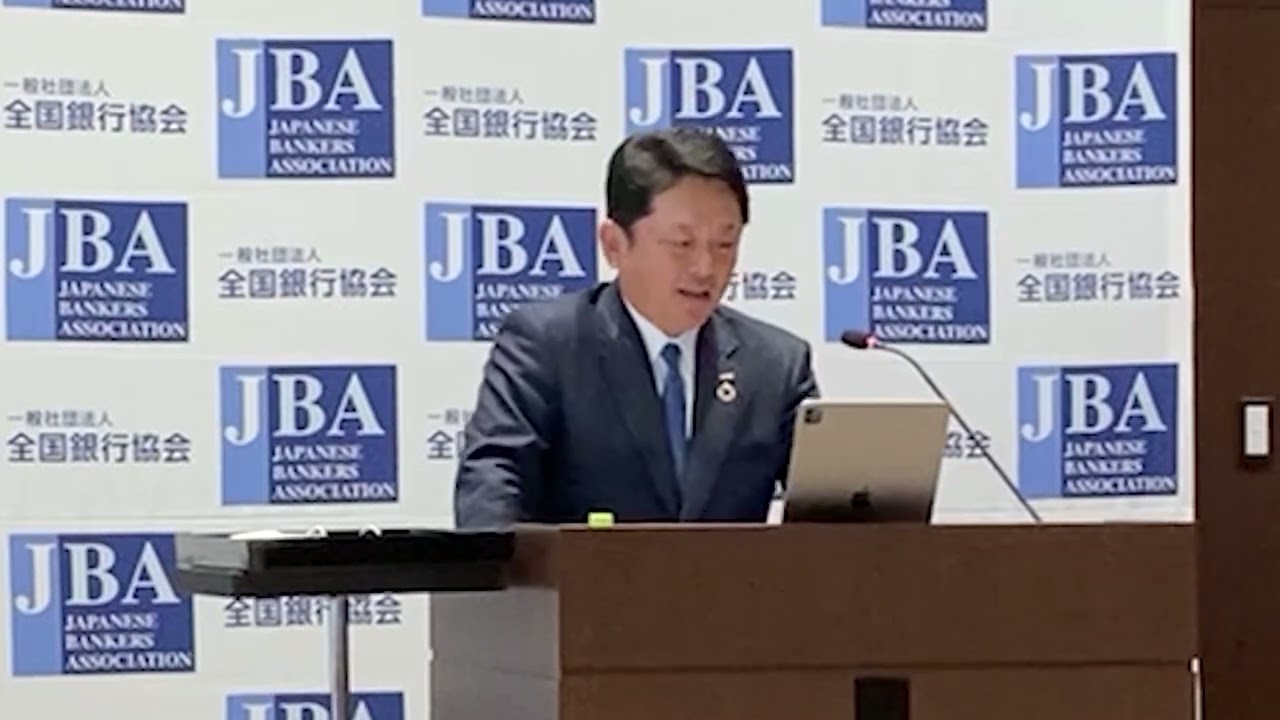
2023/4/3 全銀協会長会見 進むデジタル化での店舗の役割、ファイアーウォール規制の2023年度の見通しについて
この動画はプレミアム会員限定です。登録すると動画をご覧いただけます。
2023.04.04 18:46
Q.デジタル化が進む中で店舗の役割・あり方をどう考えているか。また、ファイアーウォール規制の2023年度の見通しについて。
1点目はデジタルと店舗の役割ということだと思っておりますが、デジタル化の進展というのは、お客様との接点が大きく変化するものですが銀行店舗の役割はやはり引き続き残っていくものだと思っています。デジタル化を進めるとやはり銀行の窓口に来店するお客様は減少するということだと思っていますし、お客様が銀行に期待するサービスというのが変化します。スマートフォン等のデジタルデバイスを通じての顧客接点がその代表でございまして、ご来店いただかなくても銀行のサービスができるように、各行が試行しながら新たなサービスの開発に取り組んでいると思っています。
また一部の地方銀行においては新たな顧客接点の提供による顧客基盤の拡大を目指して、デジタルバンクのビジネス展開もできているというのはご承知の通りだと思っております。ただ繰り返しになりますけど、そういった状況の中でお客様との接点のポイント、こういった関係性は大きく変化してきていますが、銀行の店舗の役割がなくなったということではないと思います。例えば、資産運用とか資産形成の事例というふうになりますが、やはり将来に漠然と不安があるけれども何から始めていいかわからない、なかなかアクションを起こせない、というお客様も実際おられると思います。この場合はやはり資産形成運用に関するお客様の人生設計をお伺いして、その実現への適切な支援について一緒に考えさせていただくというのは、店舗にご来店いただいてフェ-ス・ツー・フェ-スで様々なご相談にお答えすることが、やはりお客様の満足度を高めることではないかと思っています。
また同様に、住宅ローンの借り入れの検討もそうだと思います。やはりお客様にご来店いただきまして、現状をお伺いしながらライフプランに合わせた返済プランとか、あるいはその病気とか怪我に備えた保険の付保、様々な条件を加味した上でお客様に最適な提案を行うのは、やはりデジタルよりも来店してお話する方がお客様にとってはフィットするのではないかと思います。お客様に対面と非対面、あるいは来店とスマホ、こういう選択肢をお渡しさせていただくっていうことが大事ではないかなと思っておりまして、そのニーズに合わせたコンサルティングサービスを提供する。両方の特徴を生かしたサービスを提供しながら新しい金融体験の場を提供していきたいと思っております。1点目は以上です。
2点目です。ファイアーウォールの規制緩和についてご説明をお話させていただきたいと思います。ファイアーウォールにつきましては1993年に金融制度改革法に伴う導入以降、大きな緩和がなかったのですが、2020年10月以降の金融審議会「市場制度ワーキンググループ」の議論に基づきまして2021年6月にはファイアーウォール規制の適用対象から外国法人顧客を除外すること、2022年6月には新オプトアウト制度の創設、オプトインの簡素化、ホームベースルールの撤廃などが設置されております。これにより現状、上場企業グループの一部のお客様には銀証連携した提案ができるようになり利便性が高まる可能性が出てきております。ただ、ファイアーウォール規制の残課題としては依然としてありまして、それが我が国の資本市場の活性化や貯蓄から投資への好循環に向けた銀証間の円滑な連携の妨げにはなっております。例えば、外務員の二重登録禁止規制であるとか、上場企業グループ以外の非上場大企業、中堅・中小企業、個人の情報授受規制の見直しというのは私は不可欠であるという考えは変わっておりません。いずれにしましてもお客様の利便性、便益の観点から緩和を進めていくべきものというふうに思っております。例えば、お客様に対して銀行、証券の両方の商品を提案することがあるが、そういった事例の場合、お客様に1人の営業担当者が責任を持って各種の提案を行って欲しいというニーズがあります。
ただ、今は外務員二重登録禁止規制があるということで、外務員登録を銀行側で行った担当者は、銀行の商品、証券側で登録を行った担当者は、証券の商品しか提案できずにお客様がやはり煩わしいということを感じてしまうことがあるということでございます。また現場の声として、もっとシンプルな言い方をすると情報共有の同意が入り口にあることによって、お客様の投資検討のきっかけや機会が奪われているということも聞いております。具体的には例えば投資に踏み出せない理由として、知識がないとか損をするのが不安であるとか、手続きが面倒、時間がないと、様々な心理的なハードルがある。その中で様々なご提案の前に、まず情報共有の同意をというふうな話をするとですね、そこで止まってしまうケースは結構多い。例えば昼休みに銀行の窓口に来られたときに、「時間があるから証券会社の話聞いてもいいよ」と言ってくださるお客様に、今の制度だと「ご印鑑を持ちですか」とか「まずは同意書がないと」と。このようなところが今の現場の実態であります。
結果として、ここで離脱されているお客様が多いのが現場であります。今後、我が国が重要な社会課題である、事業承継とか、相続などのサービスにおいて同様なことが起こっておりまして、やはりお客様のご負担をかけずに銀行や証券がスムーズに情報共有をすることで、利便性、付加価値の高いサポートが可能になると考えております。銀行界として、顧客満足度の向上を通じた貯蓄から投資への好循環や資本市場の発展につなげていきたいというふうに思っております。
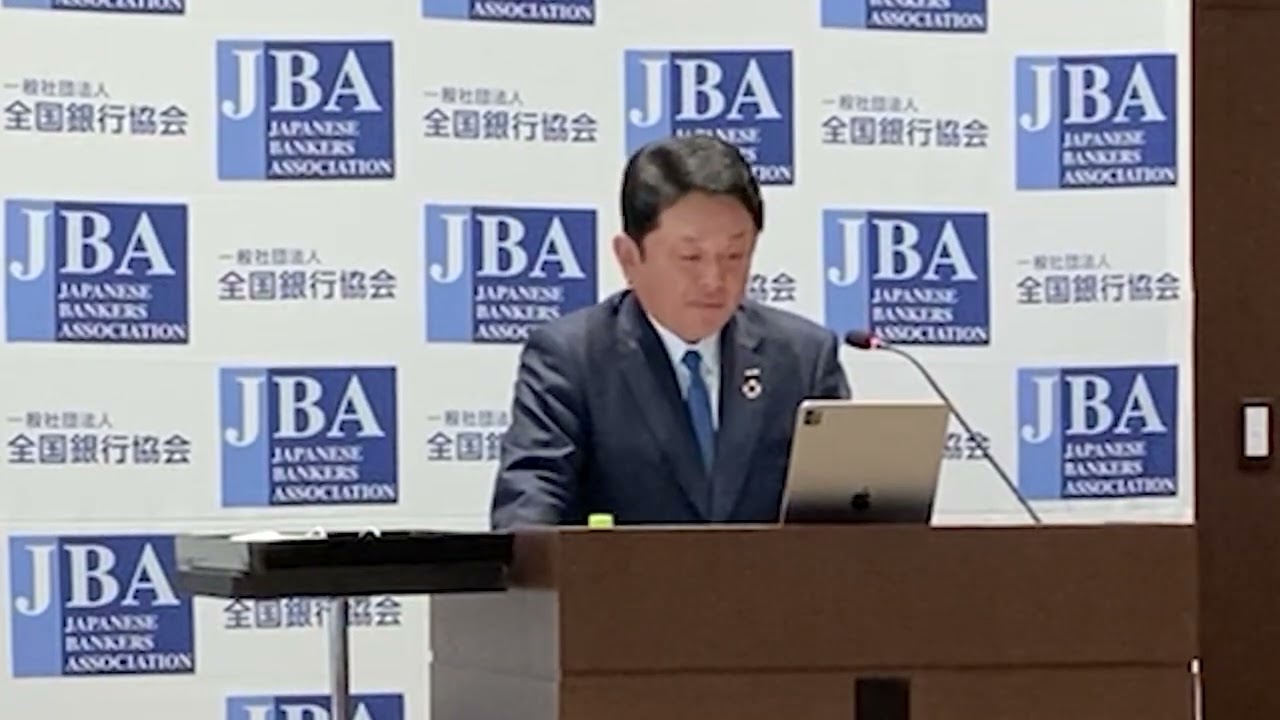
2023/4/3 全銀協会長会見 地銀の今後の経営環境と金融システムに対する不安について
この動画はプレミアム会員限定です。登録すると動画をご覧いただけます。
2023.04.04 18:42
Q.世界的な金融システム不安に関連して、今回の米銀行の破たんを踏まえた地銀の今後の経営環境についてどう考えているか。また、米銀行の経営破綻やクレディスイスの救済合併など信用不安が相次いでいるが、金融システムに対する市場の不安心理についてどう考えているか。
一つ目は米銀の破綻を受けた日本の地銀の経営環境の変化と認識した上で、今後詳細が判明すると思いますが、現時点で報道ベースの情報ということでございますので個人の見解になると思います。先ほども申し上げたように、シリコンバレーバンクの破綻の原因というのは、ALM管理の甘さにあったと思っております。スタートアップ企業関連中心のお客様であったりとか、預金構造が粘着性の低い法人預金である、あるいは米国債、ABSのようなポートフォリオ運営だったと。こんなところが顧客預金の流出になり、評価損を抱え有価証券の売却に迫られ、信用不安、取り付け騒ぎが起こり破綻に至ったと。このようなことでございますので、繰り返しになりますけどやはりこれは、銀行の資産サイド、負債サイド共に分散が効いておらず、流動性リスクの管理、あるいは金利リスクの管理などのALMの管理が不十分であったということですので個別行特有の問題でございます。
一方で見方を変えると、余資運用先として米国債等を保有したものの、中央銀行による利上げにより有価証券の評価損を抱えていると。こういう観点で言うと、先ほどのご質問の主旨のですね、邦銀においても似通ったケースがあると思います。ただ、米国と異なるのは、邦銀においては日銀による長期の量的・質的緩和によって潤沢な資金を保有しているということもある、あるいは企業や個人などに預金が分散されており、預金の粘着性が高いものだと思っていますので、預金流出等による資金不足を理由に有価証券の売却が起こる可能性は低いと考えております。
ただ、米国で今回のような地銀破綻が予見できなかったように、やはりその先行きを見通すのは大変厳しいと。そういう意味で言うと、大事なことというのは各行がビジネス戦略、リスクの許容度を踏まえて適切なALM管理をしっかり行うということが大事だと思っております。また、長きにわたる低金利の環境下で銀行の伝統的な収益源である、いわゆるその資金利益が圧迫されて、銀行にとって厳しいビジネス環境が続いていますが、やはり大事なことは変化するお客様ニーズにしっかり対応すること。各行がエクイティ投資であるとかシステム販売、広告人材派遣など伝統的なビジネスにとらわれないような新しいビジネスを進めていくことが大事ではないかなと思っております。各行が各地域が持つ資源や強みを生かしながら収益源の多様化を図ることも大事だなというふうに思っております。
二つ目の質問は、リーマンショックのような金融危機に発展するかというご質問だと思っております。これも個人的な見解ということでご認識いただければと思います。繰り返しになりますがシステム不安ということが起きましたけれども、実際には各国金融当局による潤沢な資金供給であるとか、米国での預金全額保護、あるいはスイスの買収支援ということで各国の迅速な措置が行われております。そういう意味では金融環境の悪化に歯止めがかかっておりますので、システミックリスクの顕在化の恐れというのは低下していると考えております。やはり市場の不安心理の払拭には、金融当局による迅速な柔軟な対応と各国の金融当局による緊密な連携が欠かせないということでありまして、今般の海外金融当局による一連の市場安定化策というのは、金融環境の一段の悪化に歯止めをかけて一定の成果を上げていると認識しております。
リーマンショックにおいては、大手金融機関がサブプライムローンの貸し倒れという共通のリスクを保有していたことに加えて、サブプライムローン債権を組み入れた複雑な金融商品が信用不安の連鎖を呼んだと認識しております。一方で、今回の一連の破綻や信用懸念というのは、個別行のALM管理の失敗であるとか、業績不振、不祥事など特有の要因に起因しており状況が異なっております。またリーマンショックを教訓に自己資本の拡充など、金融システムの頑強性も強化されておりまして、リーマンショックのような金融危機には陥らないというふうに私は見ております。ただ、繰り返しになりますが市場の先行きについては当面の間、予断を持たずに緊張感を持って注意していくべきだと思っています。各国金融当局の政策対応の積み重ねというのが、市場の不安心理の払拭に繋がると考えております。
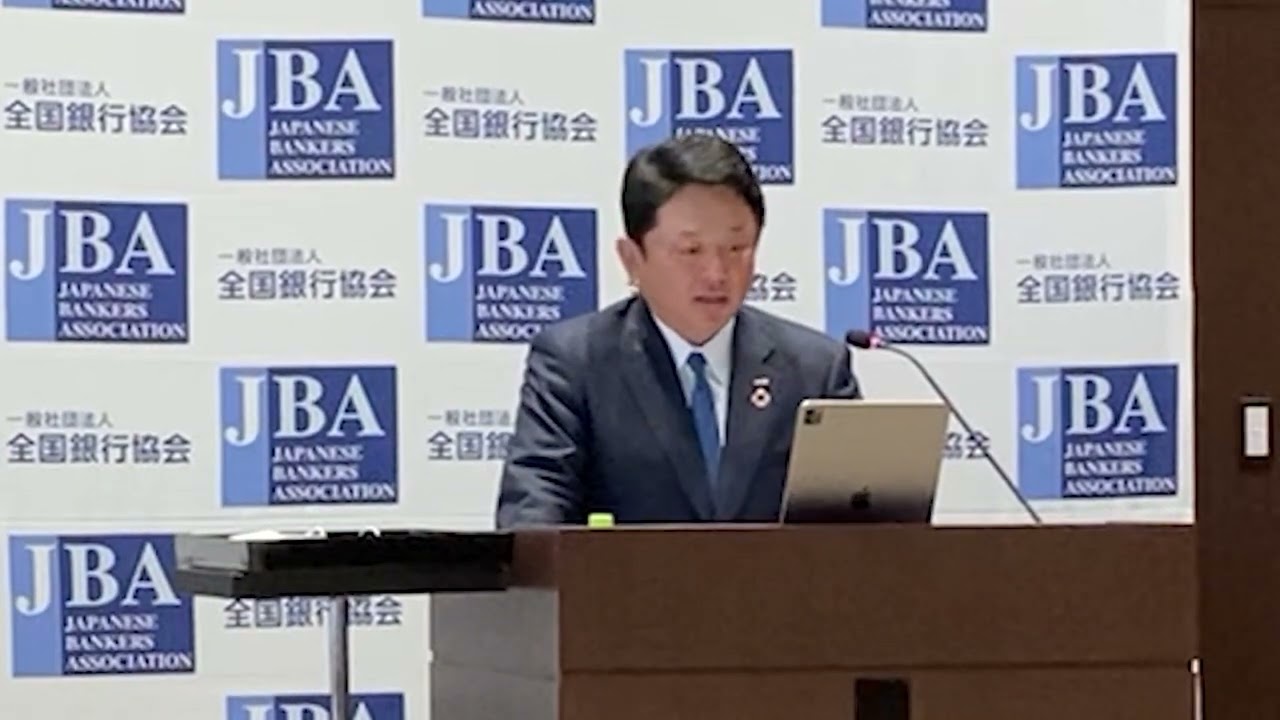
2023/4/3 全銀協会長会見 国内景気の現状と給与のデジタル払いについて
この動画はプレミアム会員限定です。登録すると動画をご覧いただけます。
2023.04.04 18:34
Q. 国内景気の現状や先行きについてのお考えは。また、4月から給与のデジタル払いが解禁された。銀行業界としての受け止めは。
一つ目の質問については、日銀短観が今日発表されておりますので、速報ベースで恐縮でございますが経営環境につきましては製造業中心に悪化をしたものの、企業の設備投資計画には底堅さというのが見られるなど、私は今年度の日本経済に明るい材料があったと評価をしています。
具体的には、大企業製造業の業況判断DIはプラス1%ポイントということで、前回の12月調査から6ポイント悪化をしたということです。これは海外の投資需要が利上げの影響などで減退していることや、半導体市場が調整局面に入っていることなどが製造業にとっては向かい風になっていると理解をしております。一方で大企業非製造業の業況判断DIはプラス20%ポイントということで、12月の調査から1ポイント改善しております。燃料費や人件費など各種コストの上昇が業績改善の妨げになっている面というのは依然としてありますが、やはりインバウンドの旅行客の回復であるとか、新型コロナの感染対策、緩和に伴うサービス消費の持ち直しを背景に、依然としてDIの水準が高いと思っています。
従いまして2022年度の設備投資の見込みというのは、前年対比プラスの11.4%ということで12月時点の評価からは下方に修正されておりますが、依然として非常に高い伸びで着地をする見込みであります。コロナ禍で先送りされた投資が再開され、正常化されつつあり、下方修正については、供給制約などの影響で年度内に実行しきれなかった面が強く、あまり心配する必要はないのではないかと思っています。実際に今回の調査で新たに公表された2023年度の設備投資計画は前年比プラス3.9%、昨年度はプラス0.8%でしたからそれを上回っておりまして、3月調査としては非常に高い伸びになっております。グリーンデジタル関連の投資、人材不足に対応するための省力化投資など、企業が将来の課題に向けた投資を活発化し始めている可能性があると、こういうふうに読んでおります。最近の金融不安を見ても分かります通り、2023年の海外経済を巡る不確実性は高まっていますけれども、国内の設備投資が増勢を維持しそうなことというのは、今年度の日本経済にとって心強い材料の一つであるというふうに考えております。1点目は以上でございます。
2点目につきましてはデジタル給与払いがどういった影響があるかの受け止め方と認識しております。こちらにつきましてはデジタル技術、先ほどのメガトレンドでお話ししましたけども、その進展であるとか、価値観の多様性を踏まえて、労働者の利便性の向上であるとか、キャッシュレスの推進、これに取り組んでいくことというのは重要なことだと思っております。その意味でデジタル給与というのも、給与をデジタルマネーで受け取ることができるようにするということで、労働者の利便性向上の目的で解禁されたと理解をしています。これまでもこのような形の会見で申し上げましたように、給与は労働者の生活の糧であります。従いまして、安全かつ確実に支払わなければいけないものであります。給与振込を取り扱う我々銀行界では、長い年月をかけて銀行口座、あるいは決済に関わる安心・安全なサービスの供給に努めてまいりました。例えば、金融犯罪防止対応、サイバーセキュリティー、反社データベース、災害対応や各種規制に基づく財務の健全性確保等、お客様の資産を守るための取り組みを多面的に講じていると。こういうことで安心を提供することで多くの事業者、労働者にご利用いただいているものと承知しております。
今回の資金移動業者による給料払いの解禁というのも、利便性はもとより、給与の取り扱いに必要な安全・安心が確保されていることを前提に決定されたものと理解しており、今後はそうした観点でのモニタリングも必要だというふうに考えております。例えば、資金移動業者のアカウントが生活資金の受け皿として使われている場合、為替取引と直結しない資金が滞留する可能性が高い。取り扱いの運営実態というのを丁寧にモニタリングしていく必要があると考えております。今回の規制によって、実際にデジタルマネーでの給料払いや受け取りをお考えになる企業や労働者もいると思います。銀行口座での給与の受け取りは、銀行にとって個人のお客様のお取引の規定の一つでありまして、それが減少するということは、例えばその資産運用や住宅ローンのご提案機会が減ると。デジタル給料払いが進むということは、銀行ビジネスにも一定の影響が出る可能性があるというふうにも思っています。従いまして銀行界としても、いつでも現金化できるATMネットワーク、あるいは業態間で資金移動可能な振込ネットワーク等、利便性の確保にも努めてまいりますが、今後もスマホアプリを利用した個人間送金ネットワークの拡充と、さらなる利便性の追求を通じて預金口座の付加価値を高めて、お客様に引き続きお選びいただけるように不断の努力を続けていきたいと思っております。
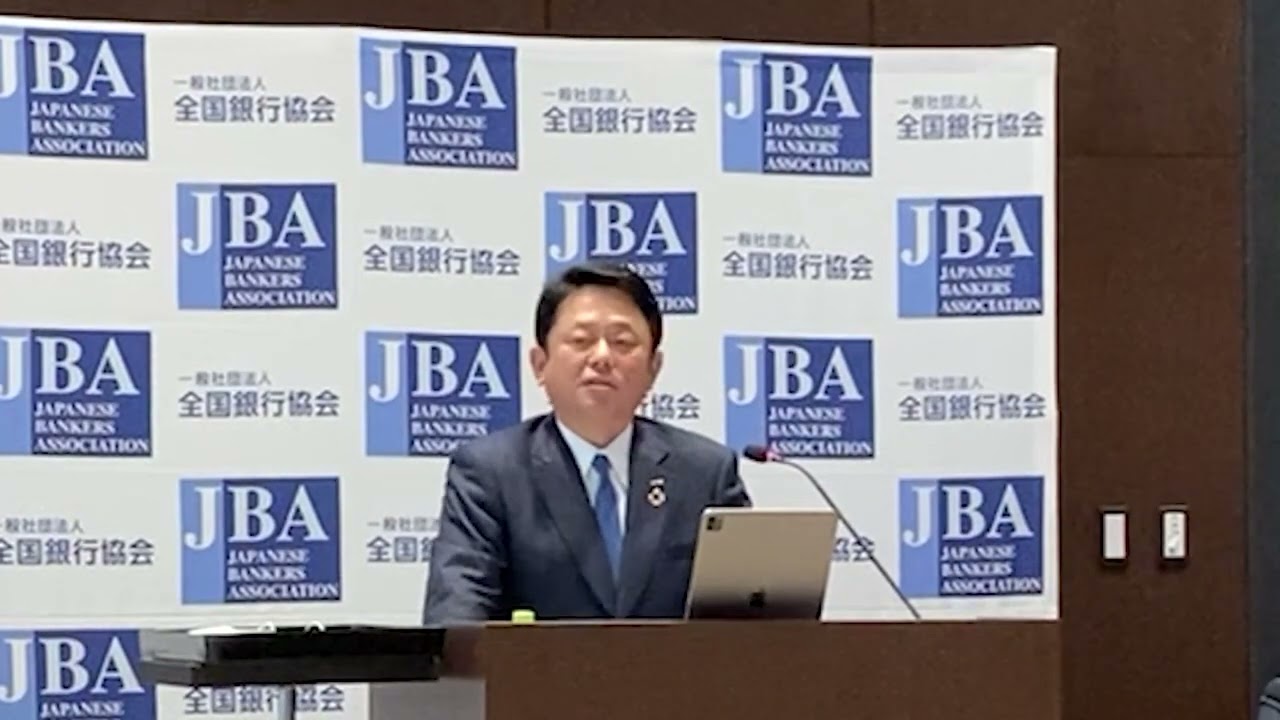
2023/4/3 全銀協会長会見 預金の粘着性について
この動画はプレミアム会員限定です。登録すると動画をご覧いただけます。
2023.04.04 18:31
Q.預金の粘着性について、ネット経由などデジタルが進むなかで、粘着性は低下していくのでは。
おっしゃるとおり、デジタル化が進み利便性が高まると言うことは、他行に預金を移しやすくなるということですので、預金の粘着性というのは従来よりも低下するというふうに思っております。
ただ、本件のご質問の背景は、繰り返しになりますけれども、破綻したシリコンバレーバンクの話だと思ってますので、これは先ほど申し上げましたように、ちょっと特異な固有の例だということもありますし、先ほどご説明の部分でなかった部分でいうとスタートアップ企業ということで、企業預金が中心ということと、やはり預金保護の対象の割合というのが極端に低かったっていうの一つあったのではないかなというふうに思ってます。
またもう一つですね、破綻のところがですね、粘着性が低いということに関わらず、いわゆる運用の方ですね、償還期限の満期が長くて、価格変動リスクが相応にある米国債であったりとか、MBSに過剰に投資してたという、いわゆる脆弱なALM管理というのもあったと。これは一つ大きく異なる部分かというふうに思っております。
翻って日本でございます。邦銀、ご案内の通り当座預金などの決済用預金は全額保護ということでアメリカとは制度が異なっております。また決済用預金以外の一般預金においても、1金融機関ごとに預金者1人当たりの元本1000万円まで保護されてるということでございますので、全体に占める預金保護対象の割合が高くて、信用懸念に伴う与信流出リスクに対する耐性が高いというのが基本的なファンダメンタルだと思っています。
ただやはりデジタルが進む中でそのビジネス環境の変化あるいはその預金者の行動様式の変化ということで、徐々に預金者の構造であるとか粘着性ってのは、今後も変遷していく可能性があるというふうに考えております。
こういった粘着性か下がるというリスクは、やはり各行においてしっかりと変化を留意をしながらっていうことが、まず一つあって、そのためにこそ厳格なALM管理っていうのを会員各行にはお願いしていきたいというふうに立場として考えております。



