採用・人財
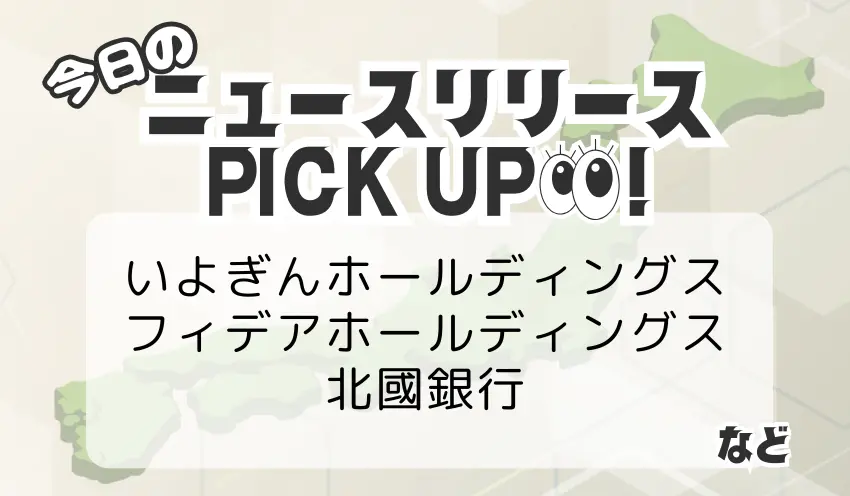
9月21日(月)ニュースリリース PICK UP !
金融業務
2025.09.22 17:00

組織・人材の支援
中小企業の海外展開をアシストする海外展開アドバイス支援
収益拡大
経営改善
2025.09.22 04:50
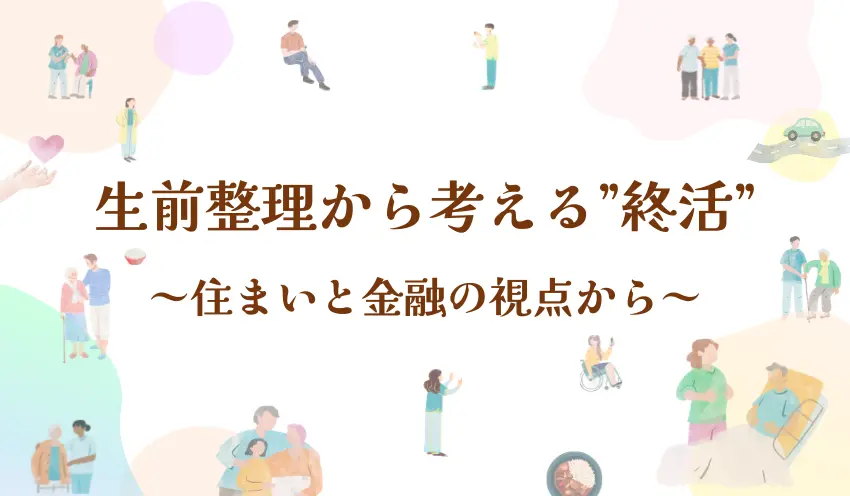
第1回 「空き家」を残さない終活術
経営効率化・業務改革
経営改善
SDGs
2025.09.21 04:50

金融業務
夢のような株式トークン化時代へ──金融インターネット化の行方
金融業務
FREE
2025.09.20 04:50

行政・政策
2025/9/19 日銀、金融政策決定会合後会見 全文速報
金融業務
行政・政策
2025.09.19 18:55
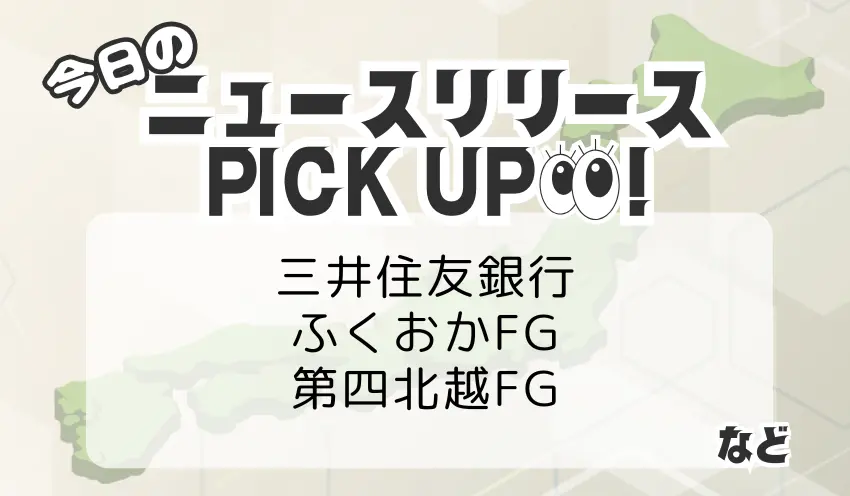
9月19日(金)ニュースリリース PICK UP !
金融業務
2025.09.19 17:10
採用・人財
採用・人財
採用・人財
採用・人財
採用・人財


-2.webp)





