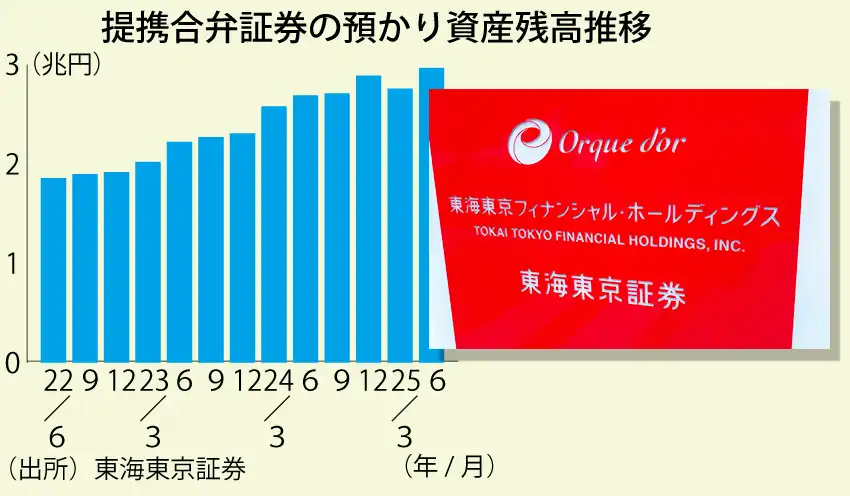マーケット・トレンド(為替) 購買力平価に基づく円高修正は機能不全に
2023.11.01 04:25
ドル円は10月に入って以降、年初来高値圏でもみ合うなか、ジリジリと値を上げ、150円台に乗せてきた(10/26執筆時点)。中東情勢の緊迫化も、かつての円であれば「リスク回避の円買い」につながったが、足元は全くといっても過言ではない程にそうした動きはみられない。
ドル円は1月安値の127円台から20円以上もドル高円安が進み、昨年高値の151円90銭台に迫る勢いにある。こうしたなか、ちまたでは購買力平価と実勢レートの乖離(かいり)を持ち出し、ドル円はいずれ円高に向かうとの理論展開を耳にする。
購買力平価とは為替レートは異なる通貨の購買力が等しくなるように決定されるとの考え方だ。例えば、米国では1ドルで買えるハンバーガーが日本では100円で買えるとするとき、1ドルと100円では同じものが“買えるはず”なので、為替レートは1ドル=100円が妥当となる。
だが、実際の為替レートは金利差や貿易・経常収支、潜在的な経済力、財政収支の違いなど、多様な要因の影響を受けて決定される。
特に近年では貿易・サービス収支の赤字常態化を背景とした円売り超過の需給環境が続いている。また、日米のインフレ率が拮抗(きっこう)する状況にもかかわらず、日本は世界で唯一マイナス金利政策を続けるなど、需給や金利のベクトルは円安方向を向いている。
長期的に実勢レートが購買力平価に収束することはあっても、足元では購買力平価の考え方は機能していないとみるべきであろう。
東海東京調査センター投資戦略部グローバルストラテジーグループ 金利・為替シニアストラテジスト 柴田 秀樹氏
関連記事
関連キーワード
おすすめ
アクセスランキング(過去1週間)
- 金融庁、粉飾対策で「第2線」注視 営業現場と連携求める
- 3メガ銀、リアル接点拡充 三菱UFJ銀、20年ぶり新店
- 地域金融機関、地公体貸出 割れる戦略 金利上昇で見直し加速
- ブラックロック・ジャパン、国内初の外株アクティブETF上場 AI銘柄に投資、早期100億円へ
- 信金、増える金融・保険業貸出 融資需要低下が影響か
- 三菱UFJ銀、Netflixの独占放映で 独自調査を公表
- 住信SBIネット銀、住宅ローンアプリ1年 本審査9割超に利用浸透
- <お知らせ>「金融×スタートアップ Meetup」 ~スタートアップ支援の課題と在り方を考えるイベント~【参加無料】
- 常陽銀、〝100億企業創出〟に本腰 包括支援へ157社選定
- 大手生保、生成AIがアンダーライティング代替 事務職を営業へシフト


 地域版はこちら
地域版はこちら