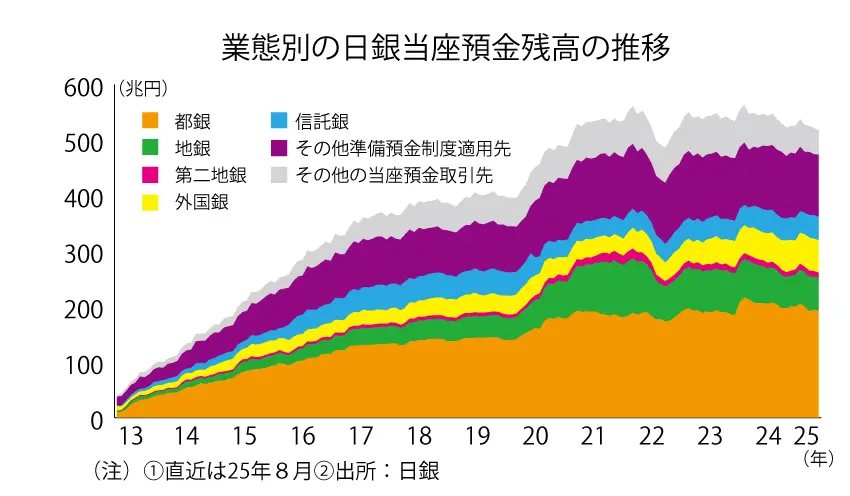VRで日銀・東証・印刷局に潜入!~オンラインツアー公開
2022.10.15 04:46
動画コンテンツやイベントをバーチャル空間で楽しむVR(仮想現実)が脚光を浴びている。仮想空間に入るためのハードウェア(ヘッドセット)の低価格・軽量化や、高速・大容量通信といったIT環境の向上で一段と身近な存在になったためだ。
金融界でも、CX(顧客体験)向上に向けた「ラウンジ」開設や、関連イベントへの出展、採用説明会・研修での活用、認知症体験など幅広い分野で導入を進めている。そんななか、日本の金融を支える重要施設を巡る「オンラインツアー」が人気を博す。
本店本館が重要文化財で見学ツアーに定評がある日本銀行は、2020年6月にバーチャルツアー「おうちで、にちぎん」をホームページにアップ。コロナ禍の初期に、学校の休校や〝ステイホーム〟が長引くなか、自宅に居ながら楽しんで学べるコンテンツとしてニーズを捉えた。「最先端技術を生かした中央銀行の取り組み」との評判が世界的に広がり、同時期に導入した英語版を含め国内外の関心を集める。
日本経済の心臓部である東京証券取引所(東証アローズ)も、21年11月からVRで一般公開。マーケット部門が売買を監理する重要業務を行い、通常の施設見学では立ち入ることのできない「マーケットセンター」を360°視野で体感できる。
紙幣やパスポートの製造を担う国立印刷局も、21年3月にVRコンテンツを公開。お札の製造工程や偽造防止技術、同局で作られる製品などが見られる「展示室」のほか、「お札がどのような機械で製造されているのか」といった、リアルの工場見学では触れることのできない視点を体験できる仕掛けを施した。
いずれも「無料公開」されており、手元にVRヘッドセットやVRゴーグルがあれば、好きなときに何度でも『東京・金融VRツアー』(以下にリンク)を楽しめる。この機会に是非、のぞいてみて下さい。
日銀情報サービス局・川村企画役に聞く
〝リアル〟と高い相乗効果
世界の中央銀行のなかで、先進的な広報活動に取り組む日本銀行。オンライン見学「おうちで、にちぎん」の企画・運営に携わる情報サービス局の川村憲章・企画役(55)に先端技術を活用した対外広報のメリットや反響を聞いた。(聞き手=多田 弘樹)
――オンライン見学の企画に至った経緯は。
「日銀本店本館を見学する〝リアル〟ツアーは学生から高齢の方まで幅広い世代に定評があり、2019年度には2万人近い方に参加していただいた。ただ、新型コロナウイルス感染拡大が深刻化した20年の春以降はツアーを休止・規模縮小せざるを得ず、修学旅行や校外学習で定例的に訪れていただいていた学校の先生から『ツアーに行くことができない。学びの場を何か提供していただけないか?』といった相談が寄せられた。見学ニーズの根強さを深く実感し、何かできることはないかと対応策を模索した」
――コンテンツ制作にはVR技術を活用した。
「感染対策の観点から、見学ツアーの代替の前提としてリモート対応を考えていた。一方でVRは以前から関心を持っており、研究もしていた。日本のVR技術は世界でも指折りで、ニーズが強いのであればすぐに動き出すべきと、最新のデジタル技術の強みを生かした見学コンテンツの企画・制作に踏み切った。ボランティア撮影を受け、3D・VR映像を制作し、動き出しから公開(20年6月30日)まで1カ月は掛からなかった」
――「おうちで、にちぎん」の魅力は。
「重要文化財である本館を〝いつでも、どこでも、独り占めして見られる〟ところ。3D構造図などから地下金庫や旧営業場など行きたい場所を指定すれば、自由に動き回れ、現金輸送車の模型や世界初の銀行券鑑査機も鑑賞できる点が好評で、30か国以上で報道された。公開後2年間のSNSリーチ数は1億5000万人。桁違いの人数に情報を届けることができ、デジタルコンテンツの情報発信力は極めて高い」
――国内外の学校向けにオンライン授業も展開している。
「ICT教育(情報通信技術を活用した教育)の環境が整う中、学校からの要望を踏まえ、デジタルコンテンツを使用したリモート見学ツアーを交えつつ、日銀やお金のことを体系的に学べるプログラムを21年5月に用意した。既に30回以上、北海道から沖縄、シンガポールなどアジアの学校に実施した。大人数や複数のクラスに対して一度で授業ができるほか、本支店共催やノウハウ共有を兼ねた傍聴も容易にできるなどオンラインのメリットは大きい」
――今後については。
「ポストコロナを展望しても、体験価値の高いリアルと情報発信力が高いデジタルを組み合わせた広報は効果的だ。リアルを見学した先生がオンライン授業を依頼してきたり、Twitterをみてリアル見学に来る人がいるなど、リアルとデジタルにはシナジー効果もある」
「学校からは『コロナが落ち着いた後も、オンライン授業やデジタルコンテンツの提供を続けて欲しい』との声を聞く。ICT教育や金融教育が進む中、通常のカリキュラムに組み入れ可能なオンラインのチャネルの重要性は一段と高まっていく。オンライン・コミュニケーションのノウハウは、広報以外の対外コミュニケーション全般で活用でき、そのノウハウ共有や人材育成が重要だ」
関連記事
関連キーワード
おすすめ
アクセスランキング(過去1週間)
- 地域金融機関、地公体貸出 割れる戦略 金利上昇で見直し加速
- 3メガ銀、リアル接点拡充 三菱UFJ銀、20年ぶり新店
- 三菱UFJ銀、Netflixの独占放映で 独自調査を公表
- 住信SBIネット銀、住宅ローンアプリ1年 本審査9割超に利用浸透
- <お知らせ>「金融×スタートアップ Meetup」 ~スタートアップ支援の課題と在り方を考えるイベント~【参加無料】
- 常陽銀、〝100億企業創出〟に本腰 包括支援へ157社選定
- 福島銀、貸金庫サービスを廃止 26年3月末で
- 改革の旗手 藤原一朗・名古屋銀行頭取、「健康経営」で日本変える
- 高知銀、投信販売体制を再構築 営業店はマス層のみに
- 埼玉県と県産業振興公社、業態超え新現役交流会 全国初、同一県の9機関協力


 地域版はこちら
地域版はこちら