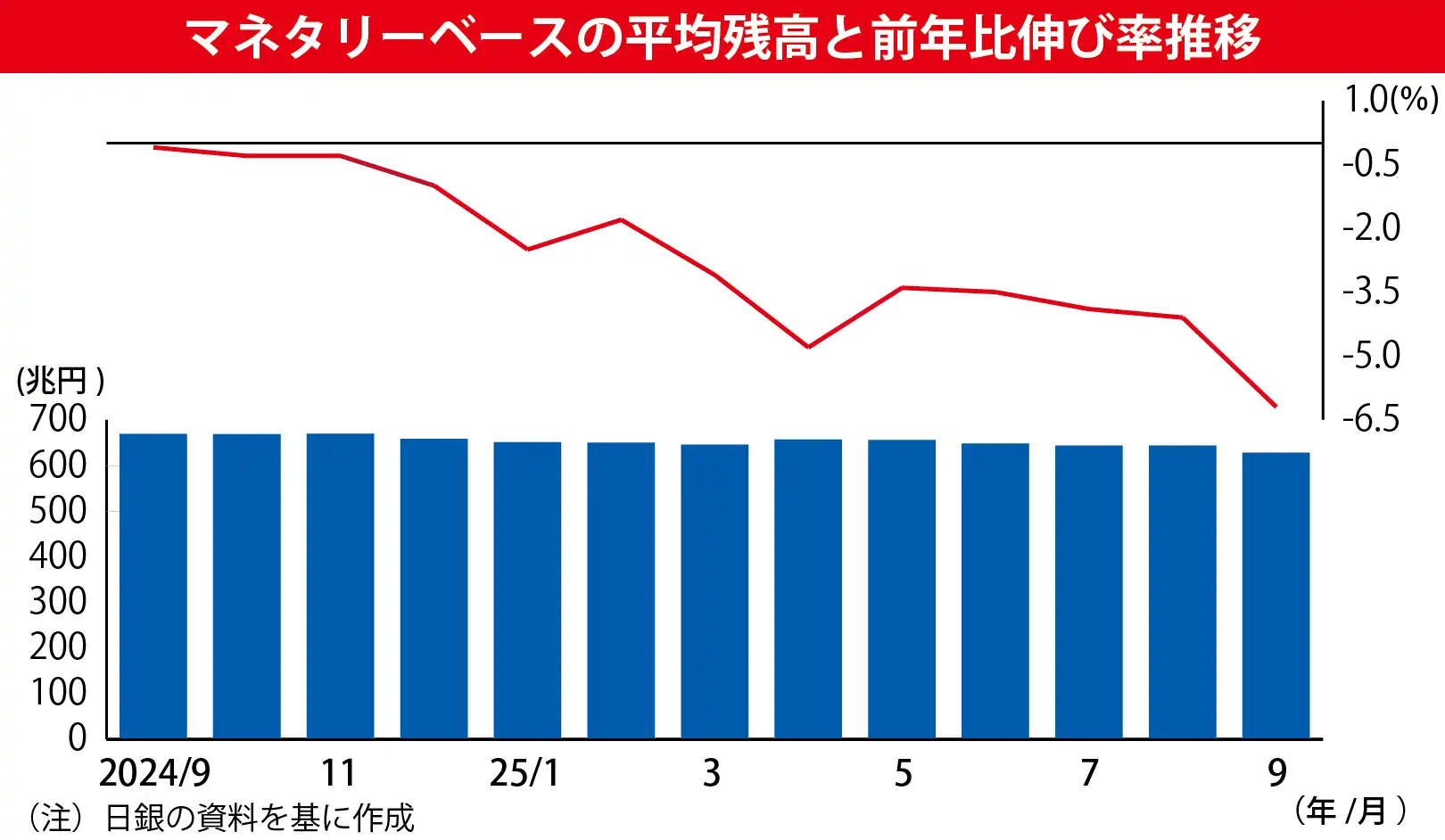【BOJウオッチャーに聞く⑧】植田日銀2年半、任期〝折り返し点〟の評価と課題
2025.10.06 11:36
【UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメントの青木大樹日本地域最高投資責任者兼チーフエコノミスト】
――総裁任期前半の政策運営をどう評価する
「マイナス金利解除やイールドカーブ・コントロール(長短金利操作、YCC)撤廃に加え、段階的な利上げにも踏み出し、『金利ある世界』を取り戻したことは評価できる。供給要因を中心にインフレ率が上昇するなか、賃金と物価が循環し始めた局面を見極めて政策を動かした点も妥当だった。半面、2024年7月末のサプライズ的な追加利上げで市場急変動を招く場面もあり、超低金利が常態化していた金融環境から移行する難しい舵取りだったことは確かだ」
――ETF処分も決め本格的な“出口”に向かう
「保有ETFは、100年以上かかるゆっくりとしたペースで売却することが示され、マーケットに大きな混乱は生じなかったものの、処分方法に関しては、金融政策の観点だけでなく、成長戦略を踏まえた活用策を採用してもよかったとみている。ETFは本来、産業政策に踏み込んだ異例の政策手段なため、その出口についても市場中立的に処理するのではなく、例えば売却機構を設け、将来の成長や社会保障に貢献する形で活用する発想もあり得たのではないか。金融政策の枠を超える部分ではあるが、〝100年計画〟という処理方法には疑問が残る」
――任期後半の課題やテーマは
「今後はアメリカの利下げ局面や日本の景気減速リスクをにらみつつ、段階的利上げの〝持続性〟が問われる局面に入る。日銀が想定する中立金利(の下限)は1~1.25%程度とされるが、実際の中立金利をどこに置くかによって政策余地は変わる。政策金利を上げ過ぎると住宅ローンや中小企業の負担、財政への影響が顕在化し、金融政策の柔軟性や独立性が制約されるだろう。そうした状況では、政府との緊密なコミュニケーションを維持することが重要。植田和男総裁は岸田文雄首相、石破茂首相と政権が交代するなか、距離感をうまく取り、自身の考えとのバランスを意識しながら政策を進めてきた。任期後半もその姿勢を保ち、異次元緩和の『出口』の行き着く先をどう国民に示すかが最大の課題になる」


 地域版はこちら
地域版はこちら