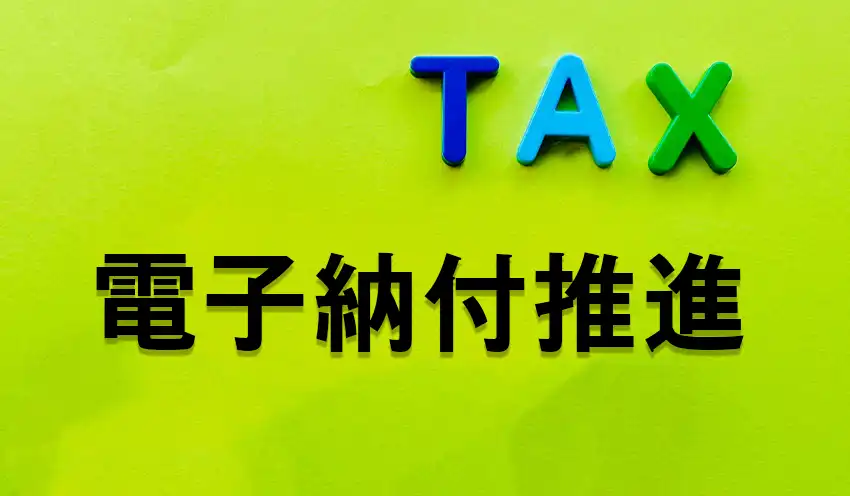柳沢祥二・全国信用組合中央協会会長 「取引先に寄り添いサポート」
2023.01.01 04:55
日本経済は、ウィズコロナの考え方のもと、社会経済活動の正常化が進みつつあり、サービス消費を中心に回復の動きが見えてきた。一方、中小・小規模事業者は、感染症拡大の長期化により積み重なった債務に加え、資源価格・物価の高騰や供給制約の影響により、未だ予断を許さない状況にある。
信用組合には今後も、お取引先との絆を活かしたコンサルティング機能を発揮しつつ、より一層の金融サービスの向上を図り、さらなる事業支援に努めることが求められる。全国信用組合中央協会・全国信用協同組合連合会においても、ビジネスマッチングやクラウドファンディングの活用による販路拡大支援や地域活性化ファンドによる地方創生支援、新現役交流会の継続的な開催による人材支援など、様々な面からお取引先に寄り添ったサポートを実践していく。
現下の厳しい状況におかれている中小・小規模事業者の打開に向け、お取引先へのさらなるコンサルティング機能を発揮するためにこれまで以上に専門的な知識が求められる。政府でも、創造性を発揮して付加価値を生み出していく原動力は「人」であり、「人への投資」は欠かせないとして各種政策が進められている。今後さらに多様化・高度化する業務に的確に対応していくには、信用組合も人材の育成を強化し、個々の能力・専門知識を高める必要がある。
当会では、その具体的な取り組みの一つとして、信用組合や中央組織の将来を的確に見据えた役員候補になりうる人材の育成を図ることを目的に、これまでのしんくみ大学を発展的に見直して「新・しんくみ大学」を発足した。今後5年先、10年先を見据え、信用組合自らが将来にわたり持続可能な経営を確立するためにも、こうした取り組みを一層強化し、人材力の強化や専門性の向上に努めていく。
新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけにデジタル化が急速に進展している。信用組合もこうした社会の流れとともに、お取引先のニーズを踏まえたうえで、キャッシュレス化の推進や非対面取引の拡大などデジタル技術を活用した利便性の高いサービスを提供することが重要になっている。
決済サービスのデジタル化については、昨年11月にスタートした電子交換所を過渡期対応として、令和8年度末の手形・小切手機能の全面的な電子化に向け、業界としても遅滞の無いようしっかり取り組んでいく。こうした取り組みを始めとし、デジタル技術の活用を進めることにより業務の合理化・効率化を図り、金融サービスの利便性を向上させることでお客さまの支援に力を注ぐことができる、いわゆるデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進につなげていくことが重要だ。
関連記事
関連キーワード
おすすめ
アクセスランキング(過去1週間)
- 西京銀、口座開設効果で給振1000件 サービス拡充、流出防ぐ
- 七十七銀宇都宮法人営業所、東北へのつなぎ役に徹する 開設2年で融資170億円
- 三菱UFJ信託銀、低コストPEファンド 1~4号累計で900億円
- 金融庁、信金・信組の顧客属性調査 年齢と預金額把握へ
- 金融庁、サステナ情報開示義務化 SSBJ基準適用
- 都銀、貸出金利引き上げ先行 地銀上回る月も
- 新潟県信組と興栄信組が合併、2026年11月に 基盤拡充と効率化
- 肥後銀、「オペレジ」確保を高度化 勘定系バックアップ平日稼働
- ひろぎんHD、女性登用へ階層別研修 役員面談で意識改革
- 【ニッキン70周年企画(1)】三井住友FG、「オリーブ」開発のキーマンにインタビュー


 地域版はこちら
地域版はこちら