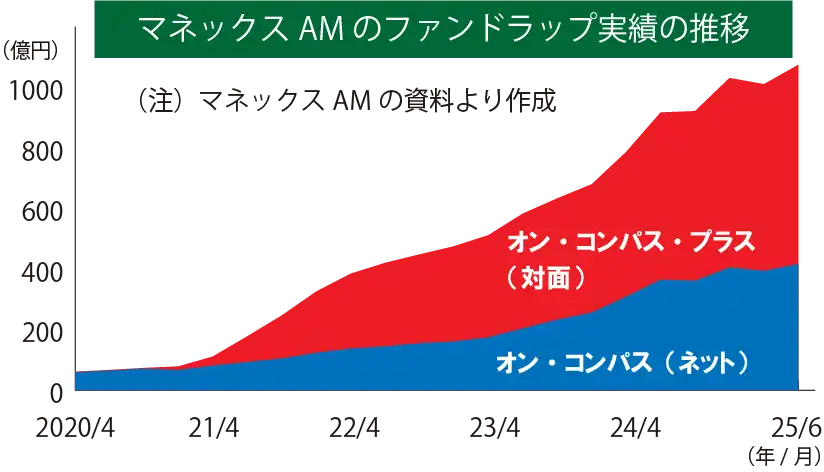【ニッキン70周年企画(9)】マネックスグループ・松本会長インタビュー 米国水準の枠組み整備を
2025.08.15 04:40
読者に支えられて70年 ニッキンは金融の未来を応援します!
日本金融通信社(ニッキン)は2025年8月27日、設立から70年を迎えます。本紙第1号が発行された1955年は、戦後復興を遂げた日本が高度経済成長期に突入する転換の年でした。あれから70年。急速な人口減少、慢性的な人手不足、デジタル化の進展など、日本は再び転換点を迎えています。新たな環境に適応するには、リスクを伴う挑戦が不可欠。「ニッキン70周年企画」の連載記事では、次の時代への「橋渡し役」として存在感を高める金融機関の姿を追いながら、10年後の金融界を展望します。連載第9回の今回は、マネックスグループの松本大会長に、デジタル通貨を取り巻く国際環境についてインタビューしました。
マネックスグループ・松本会長に聞く
近年、暗号資産やステーブルコインが存在感を高めてきた。米国がトランプ大統領の下で法整備を進めるなか、日本の金融界はどんな未来像を描くべきなのか。伝統的金融と新しいデジタル金融の両方に精通する、マネックスグループの松本大会長に、日本の金融界の課題や可能性について聞いた。
国際比較で法規制に遅れ
――マネックスグループ傘下に、カナダの暗号資産運用会社がある。その実績は。
「3iQは、暗号資産の運用分野では世界で一番実績と経験のある会社の一つだ。例えば、ビットコインのETF(上場投資信託)はカナダで最初に作られたが、同社がすぐに約70%のシェアになった。ファミリーオフィスやソブリンウェルスファンドなどの機関投資家に対しても、暗号資産運用のお手伝いをしている」
――日本と欧米で暗号資産の状況にどのような違いがあるのか。
「日本は、資金決済法の成立など法規制が早かった。一方で米国などは、まだ法規制が確立しない中でイノベーションを起こしてきた。最近はトランプ大統領の下で米国が法規制を始め、法律により暗号資産を認める方向に動き始めた。以前からのイノベーションに、法規制による信頼性も加わることになる」
「日本は法規制が早かったのは良かったが、その枠組みに固執してしまい、世の中の変化についていけなかった。税金の問題もある。暗号資産を売買して利益が出た場合、海外は大体が分離課税で金融商品と同じような扱いだが、日本は雑所得として総合課税になり、使いづらい。日本は暗号資産で先行したはずなのに、今は米国など海外に遅れをとっている」
――日本が遅れた原因は。
「暗号資産を管轄する金融庁は、産業育成ができなかった。本来は(同庁の)総合政策局が産業育成をして、監督局が監督をするのだが、(両局は)同じ(金融庁という)組織内にあって人事交流もしており、どうしても監督行政という意識が強くなってしまう。もし経済産業省だったら違ったかもしれない。金融ビジネスや暗号資産の産業育成というミッションは経産省に移し、金融庁は監督に徹する方が良いのではないか。官僚の方々は皆、優秀で真面目なので、自分の仕事をしっかりやろうとすれば管理する方向に行くのは当然だ。日本の成長を考えると、産業育成は全て経産省にまとめた方が官僚人材の有効活用ができる」
米国のステーブルコイン法は影響大
――今後、日本でも暗号資産の存在は海外のように高まるか。
「米国との違いがあまりにも大きく、このままでは空洞化するだろう。暗号資産やトークンの世界は本来ボーダーレスであり、日本だけが違うルールであれば皆、海外に行ってしまう。AI(人工知能)の進化により、日本の個人客が、ChatGPTに投資判断を仰ぎ、AI(人工知能)が人間に代わって口座開設から株の売買まで全て行うというような時代が迫っている。AIによって言語の壁もなくなる。そうなれば、事業者が日本にあるか海外にあるかは関係なくなる。日本人のお金が外国の事業者に流れないためにも、早く米国と同じ土俵を整えなければならない」
――マネックスグループ傘下のコインチェックのビジネスは足元で順調か。
「国内制度の遅れもあって、米国でコインチェックグループという持ち株会社を上場し、暗号資産ビジネスを世界で展開できるフォーメーションを組んだ。コインチェックは、規制が厳しい日本の環境でサバイブしてきた取引所であり、その力を活用して世界で活動していくというのが今の戦略だ」
――米国でステーブルコインの関連法案が可決された。どう受け止めたか。
「今回の法案では利息をつけることがスコープに入ってないが、今後変わっていく可能性もある。そうなれば、今まで銀行やクレジットカード会社が担っていた領域で、単に技術が変わるだけでなく、サービスを提供する主体も変わる可能性がある」
世界標準の枠組みに対応を
――金融機関への影響は。
「従来、物を買ったら銀行振り込みかカード決済をしていたが、これからはアマゾンのようなプラットフォームが独自のステーブルコインを発行し、出品者はステーブルコインを受け取り、また何か買うときにそのステーブルコインで支払うということが起こり得る。そうなれば、銀行もクレジットカード会社もいらなくなり、アマゾン経済圏の中で全部決済が終わってしまう。預金と決済の両方の行為が特定の経済圏の中で完結してしまう可能性がある。これは米国だけでなく世界中に波及する大きなインパクトがあり得る」
――日本の金融機関はどう対応すべきか。
「今までと同じことをやっていたら、どんどん縮小していく可能性があり、新しい法案や枠組みにどんどん対応して、変わっていかなければならない。それなのに、米国だけ枠組みが変わるのが早くて、日本の枠組み変更が2年後だったら、日本の金融機関の対応も遅れてしまう。2年後に枠組みが変わって頑張ろうとしても、米国はすでに2年の経験とノウハウを積んでいて、良いサービスを提供できるようになっている。すでにいろいろなサービスの改良が終えた企業が、日本に進出してくるだけだ。例えれば、米国が4ベースの野球をやっているのに対して、日本が3ベースでやっているようなもので、日本の選手は戦えなくなる。早く枠組みを一致させないと、日本の産業が弱体化してしまう。役所がやらないなら、民間が米国など進んだ国の枠組みに自ら対応していくしかない」
――マネックスグループの取り組みは。
「創業時から世界標準を意識してきた。創業2年目から社外取締役が過半数を占め、委員会設置会社ができたときにすぐに移行し、IFRS(国際財務報告基準)への会計基準変更も早期に採用した。世界標準にしたからといって世界的プレーヤーになれるわけではないが、世界標準にしておかなければ戦えない」
「ニッキン70周年企画」の連載第10回は8月16日に配信します。


 地域版はこちら
地域版はこちら