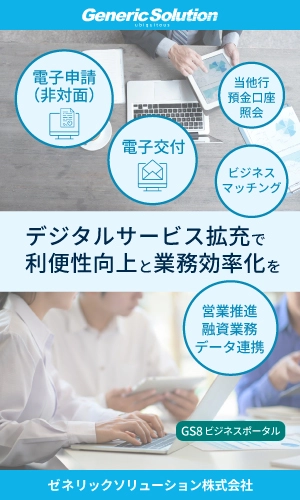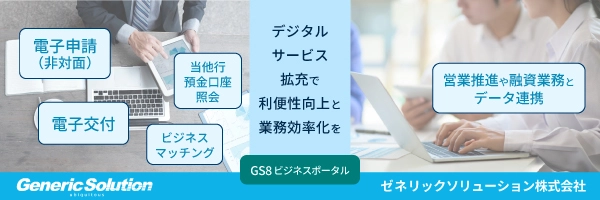【眼光紙背】 「独身税」取り巻く不安
2025.07.03 04:30
団塊ジュニアのやや上に属す筆者の年少時、街は子供の活気にあふれていた。ベッドタウンの小学校は40人学級で10クラス以上も珍しくなかった。もうそんな光景にはお目にかかれそうもない。
先日発表された2024年の日本人の出生数は68万6061人。統計開始以来初めて70万人を割った。80万人を割ってからもわずか2年。国立社会保障・人口問題研究所の推計より15年ほど早く少子化が進んだ計算だ。
国も対策に乗り出しているが、気がかりな新制度がある。26年4月に導入される「子ども・子育て支援金」。正式名より、ネット上で揶揄(やゆ)される「独身税」の呼び名の方が通りがいいかもしれない。
趣旨は全経済主体で子育て世帯を支えるもので、財源は総額1兆円。医療保険に上乗せして徴収し、一人当たり月250~450円程度にとどまるものの、子供のいない独身者は直接恩恵を受けられない点が物議を醸している。SNSでは「結婚も育児もできないのに不公平」といった嘆き節も聞かれる。
国によれば、支援金は課税ではなく社会保険料の位置付けで、医療保険とは別枠で管理される。制度を創設した岸田政権は「歳出改革で実質的な負担を生じさせない」とまで強調した。この支援金以外にも、妊婦支援など総合的な少子化対策を講じるとしている。
ただ、額面通り受け取られないのは、誤解されやすい制度なのに、そうした説明の行き届かなさに加え、現役世代を取り巻く環境も大きいと感じる。
少子化と背中合わせの高齢化において、現役世代は年金や社会保険で高齢者の負担をも背負う。現役世代に限らないが昨今の物価高で家計の圧迫感と痛税感も増している。そこに「独身税」という言葉が独り歩きし、独身者や子供のいない世帯は追い詰められた感覚を抱くのではないか。
より直接的な「独身税」を導入した事例は海外にみられる。ブルガリアでは1968年から約20年間未婚者に対して課税があった。しかし、未婚者の負担と経済的な不安を招き、効果が上がるどころか逆に出生率は低下。結局撤廃された。
このまま制度開始が近づき、さらに混乱が広がることが心配だ。政府は十分説明を尽くしてほしい。
(編集委員 柿内公輔)
◇


 地域版はこちら
地域版はこちら