
2024年8月に、信用金庫を対象とした次期リーダー候補をサポートする「わたしと組織のマインド改革プロジェクト」を始動。全国の信用金庫から選ばれた女性職員7人が、男女の職務分担へのバイアスや仕事と子育ての両立など女性活躍推進に関する現状の課題を洗い出し、解決に向けてそれぞれが動き出した。11月にはそれぞれの信用金庫で抱える課題とその解決策をまとめ理事長に提言した。
[関連記事] わたしと組織のマインド改革プロジェクト 信金の女性活躍に7人の旗手
プレミアム記事では、7信金の次期リーダーがそれぞれの理事長に提案した内容を紹介している。今回は、島根中央信用金庫人事部の淀谷友加副部長を取り上げる。信金の強みであるface to faceをさらに生かす店舗戦略や子育てしながら働きやすい職場づくりなど3つの施策を提案した。
提言内容の一部始終は、プレミアム動画に掲載。
男性と同じ働き方では女性活躍を実現できない
「理事長、今日はお時間をいただきまして、ありがとうございます」と言葉を発しながらも日頃から福間均理事長との良好な関係が垣間見える始まりだった。「そもそも女性活躍がどのような背景でスタートしたのか改めて調べてみました」と本題に入る。
「当初は、女性が男性と同じように働くということだと思っていました」とし改めて自身の考えを正すとともに、労働力不足や男女の賃金格差など各種統計を用いて、国が取り組む女性活躍推進の背景を説明した。そのうえで「女性が働きやすい職場を作ることが課題の1つとして見えてきました」と福間理事長の反応を伺った。続いて、育児をしている女性の有業率など島根県の女性の活躍状況を説明。「島根の女性は働きながら育児などがしやすい環境におかれている」としながら島根中央信金での3つの課題を挙げた。
まず、女性の活躍推進の目的が明確に伝わっていないと指摘。「女性を管理職に登用することはよく耳にするが、男性と同じ役割なのか、女性としての役割があるのか不明確」と。加えて、女性を育成する風土がない、理想のロールモデルがいないことを訴えた。自分自身を振り返り、「男性と同じように働く女性管理職の姿をみて、“残業が多い”、“緊急時の対応を迫られる”などのマイナスイメージがあり、育児をしながらキャリアアップにネガティブになりがち」と説明した。「男性と同じ働き方を求めてきたため女性活躍が実際にはあまり進んでいない」とまとめた。
女性の強みを活かす環境整備を
現状の課題が生まれた背景には、「女性活躍を進めるうえで、男性と同じ働き方をするものという無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)があり、それを修正する必要がある」と語った。「そもそも男性と女性は体や心の違いがあり、同じ働き方ではなく、双方が理解しあったうえで女性が気持ちよく働く場を作ってあげることが最優先」とした。女性の特性を活かした働き方の実現には、「“とりあえずやってみる力”や“みんなでやる力”など女性には7つの強みがある。女性1人ひとりが自分の強みを活かし、あらゆる分野で活躍できる環境整備が必要」と訴えた。
女性の強みを活かす3つの戦略
課題と女性の強みを整理したうえで同信金としての「女性の強みを活かす戦略」を提案した。1つめは、AX(アナログトランスフォーメーション)店舗の実施。カウンターを廃止しデジタルとアナログをバランスよく取り入れる。「お客さまの入口と出口は必ず人で終わらないといけない。それが信金だと思う」としたうえで「職員の人数が減っていくなかでお客さまとの接点を減らすことはできない。システムでできる部分は効率化をすすめ、カウンターを廃止し、お客さまとしっかりと会話し情報を得る。このような思い切ったことも必要」と考えを明かした。
2つめは、子育てをしながら働き続けやすい職場づくりの促進・支援。「最近、在宅勤務の話をよく耳にするが、信金での在宅勤務はイメージしにくい」ことから「わいわいスクールの開校」を提案した。小1の壁などにも対応し、職場で一緒にいながら仕事ができるのが特徴。3つめは、「女性活躍プロジェクトチームの発足」。結婚や育児などさまざまなライフステージにいる職員の声を集め、働き続けられる理想の職場環境の整備に取り組む。
「3つを実施することにより、業務の改善や企業文化の改革が進み優秀な女性の採用や信金のイメージアップにつながる効果が見込めます。最終的には女性活躍だけではなく全職員活躍につながっていけば」と締め括り「理事長、いかがでしょうか」と福間理事長に意見を求めた。
◆提案後のインタビュー骨子
――提案を受けた率直な感想を教えてください。
福間理事長:環境が変化しているなかで、男女ともに働きやすい環境にするためにやらなければならない施策は、しっかりと見定めてやっていく必要があります。信用金庫の収益力に応じた改善を進めていかなければいけないなかで優先順位をどうするかです。女性活躍限定で言えば提案の内容になるのかもしれませんが、人事政策全体では、ようやく65歳定年制を導入し実質3年目に入り、70歳までの再雇用制度への取り組みを進めてきています。次のステップでは、やはり全体としての賃金の底上げを図っていく必要があります。当金庫の場合、男女の賃金格差はないので、昇格するモチベーションや仕組みに問題があるのであれば、職員のリテラシーをもう少し上げて行って障壁を取り除く必要があると思います。提案内容はよいが、女性だけに限らず男性についても同様に取り組んでいく必要があると思います。
――ご自身の子育て時はどのような状況でしたか
淀谷さん:島根県は、近くに両親がいるなど、お手伝いをしてくれて一緒に育ててくれる人が身近にいる割合が他の県に比較し高いと思います。保育園とかも充実してます。待機児童はゼロの状況です。自身の子育ての折も、預けるところがあり、あまり困ることはありませんでした。しかし、最近の若い職員は近くにサポートしてくれる人がいないとか、仮にいたとしてもまだ現役で仕事をしてるため預けられないということをよく聞きます。以前とは、大きく環境が変わっています。
――女性活躍推進に対しての問題や課題は
福間理事長:現状、島根県は女性の育休取得の水準が比較的高く、共働き等であれば、昇格したいという気持ちになかなかなりにくいようです。女性と男性の採用人数はそれほど変わらないので、管理職への女性登用のウエイトも半分くらいになってほしいと思いますが、管理職としての責任は負いたくないという人もいます。子育ての最中に管理職としての仕事も、となるとなかなか難しいと思うので、子育てが終わったときに管理職というポジションに就きたいという気持ちになってもらえるかどうかです。これは男性職員も一緒で、昔のように女性の上司の下で働きたくないという世代はまずいません。おそらく家庭内のパワーバランスが昔と大きく変わり、共同して子育てをする環境になっているからだと思います。だから男性も子育ての時間が取れなくなるからそれほど昇格しなくていいという人が増えています。組織を運用する側としては、昇格できる環境はあるものの、それを希望しないというマインドがあることにジレンマを感じます。
――今回の提案を受け採用を検討する内容はありましたか
福間理事長:やはり多様な勤務体系は必然的にやらざるを得ないと思っています。継続的な雇用をお願いする側からすると、ニーズに合った雇用形態を作っていく必要があります。





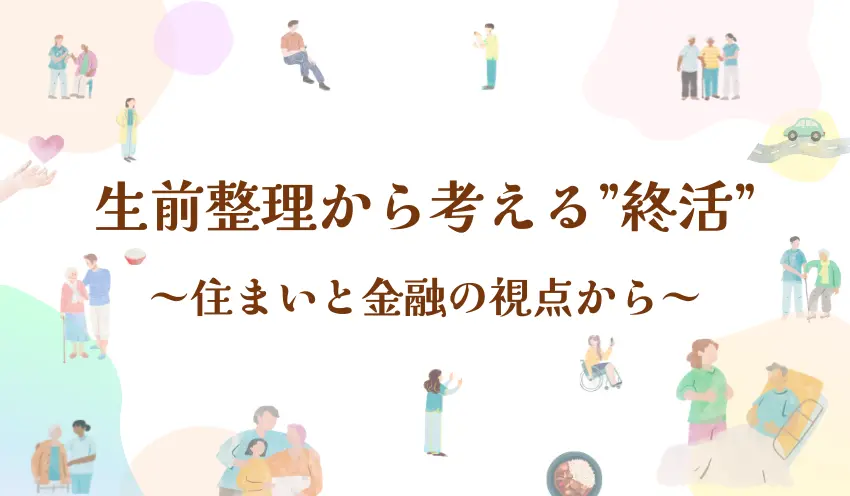

-国産牛乳「危機」から一転-5.webp)