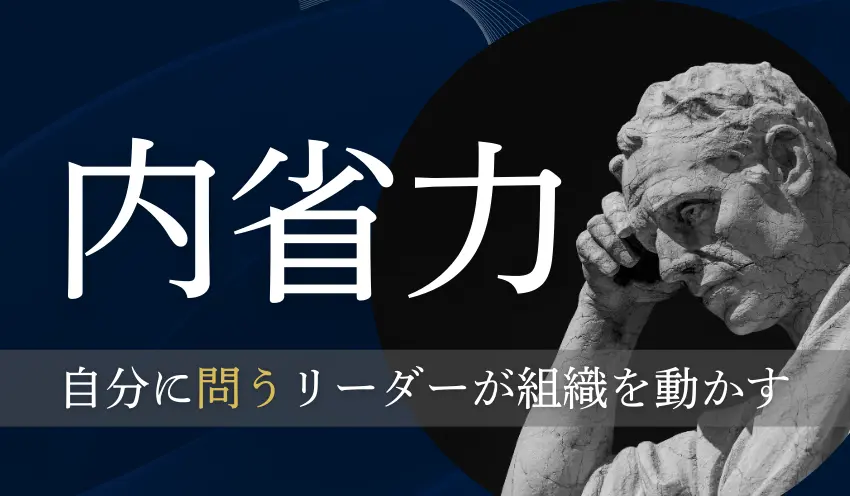2020年に全世界を恐怖に陥れた新型コロナウイルス感染症。外出制限や渡航制限が出され、各国経済に大きな打撃を与えた。今もなお影響は続いているが、徐々に経済活動は再開しつつある。一方、中小企業の管理体制構築を支援する経営コンサルタントの藤原勝法氏は、今後、中小企業からの返済猶予依頼が増加すると予想する。シリーズ「本当の危機はコロナ後にやってくる」は、金融機関職員の目線でリスケ手順などを含め中小企業をどのように支援していくべきかを解説する。
3年目を迎えたコロナ禍の影響は、当初よりは大分落ち着いてきたとはいえ、まだまだ不安な状況が続いています。新型のウイルスが世界に蔓延し、私たち人類に健康被害や生命の危機をもたらしたからです。そして世界経済をも悪化させ、わが国も例に洩れず、大きな痛手を被ることとなりました。
現代の大きな不況といえば、「リーマンショック」や「東日本大震災」を思い浮かべる人が多いと思います。いずれも大きな不況でしたが、コロナ禍は、それらと大きく異なるところがあります。
まず、リーマンショックは金融問題にもとづく不況であったため、その秩序に則って対処すれば、あとは時間による解決が望めるものでした。影響を受ける範囲も限定的でした。
東日本大震災は、原発事故という大被害を伴い、今でも深く日本人の心の傷として残っています。この大震災も当然、経済に大きな打撃を与えたのですが、日本という1つの国だけに起こったものであり、世界規模の不況にはなりませんでした。
そうした点で、いずれも今回とは大きく違っています。経済への打撃は長引き、そして「いつ終わるのかわからない」という不安が、心理的にも大きな負担となっています。特に中小企業においては、心配のタネが尽きませんでした。そして、それは今も続いています。
ところが不思議なことに、資金繰りは、それに比例して悪くなっていないケースが多いようです。飲食業や観光業は大変な状況ですが、それでも、売上の大幅な減少に対し、破綻した企業はそれほど多くはありません。ご存じのとおり、政府が過去に類を見ないほど大規模な経済対策を講じてきたからです。この施策により、企業が支えられ続けているのです。
しかし、企業が耐えられるのも「限界」があります。理由は、政府が支援する原資が尽きてきたほかに、もっと大きな要因が「企業側」にもあると考えられます。企業は、各種の資金繰り支援を受けて一時的に救われたとしても、そのお金は「資本としてもらった」ものではなく、借入金、負債です。

このことに気づいていない経営者は少ないと思いますが、どこまで深刻に考えているかは、人それぞれでしょう。では実際問題として、今後どういうことが起こってくるのでしょうか?リーマンショックを例にとってみましょう。このときも支援策が講じられ、中小企業に「貸しはがし」をしてはいけないとか、返済サイクルの緩和に柔軟に対応するようにといった指導が、金融機関に行われました。「中小企業金融円滑化法」の制定により、法整備も図られました。この施策により、難を逃れた中小企業が多くあったのは確かです。
しかし先にお伝えした通り、これはあくまでも時間的余裕が与えられただけで、借入金(負債)が無くなったわけではないのです。このことを理解していた社長は、時間的猶予の間に対策を講じて、難を逃れたことでしょう。
それに反して、一時の資金難を逃れたことに安堵して、対策を講じなかった社長はどうなったのでしょうか。業績を回復させてキャッシュフローの改善や債務超過の解消ができなかった中小企業は、借入金の返済が開始されると、その負担に耐えられず、事業を継続することができませんでした。いわゆる「倒産」です。
それと同じようなことが、コロナ禍後に起こると想定されます。その規模については、リーマンショック後を遥かに超えるとも言われています。なぜなら、資金繰り支援によって実行された融資の規模が大きいからです。
最悪の事態を避けるには、今からでもしっかりと事業を回復させることに注力しなければなりません。事業の再構築を検討し実行に移したり、あるいは、各種費用を見直し、収入に合わせて支出を抑え、資金繰りを安定させるなどです。
こういった大がかりな経営施策は、中小企業の場合、自社だけの知見や努力で行うのは難しいものです。そこで、中小企業の社長にお勧めしているのがメインバンクへの相談です。メインバンクとは、単に借入残高が一番多い金融機関という意味ではないはずです。取引先の社長が悩みをなんでも相談することができ、それに応じることができる金融機関ではないでしょうか。
中小企業の取締役を務めていた時代に多くの中小企業の経営者にお会いする機会に恵まれました。当時、経営者が金融機関に対する印象でよく聞いたのが、「管理系の話は不得手でよくわからない」とか「苦手でついつい足が遠のく」という話です。うまくつきあえば、事業をより良くすることができます。活用しない手はありません。事業を安定的に且つ継続させていくには、金融機関からの支援が必要です。
金融機関に苦手意識を持つ社長さんは、付き合いたくないのではなく、付き合い方がよくわからないという面が大きいのでしょう。「金融機関ってそんなにとっつきやすい存在なのか」と思ってもらう必要があります。実際に、そういう気さくな方ばかりであると私は感じています。金融機関で働くみなさんは、中小企業の社長にもっと会い、身近に感じてもらうことで結果的に中小企業の事業のお役に立てるのではないでしょうか。

出版書籍:銀行は、社長のどこを見ているのか?「強い会社」を作る35の極意 青春出版社