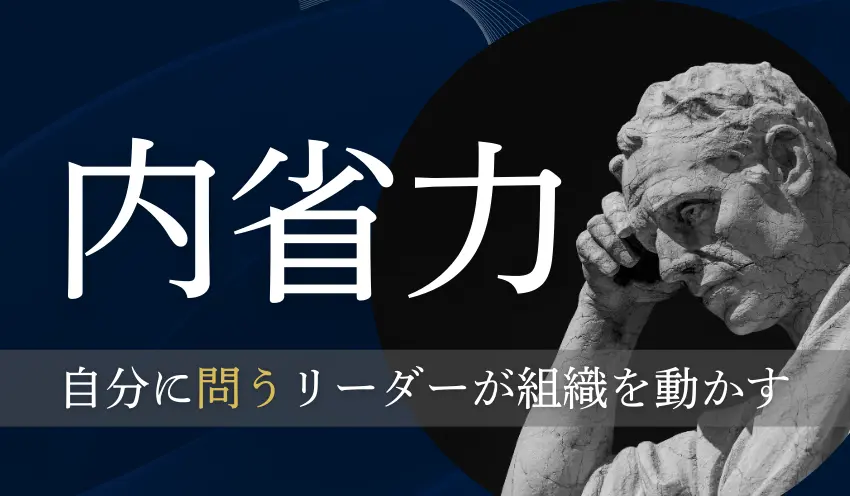
「自分が変わるべきだと、あなたはいつ最後に本気で思いましたか?」
「あなた自身が変わることで、手に入れられるものがあるとしたら、それは何でしょうか?」
組織開発を主眼に置いたエグゼクティブ・コーチングの国内リーディングカンパニー「コーチ・エィ」によるシリーズ「内省力 -自分に問うリーダーが組織を動かす-」。初回テーマは「変化」。
こんにちは。エグゼクティブコーチの内村創と申します。私は日々、大手企業の役員や経営陣の方々と、コーチングの中で対話をしています。その対話の中で大切にしているのが、こうした「問い」を間に置きながら、共に考えていくことです。問いは、ときに心の奥で眠っていた何かを、そっと揺り動かします。そして、静かに、しかし確かに、私たちを「変化」の入り口へと導いてくれるのです。
自分だけは変化の対象外
かつてのように安定が求められていた時代とは打って変わり、私たちは今、スピードと挑戦が強く求められる変化の時代を生きています。
私がコーチするリーダーたちも、変化を求めてコーチングを活用しています。
きっと誰も、自分の会社や組織が「このままでいい」とは思っていないのではないでしょうか。
そのため、コーチングの現場では「何を変えるべきか」という話題が頻繁に出てきます。
社員の意識、組織の風土、経営のあり方、部門や会社を超えたコラボレーション、ミドル層の育成方法……。
「部下たちにもっと主体的に動いてほしい」
「サイロを打破して、もっと協働しないといけない」
「役員同士が全社視点で、遠慮なくやり取りできるようにしたい」
「守りの組織文化を、挑戦の文化へと変えたい」
こうした言葉が、日々語られています。
しかし不思議なことに、周囲にこれだけ変化を求めながらも、「では、まずあなた自身はどう変わりますか?」という問いを向けると、はっと沈黙される方が少なくないのです。これは、その人が怠けているわけでも、自分と向き合う意思がないからでもありません。むしろ、極めて自然なことです。なぜなら、私たちの脳は、根本的に「自分は変わりたくない」と考えるようにできているからです。
脳は“変化”を危険とみなす
人間の脳には、古来より「変化=危険」というプログラムが組み込まれています。脳の「扁桃体」と呼ばれる部位は、予測不能な事態や未知の環境に強く反応し、「変化するくらいなら、現状を維持したほうが安全だ」と判断します。つまり、多少の不満や不合理があったとしても、「慣れ親しんだ不満」のほうが、「未知の可能性」よりも脳にとっては安心なのです。これは進化の過程で獲得してきた、人間の生存本能そのものです。
自己防衛としての“変わらなさ”
脳が変化を避ける理由は、もう一つあります。それは、私たちが無意識のうちに守っている「私はこういう人間だ」というセルフイメージの存在です。
「自分は期待に応えることができる人間だ」
「自分はちゃんとした人間だ」
「自分は冷静で合理的な判断をする人間だ」
「自分は人に弱みを見せない人間だ」
「自分は人に優しく、人の痛みがわかる人間だ」
あるいは、
「自分はこうやって成果を出してきた」
こうしたセルフイメージは、心の安定を保つためにとても重要です。しかし、それが強く固まってしまうと、「変わる」という行為は、まるで自分の“核”を否定するかのような恐れを生み出します。特に、これまで成功体験を積み重ねてきた人ほど、その無意識の抵抗は強くなるのです。
無意識に、問題の“外側”に立つ
こうした変化への心理的な抵抗は、非常に人間的で、ごく自然な反応です。しかし同時に、それは思わぬ盲点を生み出します。
私たちコーチが、日々の対話の中でとても大切にしている考え方があります。
「自分が問題の一部でない限り、あなたは決して解決の一部にはなり得ない。」
つまり、どれだけ熱心に「会社が悪い」「上司が悪い」「部下が育たない」と、自分の外側に原因を探し続けたとしても、それを語っている自分自身もまた、その問題を生み出しているシステムの一部なのです。
たとえば、
部下が挑戦しないと感じている上司は、無意識のうちに「失敗を咎める空気」を作っているかもしれない。
組織が硬直していると感じている経営陣は、自ら率先して変化に飛び込む姿を見せていないのかもしれない。
問題の“外側”に立ち続ける限り、私たちはただの評論家にすぎません。そして、評論家には現実を変える力はありません。本当に変化を起こしたいのであれば、自分もまた、その問題を生み出しているシステムの一部だと認めること。それこそが「自分が変わる」ことの出発点であり、評論家から当事者へと変わるターニングポイントでもあるのです。
ヒーローズ・ジャーニーという変化の物語
「ヒーローズ・ジャーニー(英雄の旅)」という物語の構造をご存知でしょうか。神話学者であり、『千の顔を持つ英雄』の著者でもあるジョーゼフ・キャンベルは、世界中の神話や物語を研究する中で、そこに共通するひとつの構造があることに気づきました。それが、「ヒーローズ・ジャーニー」という物語の型です。
物語は、以下のような流れで進んでいきます。
1. 主人公は、平凡な日常を生きている
2. ある日、「コーリング(召命)」が訪れる(現状への違和感や問題がきっかけ)
3. 最初は恐れて断るが、導き手や仲間の支えによって旅に出る
4. 試練や困難の中で葛藤し、成長していく
5. やがて力を得て、新たな視点を持った自分として帰還する
この構造は、『スター・ウォーズ(エピソード4)』にも、『桃太郎』にも、さらには『千と千尋の神隠し』にも、そのまま当てはまります。「ヒーローズ・ジャーニー」とは、安定から冒険へ、試練を超えて新たな自分へと変わっていく変容の物語です。大切なのは、これは決して特別な誰かだけの物語ではないということ。「変わる」ということは、自分が人生の主役として、物語を歩き始めることにほかなりません。誰かに言われたからでも、外的環境に強制されたからでもなく、自分の内側から湧き上がる違和感や願い、想いに応えて、自らの意志で変化に踏み出す。それが、変わるということです。
この物語のフォーマットが、何千年もの時代を超えて私たちの心を揺さぶり続けているのは、私たちの奥深くに、「変化を乗り越え、成長したい」という普遍的な願いが刻まれているからではないでしょうか。
変化の旅へ、自らの意志で一歩を踏み出す
今、多くのリーダーたちが、かつてないほど大きな変化の只中に立っています。市場の変化、社会構造の変化、価値観の変化。その中で、あなた自身の内側からも沸き起こる必然の声ではないでしょうか。
「このままでいいのだろうか?」
その声こそが、あなたへの「コーリング(召命)」です。最初はきっと、「いや、自分が変わらなくても」、「今じゃない」とその声に蓋をしたくなるかもしれません。それは自然なことです。私たちはみな変化を避け、安定を求める生き物だからです。
でも、だからこそ、今、問いかけてみてください。
「私が変わることで、どんな未来が拓けるだろうか?」
誰かが変わるのを待つのではない。社会や組織が変わるのを願うのでもない。
あなたが、自らの意志で一歩を踏み出す。その瞬間から、あなた自身の物語が始まります。
あなたが望む未来は、他でもなく、あなた自身が変化することから拓かれていく、
多くのリーダー達の変化に伴走してきて、私はコーチとして今そう思っています。
内村 創
株式会社コーチ・エィ
米国 レンセラー工科大学 理工学部 卒業。日本IBM株式会社にて、複数の大規模システム開発プロジェクトを担当。プロジェクト責任者として海外のパートナーと協業し、
数々のプロジェクトを成功に導いてきた。その後、コンサルティング部門の外国人役員補佐、オペレーション部門のマネージャーを務め、
経営チームを支える一員としてグローバル企業の会社運営に関わる。IBM社内のグローバル横断組織変革プロジェクトでは、日本代表として参画した経験を持つ。
2013年、コーチ・エィ入社。2016年、執行役員就任。2025年4月より現職。








