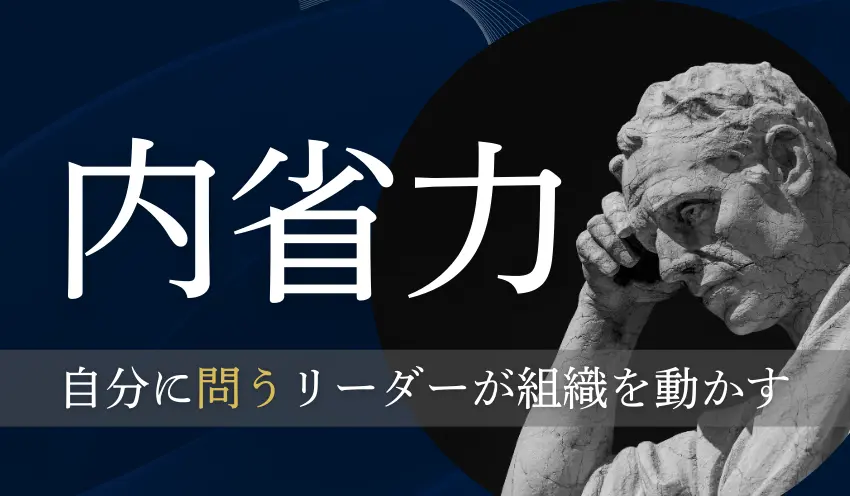金融機関の業務の柱である〝融資〟。住宅ローンなどの個人ローンや、法人向け運転資金、設備資金の貸し出しなど融資業務を通して、地域経済の活性化につなげる。シリーズ「若手営業職に贈る融資業務の基本用語」では、ニッキンが開催するCMCセミナーの講師を務める斎藤和男氏(前城西国際大学非常勤講師)が融資業務の基本について10回にわたり説明する。
ーーー 1.重要な融資業務の位置づけ
銀行法において融資は、三大業務のひとつとして「資金の貸付け又は手形の割引」として預金・為替(決済)とともに定義されています。金融機関にお勤めの方はすでにお分かりのことですが、金融機関において融資業務は非常に重要な位置づけです。貸出金は、金融機関のバランスシート上で資産の5割以上を占めているのが通常です。そのため、資産が生み出す収益として、貸出金の利息が大きな源泉となっています。
全行職員に占める融資業務にかかわる組織や人員は、非常に大きなウエイトを占めています。貸出金の品質を高め、収益面で大きな影響を与える不良債権にならないように、あるいは法律的な側面から違反をしないようにモニタリングする人材も必要だからです。そのほか、監督官庁が預金者に代わり預金がきちんと貸出金などに運用されているかを監督しており、その対応も必要です。信用リスクという言葉が使われていることがあります。


また、貸し出しを行っている取引先にかかる様々な情報を把握するための人員やシステムが重要な役割を占めています。貸出金におけるシステムの役割は、非常に簡単なものですが、貸し出しを行うまでの意思決定に必要なシステムと、その後の貸出金の状況を把握するためのシステムが必要です。
融資業務は、金融機関ではなくてはならない業務であるとともに、非常に手間がかかるため、最近は、AIなどを活用したシステムなどで自動的に判断する試みもなされていますが、人手を最小にとどめることができるには、先であろうと考えられます。
ーーー 2.貸出金の分類を理解すること
融資(=資金を融通すること)という言葉は、世間で一般的に使われている言葉ですが、銀行法では資金の貸付けなどと表現されています。銀行内部では貸付や貸し出しという言葉が使われるのが通常ですが、広義の意味で与信(=相手に信用を供与すること)という言葉も使われます。ここでは勘定科目である貸出金の分類用語を説明します。
貸出金は、資金を貸出先に交付するものと、交付を伴わないものとに大きく分かれます。貸出先へ交付するものは、手形貸付、証書貸付、当座貸越、割引手形です。手形貸付は、取引先に約束手形を差し入れてもらい貸し出しを実行します。約束手形には実行日、期限日、金額などが記載されています。
証書貸付は、取引先から借用証書の提出を求め資金を貸し付けます。証書には、貸付金額、資金使途、返済期限、返済方法、利率などが記載されています。住宅ローンや設備資金、長期資金などに使用されることが多く、最近では貸出金のほとんどがこの形態で行われています。
当座貸越とは、当座勘定を持つ取引先が貸越契約を締結し、一定の金額までのマイナス残高を認めるものです。
割引手形とは商取引において使用された約束手形を期日までの期間がある場合に金融機関が買い取ります。期間までの利息を徴求するので割引手形といいます。
ーーー 3.保証や代理店貸付も融資業務に加える
一方、資金の交付を伴わないものには、支払承諾、貸付有価証券、代理貸付があります。支払承諾とは、金融機関が取引先からの依頼に基づいて取引先の各種金銭債務の保証を行うものです。貸付有価証券とは、金融機関が所有している有価証券(国債や地方債など)を取引先に貸し付けて手数料をもらうものです。取引先は主に官公庁の仕事の入札などに利用します。
代理貸付は、金融機関が政府系金融機関(例えば日本公庫や日本政策投資銀行)の代理店となり、取引先に資金を貸し付けるものです。金融機関は自己の資金を使用しません。
融資関連用語集はこちら!
今回は、勘定科目上の用語を説明しました。次回からは融資業務に用語解説を織り交ぜて解説します。