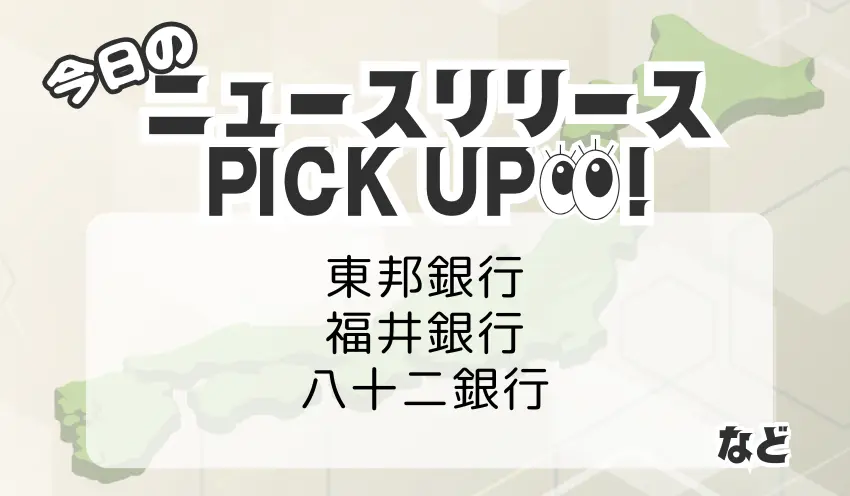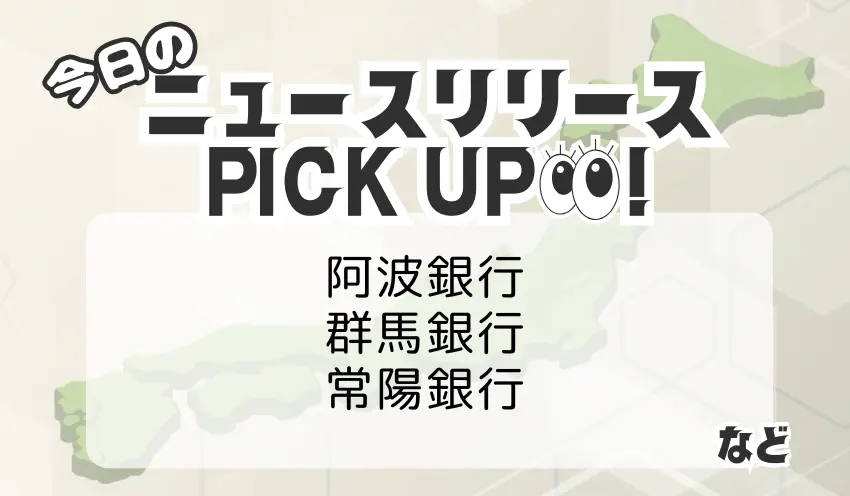NTTデータ経営研究所の執筆陣が連載する「グローバル最先端の決済・金融動向レポート」の最終回。金融環境の変化とデジタルの進展により、取引データを活用した“次世代型の中小企業融資”が今再び注目されている。地銀はデジタルと対面の両輪で顧客との粘着性を高める意義を見出せる。
SME向け融資の武器となるか?
近年、金融機関における中小企業(以下SME〈Small- and Medium-sized Enterprise〉)向け融資のあり方が大きく変化している。大手銀行は従来の与信モデルに加え、新たなアプローチを模索し始めている。その象徴的な動きが、トランザクション・レンディングである。
従来の銀行融資は、決算書や担保に基づいて審査を行うのが基本であった。一方で、トランザクション・レンディングとは、売上や入出金、請求書など日々の取引データを活用して信用力を評価し、融資を行う手法である。
財務諸表に依存せず、リアルタイムに蓄積される取引データを用いることで、審査の迅速化や小口・短期資金への柔軟な対応が可能となる。これは、事業実績の乏しい企業やスタートアップにも融資を提供できる可能性が広がる点が特徴である。
みずほ銀行はスタートアップ企業UPSIDERを子会社化し、カード利用や請求データといった非財務情報を活用した新しい与信モデルの構築を進めている。池田泉州ホールディングスはデジタルバンク「01Bank」を設立し、クラウドファンディング事業者のMakuake(マクアケ)などと連携して得た法人顧客のデータを活用したトランザクション・レンディングの提供を行う。
こうした動きから、取引データを活用した融資が今後一層注目されていることは明らかである。しかしながら、トランザクション・レンディングは2017年頃から「次世代型の中小企業融資」として期待されながらも、日本国内ではいまだ主流化していない。果たして本当に、SME向け融資の「武器」となり得るのか。この問いを解くためには、まず過去の歩みと環境の変化を整理する必要がある。
なぜトランザクション・レンディングが普及してこなかったのか
国内におけるトランザクション・レンディングの導入は、Fintech企業に加え、メガバンクや地方銀行も2010年代後半から取り組んできた。しかし、その多くは数年で撤退や縮小に至った。
第1の理由は、超低金利環境である。2016年に日本銀行がマイナス金利政策を導入して以降、貸出金利は歴史的な低水準にとどまり、従来型の融資で一定の資金需要を満たすことができた。さらに、2020年以降は「ゼロゼロ融資」と呼ばれる実質無利子・無担保の資金供給が政府系金融機関を中心に展開され、SMEにとって低コストで資金調達する手段が豊富に存在した。こうした状況では、あえて新しい融資スキームを選ぶ必要性は小さかった。
第2の理由は、SMEのデジタル化の遅れである。2017年時点でクラウド会計ソフトの利用率は14.5%※にとどまり、請求や入出金を電子的に管理する企業は限定的であった。金融機関にとっても、与信に活用可能なデータを十分に収集できる環境が整っていなかったといえる。
このように、低金利とゼロゼロ融資による資金供給、そして中小企業のデジタル化の遅れという二重の要因が、日本におけるトランザクション・レンディングの普及を阻んできたのである。
※MM総研「クラウド会計ソフトの法人導入実態調査」https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=260
“必要な選択肢”となったトランザクション・レンディングの好機
しかし現在、状況は大きく変わっている。
第1に、金融環境の変化が挙げられる。ゼロゼロ融資の返済が始まり、マイナス金利政策も解除され、現在金利は上昇局面にある。従来型融資の条件が厳しくなるなかで、資金調達手段の多様化ニーズは一段と高まっている。
第2に、デジタル化の進展である。インボイス制度や電子帳簿保存法の導入により、SMEもデジタル基盤を整備せざるを得ない状況となっていることから、取引データの電子化・可視化が急速に進んでいる。これにより、金融機関が与信判断に活用できる環境が整いつつある。
このような市場環境において、これまで「不要」とされたトランザクション・レンディングが、いまやSMEにとって「必要な選択肢」として再評価される好機を迎えているのではないだろうか。
海外事例からの示唆 関係性深めるきっかけ
シンガポールは政府主導で企業のデジタル化を推進し、企業データの整備を早期に実現した。その環境を背景に、シンガポールのメガバンクとなるDBS銀行はDBS IDEAL(法人向けインターネットバンキング)上で中小企業支援のワンストップ・プラットフォームを構築している。決済、外為、融資といったサービスが同一画面に統合され、顧客は日常業務の延長で融資にアクセスできる。さらに会計ソフトやERPとAPI連携し、売上や入出金データをリアルタイムで取得・分析することで、無担保かつ即時のトランザクション・レンディングを実現している。

ここで重要なのは、DBS銀行がトランザクション・レンディングを単なる融資商品としてではなく、企業経営を支える包括的ソリューションの一部として提供している点である。日常的に利用される決済や資金管理と同じ画面の中に融資の申し込みができる機能を組み込むことで、顧客は普段の業務の延長で自然に融資を利用するようになる。その結果、融資は単なる資金調達手段にとどまらず、銀行が顧客の経営に深く関与し、関係性を強めるきっかけとなる。
地方銀行におけるトランザクション・レンディングの提供
では、日本の地方銀行にとって、トランザクション・レンディングはどのような意味を持つのか。
これまで地方銀行は、営業担当者が日々企業を訪問し、財務状況などを把握したうえで運転資金を融資してきた。いわば「顔の見える取引」を通じた情報収集が強みであった。しかし、大手銀行やFintech企業がデジタルチャネルを通じてSME向け市場に浸透するなか、この伝統的なやり方だけでは顧客基盤を守ることが難しくなってくるのではないだろうか。
企業の様々な資金調達需要への対応のため、トランザクション・レンディングの導入が求められる一方、DBS銀行の事例が示すように、トランザクション・レンディングを単なる融資商品のラインナップの一つとして導入するだけでは十分ではない。
重要なのは、企業が日常的に利用する会計、請求、決済といった業務プロセスの中に自然に埋め込む形で提供することである。例えば、地銀がクラウド会計ソフトと連携し、入金遅延や資金不足が検知された際に即時融資の選択肢を提示するような仕組みがその一例である。
こうした設計により、地方銀行は融資をきっかけにデータを蓄積し、顧客との接点を継続的に確保できる。結果として、対面で培ってきた関係性とデジタル上のデータ活用を組み合わせ、「デジタルと対面の両輪」で顧客との粘着性を高めることができる。ここに、地方銀行にとっての意義がある。メガバンクのようにスケールを武器にするのではなく、地域企業の営みに寄り添い、必要な瞬間に確実に資金を届ける。その積み重ねは、単なる金融取引を超えて、地銀が本来担うべき「地域企業の成長支援」という使命を、デジタル時代にふさわしい形で実現することにつながるのではないだろうか。
NTTデータ経営研究所
クロスインダストリーファイナンスコンサルティングユニット
コンサルタント
山下 慎平(やました しんぺい)氏
三井住友銀行を経て現職。
クロスインダストリーファイナンスコンサルティングユニットに所属し、
入社以来は金融機関や大手流通企業を対象に、
金融を軸とした事業戦略の策定・実行支援のプロジェクトに従事。
【関連記事】
地銀の中小企業融資を再定義 / 求められる非対面融資モデルの刷新
口座シフト時代の銀行口座の在り方―アジアにおけるウォレット台頭を踏まえて─
法人向けデジタルバンクは、地銀も目指すべきビジネスモデルなのか? グローバルの事例も踏まえた分析と地銀への示唆