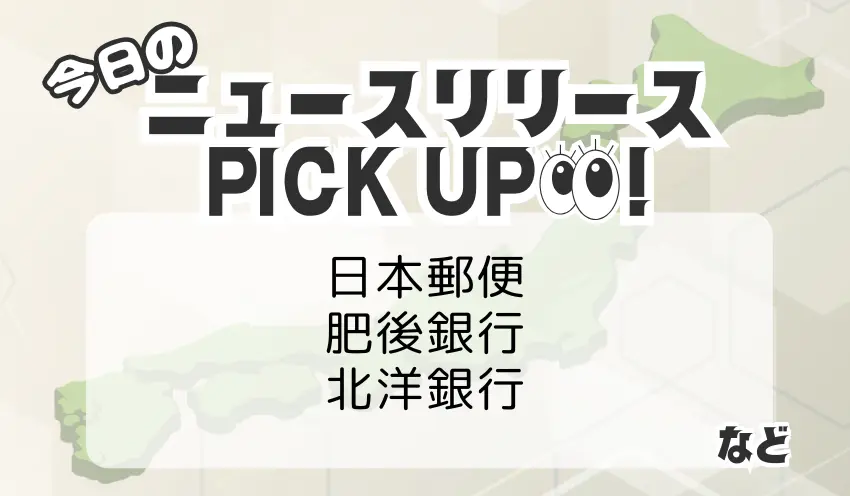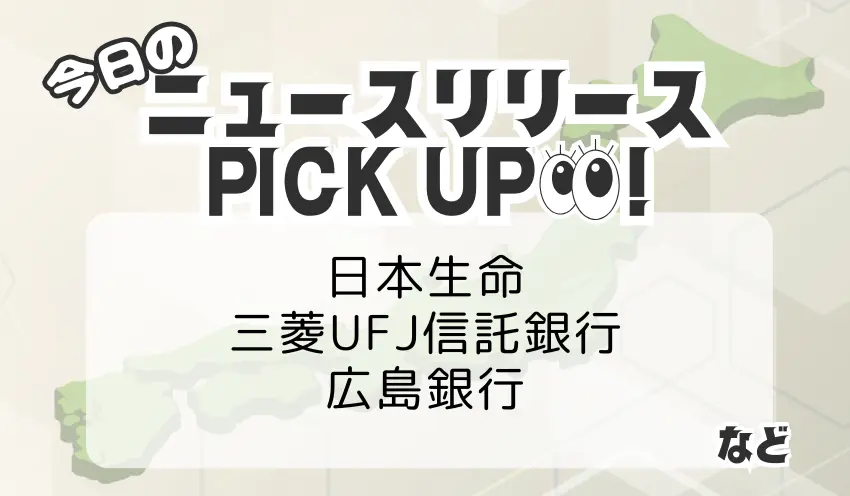NTTデータ経営研究所の執筆陣が連載する「グローバル最先端の決済・金融動向レポート」の第3回。金利ある世界に変貌したなか、地域金融機関の口座や顧客接点のあり方も変わるのか? ウォレットの台頭は預金基盤を揺るがすリスクとして顕在化するのか? この兆候をとらえ、銀行の役割を再定義する。
金利のある世界における「口座」の立ち位置の変化
日本の銀行は、これまでゼロ・マイナス金利の環境下で預金を自然と集めることができたため、金利面での競争優位性を追求する必要が薄く、主に法人融資における手数料収入に目を向けてきたのが事実としてあるだろう。そうした状況下でも、個人顧客との継続的な接点強化は常に模索されてきたが、預金が大規模に流出するなどの喫緊の課題には直面してこなかったため、その取り組みは相対的に後回しになる側面があったと言える。
しかし、金利のある世界では状況が一変する。市場金利が上昇すれば、顧客はより高い利回りを求めて資金を移動させるインセンティブが強まるからだ。資金が銀行口座に必ずしも滞留しなくなるなかで、銀行が口座に残高を集め続けるためには、顧客と継続的につながり、資金を預ける理由や利便性を提供することが不可欠となる。
近年、ネット銀行や、「Olive」、「JRE Bank」に代表される口座起点のウォレット型サービスがリテール市場を席巻しつつあり、口座開設以上に、残高を維持し資金を留保させることの難しさが顕在化している。
こうした構造変化の中、銀行が「口座」や「データ」をどう捉え直し、未来の収益基盤を構築すべきか。本稿では、アジアで先行するウォレットと銀行口座がシームレスに連携する動向に見る「口座シフト」の本質と、それが日本の銀行にもたらす「顧客接点」と「データ」の喪失という新たな脅威、そして変革の機会について考察する。
ウォレットと口座連携の加速:Singapore Fintech Festival事例から見る兆候
2024年末に開催されたSingapore Fintech Festival(以下、SFF)では、We Chat PayやAliPayなどに代表されるようにウォレット間やウォレットと銀行口座が連携し、資金移動がシームレスになるといった動向が示された。
こうした事例は一見アジアにおける国際接続の話に見えるが、実際には日本国内のウォレット型サービスや日常口座にも直結する構造変化を示している。つまり、海外のQR決済やネットワーク拡張は、日本の銀行にとってもリテール預金や顧客接点の在り方を揺さぶる問題として無関係ではない。
なお、SFFで紹介された具体的な事例は以下の通りだ。
【事例1】 roamQR: シンガポールに本社を置くLiquidグループが発表したroamQRは、モバイルのローミングのように、各国のウォレットを相互接続し、ユーザーが自国のウォレットをそのまま異なる国で利用できる仕組みである。2025年内に提供開始予定で、日本市場も対象に見据えている。
この構想による示唆は、銀行口座を代替するウォレットが、資金移動のネットワークを自ら構築し始めた点にある。このネットワークができあがれば、小口決済が銀行口座を経由せずに完結し、銀行口座そのものが置き換わる可能性が出てきているのだ。これにより、銀行からの預金流出がウォレット側にシフトし、ウォレットのネットワーク内で資金が循環するようになるほか、銀行は顧客との最前線の接点を失い、顧客の資金移動に関する重要なデータをウォレットに掌握されるというリスクに直面する。

【事例2】 OCBC×WeChat/Alipay: シンガポールの大手銀行、オーバーシー・チャイニーズ銀行(OCBC)はSFFの期間中に、自社の銀行口座からウォレット(Alipay、WeChat Pay)へ直接送金できるサービスをローンチしたことを発表した。この仕組みは、裏側でVisaの既存のネットワークを利用している。
この事例の重要な意味は、ウォレットが銀行口座と直接つながり、資金を取り込む仕組みを作り始めた点にある。銀行にとっては、ウォレット連携で収益機会や顧客接点を得られる一方で、送金の主役がウォレットに移り、銀行が資金供給者の位置づけに留まるリスクも孕む。これにより、銀行は預金流出という量的な影響だけでなく、顧客接点や資金移動データという質的価値までもウォレットに主導されるリスクを抱えることになる。

【事例3】 Pay Pay: Pay PayはSFF初日に発表されたFortune Fintech Innovators Asia 2024(60社)に選出され、日本を代表する決済事業者としての存在感を発揮していた。パネルトークにて、「日本人観光客に対しても、QRコード決済システムを利用して、日本で体験するのとまったく同じ体験をしてもらうことを検討しており、近い将来にそれを実現しようとしている」との発言があった。
これは単なる決済利便性向上に留まらず、国内ウォレットが国境を意識させない決済の入り口として機能することを意味する。さらに、Pay Payは給与受け取りサービスにも対応を拡大し、「資金の入り口」から「国内外での支払い」までを一気通貫でカバーするネットワークを形成しつつある。
顧客の日常的な資金フローをウォレットが囲い込むことで、銀行はその預金や直接的な顧客接点を失い、顧客の行動データへのアクセスも限定されてしまうのだ。

SFFで目の当たりにしたのは、銀行口座を経由せずにウォレット間、あるいはウォレットと銀行口座間で直接完結する新たな構造の形成である。こうした動きは、ウォレットが送金・決済の入口としての役割を広げ、国内の預金や決済・口座データを囲い込む構造変化を促している。
特に地域金融機関にとっては、こうした動きがマス層の預金流出を加速させ、従来は安定的に集まっていたリテール預金基盤を揺るがすリスクとして顕在化しつつある。
ただし留意すべきは、ウォレットの進化が必ずしも銀行預金への直接的なシフトを一方向に促すとは限らない点である。たとえば「Olive」のように銀行口座と一体化して資金を取り込むモデルと、「PayPay」のようにウォレット内で資金を留めるモデルという二つの方向性が並行して進んでいるのが実情だ。しかし、どちらのモデルを取るにせよ、銀行が顧客接点やデータを自らの手元に残すことの重要性は変わらない。
銀行に迫る構造変化と新たな脅威
銀行にとって、預金・顧客接点・データの喪失は極めて深刻な影響を及ぼす。顧客の行動履歴やニーズを正確に把握できなければ、ライフステージに応じた最適な融資商品や資産運用、あるいはパーソナライズされた商品提案といった魅力的な次なるサービス開発の根拠を失う。結果として、顧客への価値提供能力が低下し、エンゲージメントが希薄化、最終的には既存顧客の離反、ひいては更なる預金の縮小にもつながりかねない。つまり、ウォレットの台頭により銀行が顧客の資金移動の最前線から退場させられ、データに基づいた価値創造の循環が断ち切られることが、銀行にとって最大の危機なのだ。
なお、この変化を単なる脅威と捉えるのではなく、口座を顧客との継続的な接点としてチャンスと捉え直す必要がある。これからは、口座そのものが顧客との継続的接点となり、その中で生まれる活動やデータを基盤として、顧客の信用判断、パーソナルな提案、ひいてはこれまでにない新サービスを生み出す重要な基盤と捉えるべきであるのだ。ウォレットが顧客との主要な接点となる世界では、銀行が顧客接点やデータから切り離されることを許容するのではなく、その接点を能動的に『つなぎ活かす』主体になることが求められるからである。
金融機関に求められる対応
今後は、口座を起点とした顧客との関係性を再構築し、資金の流入から活用までを一貫して支える戦略が求められることになるだろう。その際に、以下の多角的な視点から戦略を練る必要がある。
1. 顧客視点からの価値提供
• 顧客が「この銀行口座がなければ不便だ」と感じる、具体的なメリットをどう提供するか
>個人最適な経済的アドバイスや金融以外の価値提供(地域貢献、ライフスタイル提案など)
• デジタルネイティブ世代や支店に足を運ばない顧客に、どのように口座を「預金先」でなく「日々の生活を支える中心」として認識させるか
>アプリUI/UXの改善、ゲーム性を取り入れた貯蓄・資産形成の仕組みやSNSを活用した顧客エンゲージメントの強化など、デジタルチャネルに特化した戦略
2. データ活用とビジネスモデルの変革
• 口座データをどのように分析・活用し、顧客のライフステージや状況に応じた最適な融資商品、投資機会、あるいは地域の活性化に貢献するサービスへとシームレスにつなげるか
>データの収集だけでなく、その活用モデルの構築
• 顧客が口座内の資金を積極的に動かし、活用する動機をどう生み出すか
>ポイント連携による利用促進、柔軟な資金移動の提供、投資サービスとの連携強化により資金が銀行ネットワーク内で循環するような仕組みづくり
3. 戦略的アライアンスとネットワーク構築
• 外部パートナーシップをいかに戦略的に活用するか
>パートナーシップを通じて、銀行単独ではリーチできない顧客層へのアプローチや、提供できない新たなサービス価値を創出する視点が不可欠。急速に進化するウォレット事業者、FinTech企業、さらには異業種との連携をどう捉え、戦略的に協業を進めるかが問われる。
口座を顧客接点として関係を築き、データを活かして新たなビジネスを生む時代へ。銀行の役割を再定義する今こそ、日本の金融機関にとって大きな転換点であり、チャンスでもある。
NTTデータ経営研究所
クロスインダストリーファイナンスコンサルティングユニット
シニアコンサルタント
髙山 咲希(たかやま・さき)氏
カード会社のバックオフィス部門・新規事業開発を経て、
2021年 株式会社NTTデータ経営研究所に入社。
入社以来、国内外の金融サービスおよび決済システムに関する業界・競合調査を行う。
市場や競合の調査を通じ、金融業界の動向の知見を活かした民間企業・官公庁向けの調査・戦略策定プロジェクトに従事。