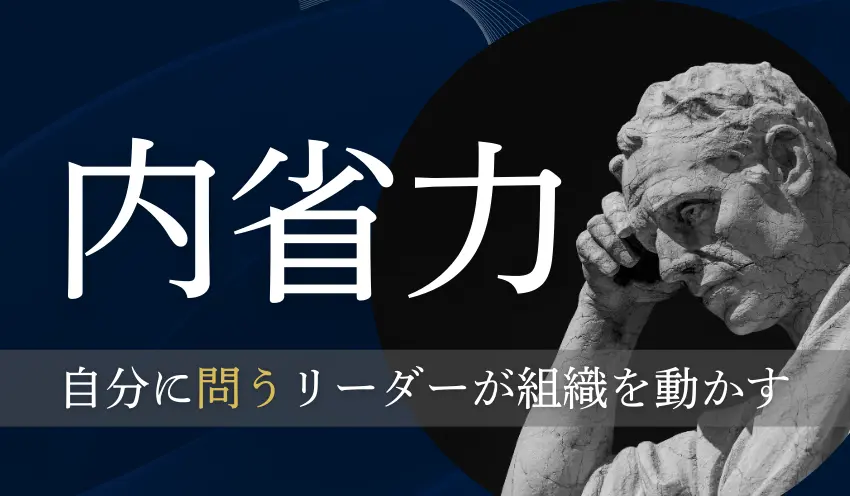独自技術を活用し、医療・介護分野の課題解決を目指して現場のニーズに応じた革新的な製品を開発・提供するリーフの森政男氏によるシリーズ「認知機能と歩行に着目した金融業界の新たな挑戦」。初回は、歩行による認知機能測定器の活用が実現する、金融機関の地域への新たな役割について解説する。
”歩行”データでつかむ兆候
近年、認知症の予防と早期発見は、重要な社会課題となっています。中でも注目されているのが、「歩行」と「認知機能」の関係です。歩行は身体だけでなく脳の働きとも深く関わっており、日常の動作の中に認知機能の変化が表れるとされています。たとえば、歩行速度の低下や歩き方の不安定さが、軽度認知障害(MCI)の初期兆候の一つとして指摘されることもあります。こうした背景から、歩行データを継続的に観察することが、早期発見への手がかりになると期待されています。
当社が開発したPiT(足圧モニタインソール)を用いた認知機能推定システムは、まさにこの点に着目した技術です。PiTは、靴に装着するだけで日常生活における足圧の変化を記録し、歩行のパターンを解析することで、認知機能の変化の兆候を可視化することができます。さらに、判定後には測定結果に応じて無理なく継続できる個別の歩行プログラムを提案できる点も、大きな特徴です。これにより、高齢者の生活に自然に馴染む仕組みを実現しています。
PiTの価値は、単なる計測機器にとどまりません。金融機関の持つ広範な地域ネットワークを通じて、介護施設や医療機関などとの連携も期待でき、「予兆の把握」だけでなく「その後の対応」までを見据えた実用的なソリューションを構築できます。これは、他の予防サービスと明確に差別化できる当社システムの強みでもあります。
顧客の資産管理をサポート
では、こうした技術が銀行業務にどう関係するのか――それは、認知機能の低下が金融取引の安全性に影響を与えるというリスクと密接に関わります。判断力が低下すれば、本人にとって不利な契約や詐欺的な取引の被害に遭うリスクが高まり、結果として銀行側の管理責任や顧客満足度にも影響が出る可能性があります。
加えて、現在の銀行業務では、高齢者が店舗に足を運ぶ機会が減っているという課題もあります。ネットバンキングの普及が進む一方で、対面での相談を必要とする高齢者も依然として多く存在しており、顧客の安全な資産管理をどう支援するかが問われています。ここで鍵となるのが、「歩くこと」の重要性です。
たとえば、セミナーや健康イベントなど、地域と連携した取り組みを通じて高齢者が自然に外出し、銀行に足を運ぶ機会を増やす――そうした動機づけの場に、PiTを活用した健康チェックや歩行サポートを取り入れることができます。これは認知機能の予防に加え、生活の質の向上や地域とのつながりを深める機会にもなります。
健康と金融の両面から支援
ひと昔前、銀行や病院は高齢者の生活の一部であり、日常的に通う「地域の拠点」でした。今回の取り組みは、そうした信頼ある存在としての銀行の姿を、再び地域社会の中に取り戻すきっかけとなる可能性を秘めています。健康と金融の両面から支援することで、地域に根ざした銀行の存在価値を再定義する――その第一歩が、「歩行」から始まるのです。
高齢者が自分の資産を長く安全に管理し続けるために。金融機関が健康支援に関わることは、リスク管理であると同時に、地域社会への新たな貢献のかたちであるとも言えるのではないでしょうか。
森 政男(もり まさお)
リーフ株式会社 代表取締役社長
大手電機メーカのプラントエンジニアリングにてスーパーバイザ従事
多数の国内外の社会インフラ・システムの立上げを経験(アジア専門)
2008年1月にリーフ株式会社を設立