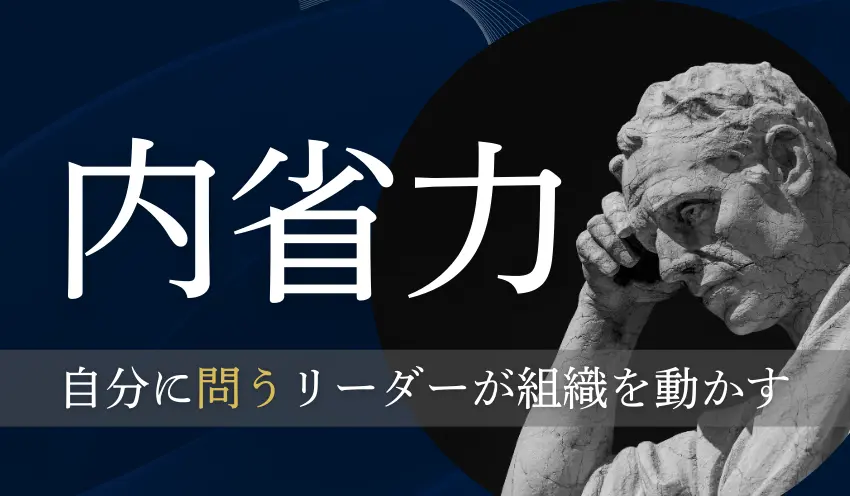前回のシリーズ「金利のある世界~本質の理解と顧客交渉術~」では、金利の歴史的な役割や、融資を中心とした金利の基本について解説しました。今回から新たに始まるシリーズ「金利に強くなろう」では、もう少し幅広い視点から金利について取り上げていきます。
1.金融市場
金利とは、お金の賃借料という意味を持つものですが、そのお金をやり取りする場がなくては、金利としての機能を果たすことはできません。このようなお金のやり取りが行われる場を「金融市場」と呼びます。金融市場では、資金を必要とする側と、資金を運用したい側との間で、お金をやり取りすることが日常的に行われています。
金融市場は、その参加者のあり方によって、大きく2つのタイプに分かれています。ひとつは「市場取引型」で、多数の資金の貸し手と借り手が参加して取引を行う場であり、これを狭義の「金融市場」ともいいます。
もう一つは、基本的に1対1で取引が行われる「相対型取引」です。金融機関との取引がこれに該当し、貸出取引では金利などの融資条件に関する交渉が行われます。また、預金取引では、預入者と金融機関が預金金利などの条件で取引を行います。
このように金融市場では、参加者が金利を支払って資金を調達したり、金利を受取って資金を運用したりしています。これらの金利は、経済状況によって変動しています。
2.金利と利回り
前回のシリーズでも説明していますが、復習のために再度説明します。
「金利」とは、資金の借り手が貸し手に対して、借り入れた金額(元本)の一定割合を期間に応じて支払うもので、「利子」あるいは「利息」とも呼ばれます。その水準は「利率」や「利子率」と呼ばれ、1年あたりの「年利」で年何%と表示されます。
一方、「利回り」は運用した資金額に対する収益の割合を示す指標であり、金利と同様に1年あたりの値で計算・表示されます。債券や株式などの投資においては、この利回りが収益性を判断する際の重要な基準となります。利回りには利息だけでなく、売却益(または売却損)なども含めた収益全体が反映されます。詳しくは第3回「債券市場とその利回り」で解説します。
3.市場取引型の市場と金利
このタイプの市場は一般的に「公開市場」と呼ばれ、短期金融市場と長期金融市場に分類されます。1年以内の金融取引が行われるのが「短期金融市場」、1年を超える金融取引が行われるのが「長期金融市場」とされ、それぞれ短期金利と長期金利が適用されます。
短期金融市場は、金融機関のみが参加できる「インターバンク市場」と、一般企業なども参加できる「オープン市場」に分かれています。
長期金融市場には、「債券市場」と「株式市場」が含まれます。これらの市場では、債券や株式(証券)の売買が行われ、長期の資金を調達する市場であることから、「証券市場」あるいは「資本市場」と呼ばれています。
金利は一般的に、長期金利の方が短期金利よりも高い水準にありますが、理論上は短期金利が長期金利よりも高くなるケースも生じます。
代表的な短期金利には、コール市場(次回で説明)における金利である「コールレート」があります。一方、長期金利の代表は「10年物国債の流通利回り」です。短期金利は、日本銀行の金融政策によって大きく変動します。長期金利は、将来の経済の先行き、物価変動、短期金利の水準などに対する市場の「予想」に大きく影響されます。
4.預金市場と預金金利
預金市場とは、金融機関と預金者の間で取引条件(金利)が決定される相対市場です。預金を行う際、通常は当該の金融機関が公表している金利が自動的に適用しますが、顧客の取引状況に応じて金利が上乗せされるケースもあります。また近年では、一般的な定期預金に加え、複雑な条件を伴う「仕組預金」も登場しています。
預金金利の計算方法には「単利」と「複利」があります(詳細は前回のシリーズを参照)。近年、日本銀行の金融政策の転換を受け、預金金利の水準は上昇基調に変わってきています。各金融機関の金利水準を注視することが重要です。
貸出市場および貸出金利については、前回シリーズで解説していますので、今回は割愛します。
次回は、主に短期金融市場とその金利について解説します。