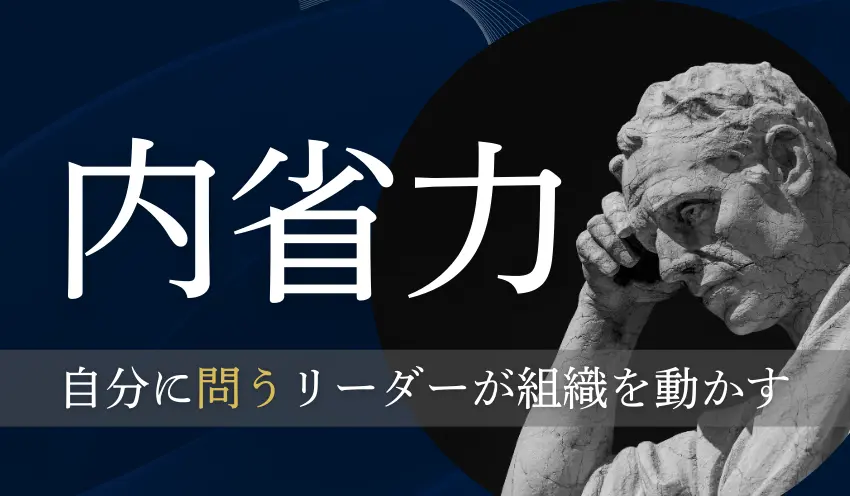昨今、テレビCMなどで多く取り上げられている認知症。り患すると金融機関口座が凍結される可能性もあり、家族でも引き出しができなくなる。将来のリスクに対応するため、成年後見人制度や家族信託の案内を強化。生命保険会社や家族信託などの支援サービスを提供する企業と連携しセミナーを開催し未然の対応を促している。しかし、非対面チャネルの拡充を進めてきた金融機関では、営業店の顧客接点が乏しいのが現状だ。
認知症は誰しも気にしている病気。今回取り上げる歩行の特徴でリスク計測ができるツールは、病院に行く必要がなく、わずか数分で将来リスクも含め計測できる。計測と金融商品・サービスの案内をあわせたロビーセミナーの実施は、顧客接点の拡大が期待される。
◆介護離職につながる深刻な社会問題
人口の高齢化とともに認知症にり患した患者数は増加傾向を続けている。総務省統計によると65歳以上の高齢者は2024年9月時点で3625万人と総人口の29.3%を占める。一方、認知症の患者数は、2022年に443万人(厚生労働省調べ)と言われ、高齢者人口の10%を超える。さらに日本医療研究開発機構(AMED)認知症研究開発事業が行った調査(2017年度~2019年度)によると若年性認知症有病率は18歳~64歳人口10万人当たり50.9人で、推計値で総数は3.57万人としており、年齢に関係なく深刻化している病気だ。

認知症の予防には運動や食事など生活習慣に気を配るとされているが、確実に予防できるものではない。
政府は2024年12月、今や国民誰もが認知症になり得るという認識のもと認知症施策推進基本計画を閣議決定した。認知症になってからも、一人一人が個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるという「新しい認知症観」で、地域住民、教育関係者、企業等地域の多様な主体がそれぞれ自分ごととして、連携・協働して施策に取り組むことを求めている。
◆歩行の特徴(足圧)を計測 1分程度で診断!
一般的な認知症の診断は、診察・身体検査・神経心理学検査・脳画像検査とされる。神経心理学検査には長谷川式簡易知能評価やMMSE(ミニメンタルステート検査)などがあるが、いずれも医療機関で受診する必要がある。いずれにせよ、これら診断方法は認知症にり患しているか否かの判断をするための検査であり、早期発見には有効だが、将来のり患リスクの判断は難しい。
今回注目するのは、医療・介護分野で各種装置、計測器を開発しているリーフ社(福岡・北九州市)が開発した歩行するだけで認知症の疑いを測定できる計測器。同社と国立高専が共同で開発した認知機能低下のリスクを指数化する技術を搭載している。専用のサンダルを履き、1分程度の歩行のあと、数十秒で結果がタブレット上に表示される(下記動画はデモのダイジェスト版、詳細は、プレミアム動画で※無料)。歩行時にかかる足圧を計測した認知機能低下リスクの有効性は、多くの研究者から研究論文が出されている。開発した計測器は、現段階では研究論文によるモデルデータをもとに判定しているが、商品化(価格は未定)予定の2025年4月以降、大学病院などと提携し、データを蓄積、精度を高めていく方針だ。販売元のベンチャー企業、ヘルステクノロジーラボ社(東京・中央区)の佐々木一成社長によると、歩き方から将来、認知症にり患する可能性が判るという。
◆ロビーセミナーに有効か
場所を選ばす、わずか数分で計測できるのであれば、営業店で来店顧客に実施することが可能。紹介した両社には、すでに地域金融機関から問い合わせが入っているという。家族信託や成年後見人制度を案内するセミナーに併せた来場者特典とすれば、日頃面談できない顧客との接点が作れると期待される。
介護離職を経験した佐々木社長の後悔 早期発見できていたら、、、(体験談)
♣ 母の変化に違和感
10年ほど前の話ですが、1人暮らしの母が75歳を超えたときに、行動に違和感が出てきたため、ケアマネジャーさんに相談して検査を受けたところ軽度認知症と診断されました。しばらくは在宅で、定期的にヘルパーさんに来ていただいて介助いただいてましたが、徐々に母の様子が変化していくのが分かりました。
私の母は、もともと優しくておっとりした性格でしたが、言葉の端々にトゲがみられるようになり、適切な表現ではないですが凶暴性が出るようになり、“これはおかしい”と病院に連れて行きました。長谷川式による判定をしたところ医師からは「佐々木さん、お母さんはかなり進行していますね」と言われ、施設への入居を勧められました。

♣ 施設入居で認知症が進行 心身ともに消耗する日々
その後、医師の勧めで施設に入居しましたが、症状は一層進行してしまいました。施設への入居で体を使った活動が少なくなり、結果、脳の血流が落ちてしまったことが原因のようです。施設では、ちょっとした運動やリハビリはありますが、しっかりとした運動プログラムが用意されているわけではありません。当時、認知症にり患して施設に入居すると自宅に戻ることはできないと感じました。私の場合は、弟が居て協力してくれましたが、「お金取られたからすぐ来て取り返せ」などと昼夜問わずの母親からの電話に加え、施設からも、「他の部屋に入ってしまい、おもらししてしまった」など迷惑行為の度重なる連絡が届き、心身ともに消耗していきました。最後には、施設の担当者から「私どもではお預かりできないので他の施設を探してください」と言われてしまいました。
♣ あの時こうしていれば、、、早期発見の重要性
そのような状況が続くと、正直、仕事をしていられません。介護に巻き込まれる肉親は、本当にしんどいです。認知症ってなってしまうと、元には戻れません。認知症にならないようにするしかないと痛感しました。もう少し早く気づいてあげることができたら、母の言動に違和感を持った時にリハビリプログラムを受けていたら、してあげられることはいろいろあっただろうと早期発見の重要性を感じるとともに今でも後悔しています。
♣ 金融機関の協力あれば支援進む
親が認知症になれば必ず肉親も巻き込まれます。早期発見には、地域や近隣住民が協力しあうことが重要です。日頃顧客と接している金融機関の方々が気遣いや相談に乗ってくれる存在であれば理想だと思います。