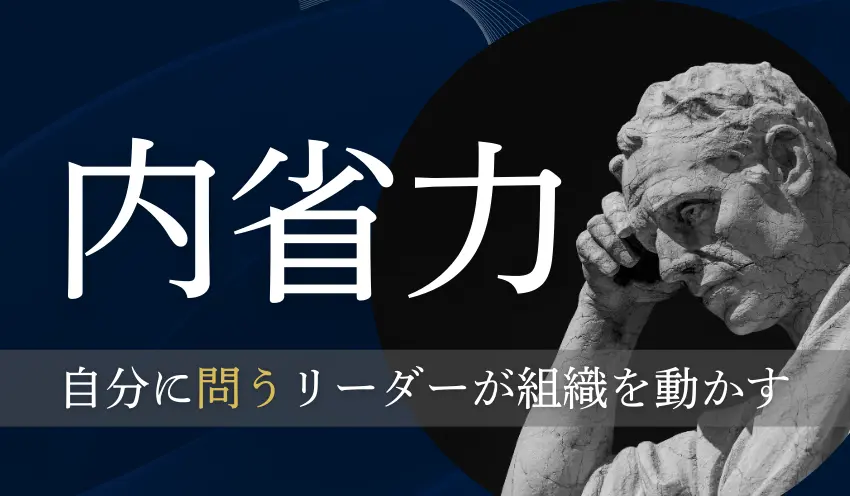アプリの機能強化などで非対面取引の拡大を進める地域金融機関。デジタルマーケティングに力を入れ非対面チャネルでの情報収集やサービス強化を目指している。しかし、400Fの中村仁社長CEOは「メルマガなども大量に送られてくる時代において単なる機能・コンテンツというのはユーザーにとっては何の価値もない」と言い切る。「顧客の状況に合わせてどのような顧客体験を設計するかを構築することが非常に重要」と訴える。シリーズ「地域金融機関が避けて通れない対話型金融」では、対話型金融の重要性を説く。初回は「FinTech登場から10年」と題し、地域金融機関が置かれている現状を解説する。
FinTechという言葉が日本で広がり始めてから10年が経過しようとしている。果たしてFinTechは日本の金融業界を大きく変革したのだろうか?確かにキャッシュレス決済やロボアドバイザーなどを取り扱い、上場企業として一定のポジションを築いた企業も登場している。
しかし、金融業界全体の変革を果たしたかというと残念ながらそれはない。日本はFinTechが業界全体をディスラプト(破壊)した国々とは異なり、un-banked(銀行口座を持たない)なユーザーがほぼいないことや、金融機関に対するサービスへの不満は諸外国と比較すると相対的に低い。そのため、FinTechの時流を取り込んだ既存のネット金融機関が飛躍を果たすきっかけにはなったがFinTechスタートアップによる躍進は限定的なものにとどまる。
では、このまま日本のFinTechの波は収まってしまうのだろうか?数年前まではそのような状況になりつつある雰囲気があったかもしれない。しかしデータとAIの活用が新時代に突入した中で、その様相は変化してきたと感じる。今後は対話型金融を積極的に活用できる企業が(その中には地域金融機関も含まれる)次の10年の勝者になると考える。本稿ではその背景などについて説明していきたい。
地域金融機関を取り巻く環境
地域金融機関を取り巻く環境については、さまざまな考察がなされている。地方の人口減少や高齢化、後継者問題に起因する廃業、そしてそれによる地域経済の衰退など、地域金融機関は厳しい状況に置かれているところも少なくない。
長らく続いたゼロ金利政策により、本業の利鞘ビジネスも収益性の低下に晒されていたが、ようやく金利のある世界が復活する見込みだ。では、金利上昇により地域金融機関の経営環境は改善されるのか。
日本総研の「金利のある世界」で顕在化する地銀の金利リスクと今後求められる対応というリサーチレポートによれば、預金金利の引き上げが先行する中で、貸出金利引き上げの交渉が難航するリスクや、金利上昇局面でのネット金融機関への預金流出懸念が指摘されている。
そのような中で、地域金融機関では2025年より本業である金融仲介機能の強化に向けたリソース強化に動く経営方針が増えているとの話を聞くことがある。実際に地域金融機関を訪問する中でも「来年は預金獲得や貸し出し強化の戦略が中心になる」との声を多く聞く。
経営資源には限りがあるため、一つの戦略にリソースを傾けると、他の戦略には十分な手が打てなくなるのが常だ。ゼロ金利時代は収益力を上げるために役務取引に力を注いでいた地域金融機関も、金利のある世界においては、利鞘ビジネスに大きく舵を切っていく可能性が高いのではないか。
次回は、ネット証券・銀行の台頭するなかで、地域金融機関の預かり資産ビジネスについて取り上げる。
 中村 仁 氏(ナカムラ ジン)
中村 仁 氏(ナカムラ ジン)
代表取締役社長 CEO
関西大学卒業後、野村證券入社。支店営業後、野村資本市場研究所NY事務所にて米国金融業界の調査及び日本の金融機関への経営提言を行う。
帰国後、野村證券の営業戦略の立案及び世界中の金融業界の調査も行う。
2016年4月にお金のデザインに入社し、2017年3月より代表取締役CEO就任。
2018年7月より400F代表取締役就任。一般社団法人日本金融サービス仲介業協会代表理事会長。