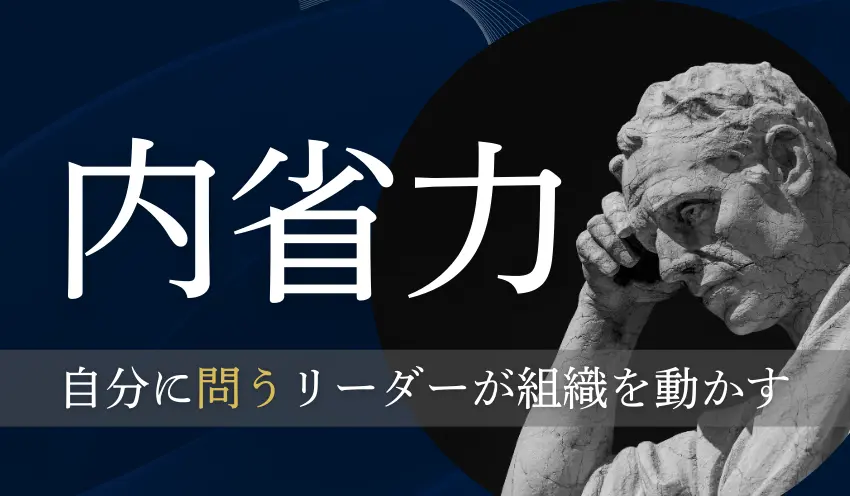ニッキンONLINEプレミアムで「しあわせに働くためのコミュニケーションとマインドセット」を連載中の宮道京子先生は20年ほど前から数々の金融機関に向けて〝価値観を新しくする 〟必要性について説いてきた。時代の流れが速い今、金融機関の現状や今後どのように改革していくべきか、インタビューに答えた。今回から5回に分けて紹介する。第1回は宮道先生の研修を、なぜ金融機関が求めるのか。“金融機関に足りないもの”を時代の流れとともに説明する。
シリーズ一覧はこちら!
―――提供する研修の特徴は?なぜ多くの金融機関は宮道先生に研修をお願いするのでしょうか?
京セラ創業者の稲盛和夫さんが提唱する方程式、「人の成長や企業の成功は、やる気×能力×考え方」という考え方があります。経営者であれば稲盛さんの本を読んで頭に入っているような言葉です。「やる気×能力×考え方」の〝やる気〟というのが、いわゆるエンゲージメントになります。能力を身につけるためのものが、今までやってきていたスキル研修です。しかし、いくらやる気があって、能力があっても考え方が古ければそれを使いこなせません。
私の研修はHow toではありません。要はやり方を教えるのではなく考え方を伝える研修です。あとはあり方、〝being〟です。能力の研修ばかりやっていたときにモチベーションの研修も行っていましたが、モチベーションに対する〝考え方〟とセットになってないと納得感がないのでモチベーションが継続しません。金融機関さんに一番足りなかったものはこの考え方です。
私はモチベーションと能力をどう掛け合わせるかを研修でお話しています。そうすると「そういう話は今まで聞いたことがなかった」とか、「そういうふうにものごとを考えていけばいいのか」とか、「そういうエビデンスがあるのか」などの声をよくお聞きします。この考え方を教える研修が、今の時代には需要があるのだと思います。
考え方は、皆さんのOSだと思ってください。古い考え方のOSのバージョンの上げ方をしっかり伝えるので、自分が少しバージョンアップできた気になると、今やっている仕事に対する能力ややる気をどのように回せば良いのかが見えてくるので、自分の進むべき道筋が見えやすくなります。それが私の研修の特徴ですね。

―――以前からそのような研修を提供してきたのですか?
そうです。心理学と脳科学と、行動科学の三つの学問をベースとしていて、そこに経済学や行動経済学なども取り入れ、そのエビデンスを持ちながら「こういうふうに考え方が変わっていきますよ」と伝えています。私の経験値だけでは経験を伝えるにとどまってしまいますから。その裏付けになる根拠がないと、考え方は変えられないですよね。例えば京セラの稲盛さんのように実際に京セラという大会社を作った人なら、その根拠がなくても京セラという会社自体が根拠になるので、聞く人はうなずきますが、私のような一講師の場合、この考え方を教えるときには学問をベースに根拠を交えて話をすることで、「時代が変わったのだな」と皆さん納得してくれます。
もう一つ言えることは、「価値観が変わっていく」ということを説く研修がすごく少なかったのです。価値観ってすごく重要なのに行動と環境のことばかりを言い続けていて。それを作っているのが価値観なのに、それを説く研修が金融機関さんでは全く行われていませんでした。2023年から人的資本経営という経営のあり方が取り入れられましたが、まさにこれから価値観を変えていかないとこの人的資本経営を取り入れられないわけです。そして価値観を変えるとか共有化するとか、創造するというふうにフェーズが移り変わっているところなので、研修の依頼が増えているのでしょう。社会が価値観を重視するフェーズに入ってきたと感じます。
 宮道 京子 氏(みやみち きょうこ)
宮道 京子 氏(みやみち きょうこ)
テレビ局勤務経て、2001年に独立。中小企業診断士のメンバーと中小企業・医療機関のコンサルティング業務に携わりながら、社員教育の重要性を感じ、心理学・脳科学・行動科学をベースにした研修会社、株式会社シー・マインドを2006年に設立。金融機関・医療機関を中心に研修や講演を行っています。
幸福学・ウェルビーイングの観点から、幸せな働き方とはどのような働き方なのか、今後のキャリアをどのようにデザインしていくか、これからの時代のマネジメントはどう変化するのか、サステナビリティ経営とはどのような経営なのかをあらゆる階層に方々にお伝えします。