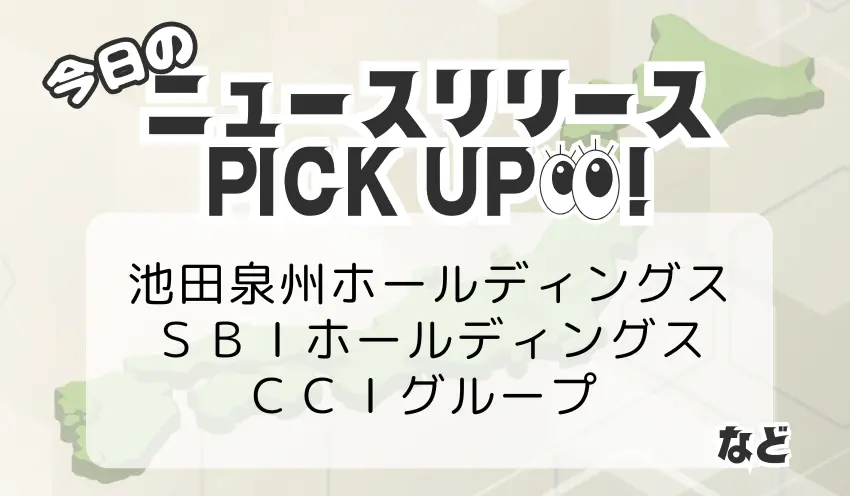生産年齢人口の減少や国際競争力の低下など、様々な要因で経済の長期停滞が続く日本。打開策の一つとして期待されるのが、創業間もないスタートアップ(SU)企業による新事業の創出だ。政府は2022年11月に「スタートアップ育成5か年計画」をスタートし、国内2万社超のSUを支援する体制を拡充。同時に金融・非金融面で官民一体の更なる後押しが求められている。シリーズ「潜入!SU最前線~Revival of Japan~」では、社会課題の解決を目指し多様な分野で活躍するSUの取り組みをインタビュー動画を交えて紹介。SUの最新事情から日本再興への確かな糸口を探る。
期待される「創造的破壊」
IMF(国際通貨基金)によると、日本の国民一人あたりの名目GDP(国内総生産)は世界33位(2023年10月時点)。2023年の国別GDPではドイツに抜かされ、世界4位となることがほぼ確実視されています。
一方、経済の新陳代謝とも呼べる企業の開業・廃業率に目を向けると、こちらも欧米各国と比べて低い水準で推移していることが分かります。産業構造の転換を円滑に進めるためには、今こそ開業・廃業率を高めて日本経済を活性化する「創造的破壊」が求められています。

欧米各国と日本の開業率の推移

欧米各国と日本の廃業率の推移
(出所)内閣官房「スタートアップに関する基礎資料集」(2022年10月)
SU支援は「国策」
新しい技術やアイデアで社会課題を解決し、同時に事業拡大を通じて日本経済を刺激する存在として、政府はSUに大きな期待を寄せています。2022年11月に開始した「スタートアップ育成5か年計画」では、①人材・ネットワークの構築②資金供給の強化と出口戦略の多様化③オープンイノベーションの推進――を3本柱に掲げ、経済産業省や文部科学省、厚生労働省など関係省庁が連携してSUの担い手育成や起業の加速を実現するエコシステムの創出を急いでいます。
SUが集積する東京都では、同時期に「Global Innovation with STARTUPS」を策定しました。5年間で東京発ユニコーン(企業評価額10億ドル以上)数10倍、東京の起業数10倍、東京都の協働実践数10倍の「10×10×10」を目指す取り組みです。2023年9月には都と協働する協定事業者50者を採択し、協定期間と定めた1年半の間に定期的な情報交換会や成果報告会・コンテストを開催して多彩な支援を展開していく予定です。
都の取り組みでは、創業・成長支援プログラムの一つに位置付ける「NEXs Tokyo」(ネックス トウキョウ)も注目を集めています。同事業は、都内に拠点を置き全国や世界に事業展開を目指すSUを「JUMP」会員、都外に拠点を置き都内での事業加速を目指すSUを「DIVE」会員と名付け、両会員やパートナーが利用できる場所を提供するなどネットワークの構築に力を入れています。パートナーには10行以上の地域銀行や銀行発ベンチャーキャピタル、複数の信用金庫、100を超える自治体が参画しています。
金融機関の支援に期待
今後期待される政策の一つが、「事業成長担保権」(仮称)の創設です。金融機関が融資を判断する場合、現行では土地や工場などの有形資産が担保権の対象となります。同制度の創設によって、新たに事業価値や将来性といった事業全体を担保として成長資金を提供する融資手法の広がりが期待されます。創設時期は未定ですが、SUにとっては同制度を活用してベンチャーキャピタルや投資ファンド以外から資金調達しやすくなることは大きな後押しとなるはずです。
ただ、いくら支援体制や制度が整備されても、資金を提供する金融機関側の事業を見定める力が養われなければ意味がありません。
今シリーズでは、ベンチャー企業支援で豊富な実績を持つデロイト トーマツ ベンチャーサポートらが実施するMorning Pitchの登壇企業等の中から各分野で革新的な事業を展開するSUを動画を交えて紹介します。目利き力を養うヒントや、金融機関によるSU支援につながれば幸いです。