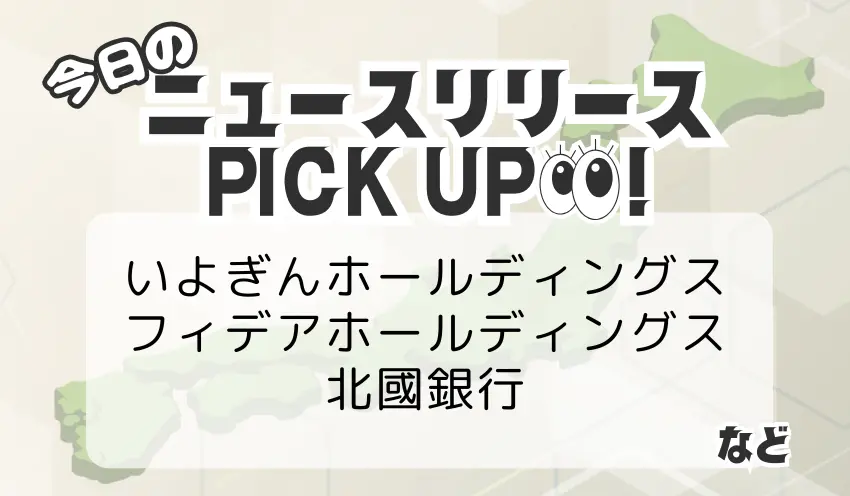2024年10月17日(木)・18日(金)に、国内最大級の金融機関向けITフェア「Financial Information Technology(金融国際情報技術展)」(以下、FIT)が開催されました。このFIT内で当社が行ったセミナーの一部分を複数回に分けて紹介します。今回は当社の社外取締役でメルカリなどを経て、現在はGrowth Camp社の樫田光社長とデータ活用の未来について経営者の視点も交え解説した内容を紹介します。
◆データで出来ることの理解を深める -専門家が果たすべき本当の役割-
樫田 データベースに関わる専門職の最も重要な役割は「何ができるか」を説明する以上に「何ができないか」を理解し、伝えることだと考えています。データやデザイン、AIなどの新しい技術が登場すると、多くの人は「これさえ使えば、すべてが解決する」といった銀の弾丸のような期待を抱きがちです。しかし、実際にはそれらが期待に応えられない場合も多く、その結果として混乱や不信感が生まれます。こうした状況を避けるために、専門家は新技術の限界や適切な使用方法についても理解し、どの場面で有効で、どの場面で使うべきではないかを明確に示すことが必要です。
ここ数年、メルカリ等でデータの価値を高め、データ活用の文化を醸成する取り組みをしてきましたが、全人類が思っている以上に、データが効果を発揮する場面は限られています。特定の状況では大きな力を発揮しますが、すべての課題をデータで解決できるわけではありません。この事実を深く理解する必要があります。
中村 私も、日々多くの金融機関の皆さんとお話をする中で、「手段」の部分には皆さん熱心に取り組んでいらっしゃると感じています。しかし、そもそも「どのように考えるべきか」という基本的な視点がないまま進行し、データを上手く活用できていない事例を複数拝見したことがあります。そのため、私たち400Fはコンサルティングに入る際、データ分析の定義を行うところから携わっています。後に、実例も交えお話しします。
◆データで出来ることの理解を深める-メルカリにおけるデータ活用の考え方
次に、メルカリの上場前後でのデータ責任者としての経験をもとにデータ活用の事例を紹介します。
樫田 スタートアップ業界で「ユースケース」という言葉が使われるように「誰がどのような課題を抱えている場面でデータが機能するのか」を特定することが重要です。ビジネスの現場では、自社のビジネスを分解し、どこにデータを適用できるユースケースがあるのかを考えることが求められます。

メルカリのようなサービスは、基本的にユーザーにサービスを提供し、ユーザーが何らかの対価を会社にもたらしてくれるものです。よくLTV(顧客生涯価値)といった言葉で表現しますが、ユーザー1人あたりにどれだけの価値があるのか、といったことを指します。一方で、ユーザーを獲得するためには、金融業界などでもよく使われるCPA(顧客獲得単価)といった概念もあります。CPAにもデータが活用できることは想像できると思います。さらに、獲得したユーザーから全体の売り上げ、いわゆるレベニューが成り立っていき、レベニューを上げるためにどのような分析をしていくかも重要なポイントになります。また、ユーザーを維持するためのカスタマーサービスやCRMを通じて、例えばクーポンを発行する等の施策が費用を伴う場合もあり、メンテナンスコストに関してもデータの適用価値があると思います。このように分解して考えることができますが、実はそれぞれの分野で適切な分析手法や提供できる価値が異なるため、それらを一括りにして十把一絡に扱うのは危険だと感じています。
ユースケースが異なれば、必要な知識も異なり、適用するためのデータ人材に求められるスキルや資質も異なるのです。下図に挙げたものはあくまで一例に過ぎませんが、ビジネスにおけるデータ分析を考える際には、「ビジネスデータ分析」といった大まかな捉え方ではなく、ビジネス全体を適切に分解し、どういったシーンやユースケースがありそうかを考える必要があります。「データから始める」というより「自分たちのビジネスがどのように成り立っていて、どこに問題があり、それがデータで解決できるかを考えること」がデータ活用の起点になるのではないかと考えています。

中村 私からはデータ活用における経営者からの視点として、プロダクト作りというのは最終的にはビジネスのために行うものだということであり、優秀なデータ担当者やプロダクトマネージャーは、最終的にビジネスをどう成長させていくかに結びつけることができる人だと考えています。
次回は、メルカリでの経験をふまえたデータ分析の注意すべき点や、データによる4つの階層などについて紹介します。
 中村 仁 氏(Jin Nakamura)
中村 仁 氏(Jin Nakamura)
代表取締役社長 CEO
関西大学卒業後、野村證券入社。支店営業後、野村資本市場研究所NY事務所にて米国金融業界の調査及び日本の金融機関への経営提言を行う。
帰国後、野村證券の営業戦略の立案及び世界中の金融業界の調査も行う。
2016年4月にお金のデザインに入社し、2017年3月より代表取締役CEO就任。
2018年7月より400F代表取締役就任。一般社団法人日本金融サービス仲介業協会代表理事会長。

樫田 光 氏(Hikaru Kashida)
株式会社400F 社外取締役
早稲田大学大学院理工学研究科を修了後、外資系戦略コンサルティングファーム等に勤務。
2016年:株式会社メルカリ入社。データアナリストチームの責任者を務める。
2019年:note株式会社(旧株式会社ピースオブケイク)社外顧問
2020年:メルカリ退社、株式会社Growth Camp創業
2022年:日本政府 デジタル庁にデータ分析の専門人材として参画