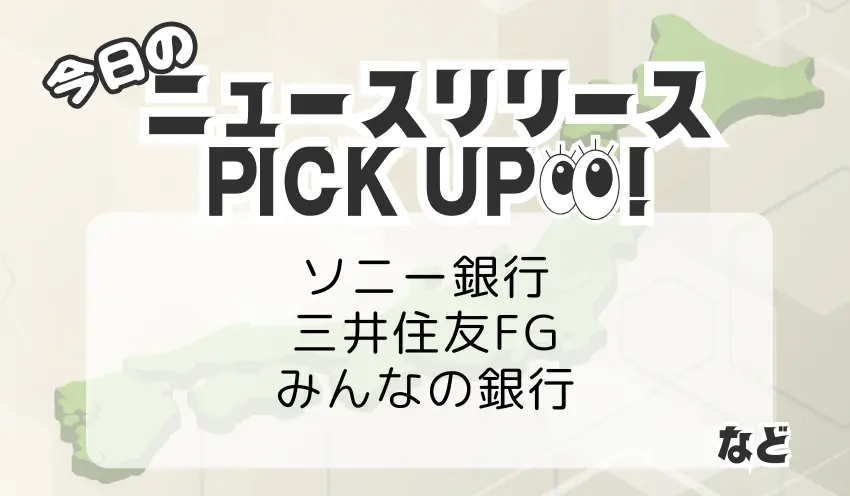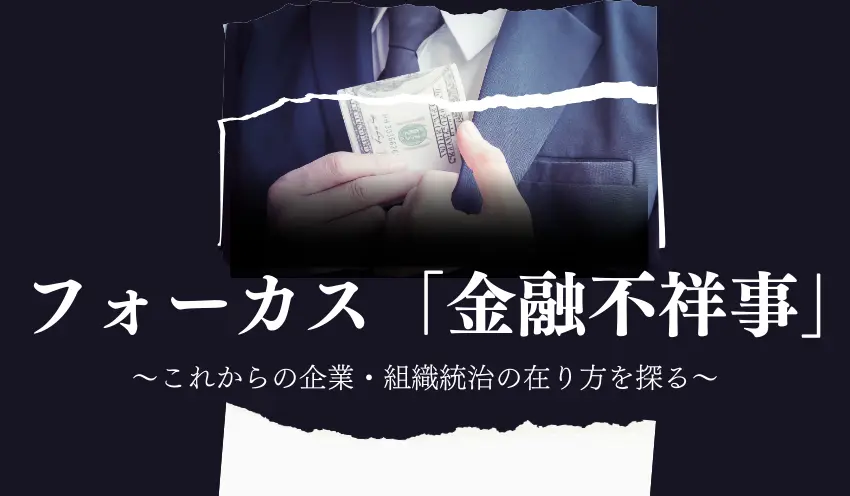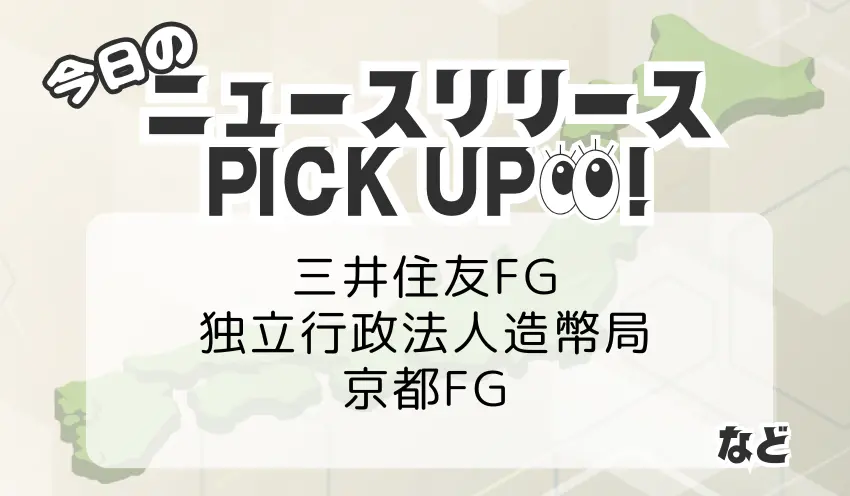生成AIを賢くつかいこなすために最新トレンドを交え解説するシリーズ「ChatGPT・生成AIとの共創世界~恐れるのではなく賢く使う!~」。Vol.26(最終回)では、 前回紹介した最新型の統合型生成AIモデル「GPT-5」を巡る論争をふまえて「人が求めるAIとは」について解説します。
■ GPT-5の反響
前回はGPT-5の紹介をしました。最新モデル「GPT-5」は、従来のGPT-4と比較して性能が向上した一方で、多くのユーザーから「応答が冷たい」「親しみがなくなった」との声が相次ぎました。背景には、OpenAIがGPT-5の設計にあたり「人間に過度に合わせすぎない」方向へチューニングしたことがあります。OpenAIは、従来モデルが見せていた“お世辞っぽさ(sycophancy)”や“過度な同意”を避け、より中立的で効率的な回答を返すことを重視しました。
しかし、ユーザーが受け止めたのは別の印象でした。回答が“形式的” ”ロボット的”になった
という声や、GPT-4oにあった魅力や温かみが失われたという意見が多く寄せられました。
これに対し、OpenAIのサム・アルトマンCEOは、SNS上で
「私たちは、GPT-5が多くの点で優れているにもかかわらず、ユーザーがGPT-4oの“温かさ”や“親しみやすさ”をどれほど大切にしていたかを確実に過小評価していた。」
とのコメントを発表。さらに「GPT-5をより温かみのあるものに改良する」とも述べ、今後のモデルで改善を図る姿勢を示しました。実際、OpenAIはユーザーの声を受けて、かつてのGPT-4oを有料プランで再び利用できるようにする措置を講じています。
この一連のやり取りは、生成AIの提供者と利用者の間にあるギャップを如実に示しています。開発側は「正確さ」「効率性」「中立性」を重視しますが、多くの人々は「安心感」「寄り添い」「会話の流れに自然さがあること」を求めています。つまり、AIに期待されているのは“正解”そのものだけではなく、その答えをどう伝えるかという“関係性”の部分なのです。
■人がAIに求めるのは“正解”よりも“納得感”
この視点を深掘りすると、私たちが日常でAIと接するときに、評価の基準が「情報の正確性」だけでないことがわかります。たとえば、検索で答えが一瞬で出ても、それがなぜそうなるのか、どのような背景に基づくのかが理解できなければ、人は納得しません。逆に、多少時間がかかっても「理由や背景をきちんと説明してくれる」方が安心できる場合もあります。
金融業界のビジネスの例で考えてみますと、
住宅ローンの返済可能額を提示するAIが「あなたの返済可能額は月◯万円です」とだけ答えるのと、「年収や生活費を踏まえると無理のない返済は◯万円前後です。将来的な金利変動を考えると、さらに余裕を持たせる選択肢もあります」と補足するのとでは、顧客の受け止め方は大きく異なります。数値は同じでも、後者の方が“納得感”を生み、顧客の安心につながるでしょう。
これは医療や教育の現場でも同様です。AIが診断情報を提示するとき、「インフルエンザの可能性があります」とだけ述べるのと、「症状から見てインフルエンザの可能性が高いですが、正確な診断には医師の検査が必要です。ご不安なら早めの受診をお勧めします」と付け加えるのでは、利用者の信頼感に大きな差が生じます。
つまり人がAIに求めるのは、「正しい答え」だけでなく、「納得できる答え」「安心できる言葉」なのです。
■ ユースケースよりも“伝え方”
現在、IT企業やAI導入中の企業は「生成AIのユースケース探索」に力を入れています。融資審査の効率化、文書作成の自動化、顧客対応チャットボットの高度化――いずれも有望な領域です。しかし、真に競争力を分けるのは「ユースケースそのもの」ではなく、その“伝え方”です。
実際、日本国内でもこの潮流は明確に表れています。LINEが導入した「LINE AIトークサジェスト」では、単に正しい返信文を提示するのではなく、直近のトーク内容に応じて返信を提案してくれます。ユーザーはそこから返信をカスタマイズすることができ、より自然で相手に伝わるコミュニケーションを実現できます。また、テレビ番組では高齢者向けに介護ロボットや見守りAIが頻繁に紹介されていますが、ここでも重視されているのは“正確な作業”以上に“安心感”や“寄り添い”といったコミュニケーションの側面です。
こうした事例は、AIが「正解を出す装置」から「関係を築く相手」へと進化しつつあることを示しています。ビジネスの現場においても同じです。顧客が知りたいのは数値やシミュレーションの結果だけではなく、「なぜその答えになるのか」「自分に合っているのか」を理解し、納得することです。AIがそこまで踏み込んで伝えられるかどうかが、顧客体験の差となり、最終的には信頼の差につながります。この差を埋めるのはAIモデル自身の進化に頼るだけでなく、人間の役割でしょう。
GPT-5を巡る“冷たい”論争は、AIが人間社会に溶け込む過程で避けて通れない問いを浮き彫りにしました。人が求めるAIとは、正確な情報を返す機械ではなく、納得感と安心感を伴い、人間同士の関係性に似た“伝え方”を備えた存在なのです。ビジネスマンにとっても、AIを単なる効率化の道具として捉えるのではなく、顧客との信頼関係を築くためのパートナーとして活用する視点が求められています。

吉山 潔 氏(よしやま きよし)
1963年生まれ
HEROZ株式会社
AIビジネスコンサルタント
外資系金融機関3社IT部門在籍。
外資系IT企業日本法人2社カントリー・マネージャー
他・外資系/国内IT企業を経て現職
 |