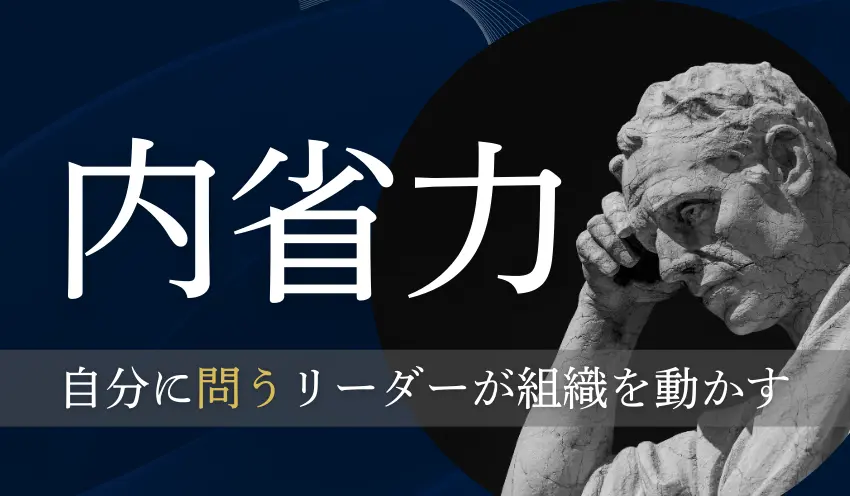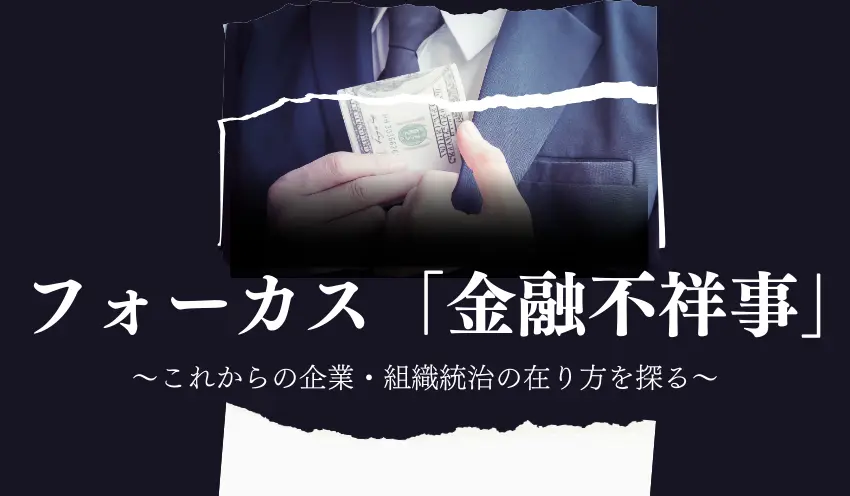
現代社会において、ますます巧妙化・複雑化する金融不祥事。金融機関経営者並びにコンプライアンス部門にはその未然防止に向けた対策が求められている。連載企画「フォーカス金融不祥事」では、金融機関の内部不祥事案などにスポットを当てて、金融・企業法務が専門で金融庁参与の山田真吾弁護士(のぞみ総合法律事務所)が、不祥事撲滅のヒント、防犯意識の啓発、これからの企業・組織統治の在り方を探る。第1回はインサイダー取引をテーマに現状分析と課題を紹介する。
1.預金取扱等金融機関による近時の不祥事の動向と本連載のテーマ
近年、金融サービスを不正に利用した詐欺等や、金融機関や金融市場に関わる不祥事や不正が相次いでいる。
大規模な銀行における貸金庫からの顧客資産の窃取事件や、大口融資先への不正融資(迂回融資、無断借名融資)、インサイダー取引、相場操縦、顧客情報の漏えい、横領等、挙げればキリがない。
本シリーズでは、いわゆる不祥事件(銀行法など、いわゆる業法において定義される法律用語)に加え、不祥事にも焦点を当て、都度都度思いつくままに解説していきたい。
なお、不祥事とは、「関係者にとって不名誉で好ましくない事柄・事件」を意味する、不祥事件を包含するより広い概念である(甘粕潔他編著『金融機関のための不祥事件対策実務必携』(金融財政事情研究会、平成29年2月)4頁)。
いわゆるコンダクトリスクという概念が浸透しつつあり、たとえ法令に違反せずとも社会規範に反する行為に対しては、世間から厳しい非難に晒されるようになった今、無視できないテーマであることから本連載においても可能な限り取り上げていきたい。
2.インサイダー取引
(1)2025事務年度金融行政方針
2025事務年度金融行政方針においては、「金融機関や金融市場の公正性が疑われるような不祥事も生じており、厳正な監督・検査や規制の改善を通じた対応が必要である。」とされ、その一例として、不公正取引規制の強化等が掲げられている(16頁)。
具体的には、証券規制違反事案への抑止力を高めるための規制強化が明記され、不公正取引等の違反事案への抑止力をより一層高めていく観点から、インサイダー取引規制の対象や、課徴金水準等の見直し、証券取引等監視委員会による効果的な検査等の実施に向けた措置について検討を進めるとされた。
こうした背景には、金融庁内部職員や、東証職員、信託銀行職員によるインサイダー取引が相次いだことがあると思われる。
(2)インサイダー取引の主体等
インサイダー取引とは、「会社関係者」「公開買付者等関係者」又は「第一次情報受領者」が、「重要事実」等を知りながら、その公表前に、当該上場会社等の売買等を行うことをいう(金融商品取引法166条、167条)。
証券代行業務を行う信託銀行の役職員でない、その他預金取扱等金融機関の役職員であっても、会社関係者等に該当しうる場合があるのはもちろんのこと、第一次情報受領者としても、インサイダー取引の主体となり得る。
また、会社関係者や公開買付者等関係者は、他人に利益を得させる目的又は損失を回避させる目的をもって、当該上場会社等の取引を推奨すれば、たとえインサイダー情報そのものを伝達せずとも取引推奨規制違反(金融商品取引法167条の2)となる。
なお、預金取扱等金融機関の役職員は「会社関係者」、「公開買付者等関係者」として、自身がインサイダー取引を行わずとも、取引を推奨することによって同規制違反となる(令和4年度金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~事例1参照)。
【取引推奨規制違反とは】
重要事実を知る会社関係者等が、他人に対して、利益を得させる、若しくは損失を回避させる目的をもって、当該事実が公表される前に、当該重要事実を伝える、(当該重要事実を伝えずとも)当該上場会社の株式の売買を推奨等すること(公開買付については、金融商品取引法167条の2第2項参照)
(出典)令和5年度 金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~
(3)課題
このように、金融商品取引法は、「会社関係者」「公開買付者等関係者」「第一次情報受領者」によるインサイダー取引を規制しているが、一方で、第二次情報受領者は、原則的にはインサイダー取引の主体とならない。
このように規制範囲を画する理由としては、第一次情報受領者は会社関係者と特別な関係を有することが多く、市場の公正性や投資者の信頼確保、会社関係者による脱法行為の防止の観点から規制が必要とされる一方で、第二次以降の情報受領者まで規制対象に含めると、処罰範囲が不明確となり、社会的混乱や過度な規制につながるおそれがあることがその理由とされるが、市場の公正・信頼を保つためには、不公正な取引を実行しようとする者への対処が欠かせない。
取引推奨規制違反は、推奨者が報酬を受領せずとも、取引を推奨するのみで成立するものではあるが、第一次情報受領者は取引推奨規制の主体とはならないため、やはり第二次情報受領者による不公正取引に対する抑止とはならない。
この問題に対し、第一次情報受領者を実質的に判断することにより本問題を解決しようとする裁判例も見られるところではあるが、令和7年6月20日付「金融庁設置法第21条の規定に基づく建議について」では、内部者取引規制における関係者の範囲について、「発行者との契約締結者などの公開買付者等関係者と同等の内部者とみなされるべき者から情報受領した者が内部者取引規制の対象外になる場合があるなど、内部者取引規制の趣旨に鑑みると不正と考えられる行為でありながら、現行制度では規制の対象とならなかった事例等を踏まえ、公開買付者等関係者の範囲等について、各関係者と同等の内部者とみなされるべき者が含まれるよう拡大する必要がある。」としており、今後の議論の動向が注目される。

山田 真吾 氏(やまだ・しんご)
のぞみ総合法律事務所
弁護士
2007年弁護士登録(弁護士法人御堂筋法律事務所入所)、
あゆの風法律事務所、財務省東海財務局(理財部金融証券検査官)、
金融庁(コンダクト企画室及びマネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室)
を経て24年9月より現職、25年4月金融庁参与(審判官)。