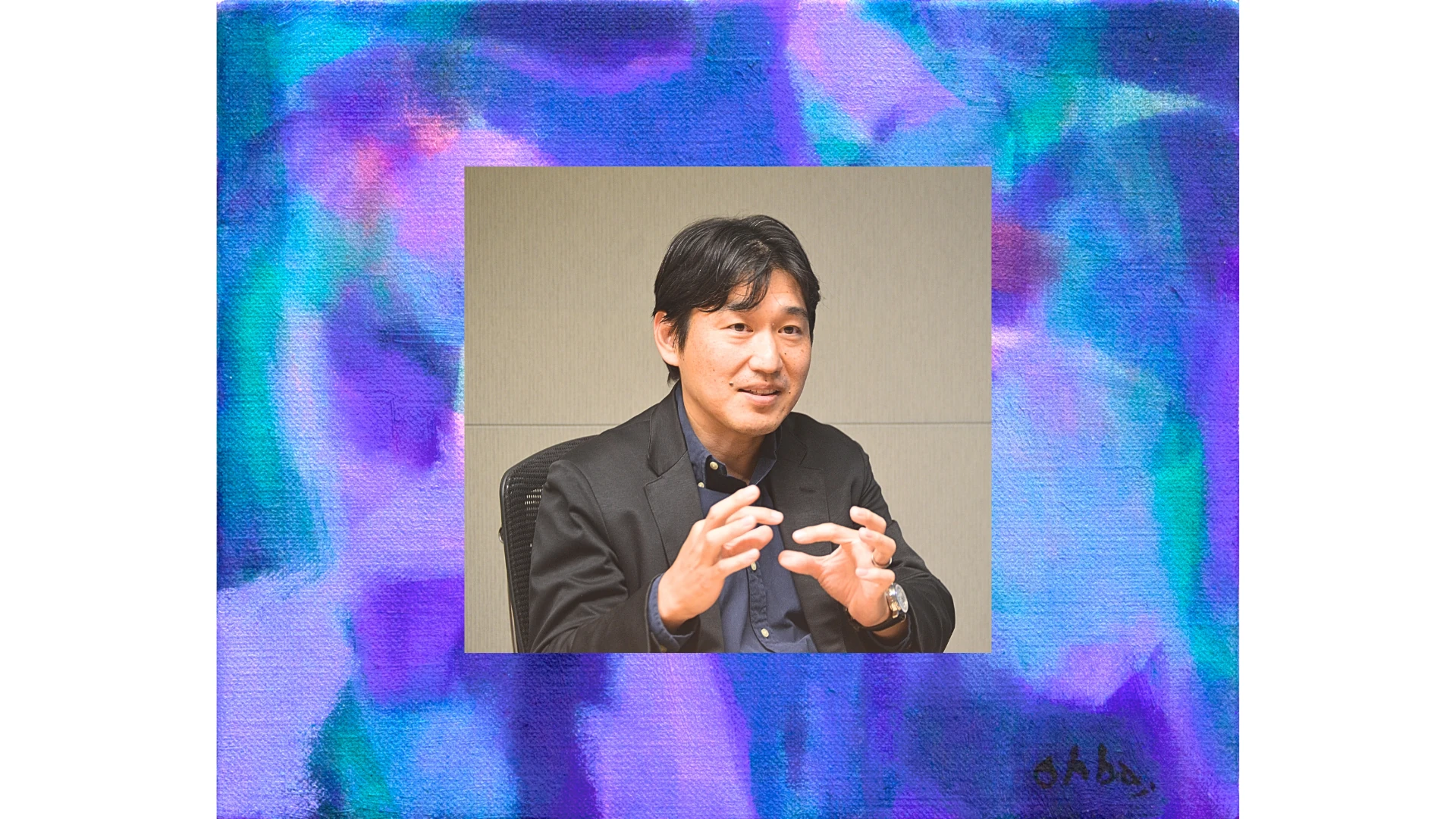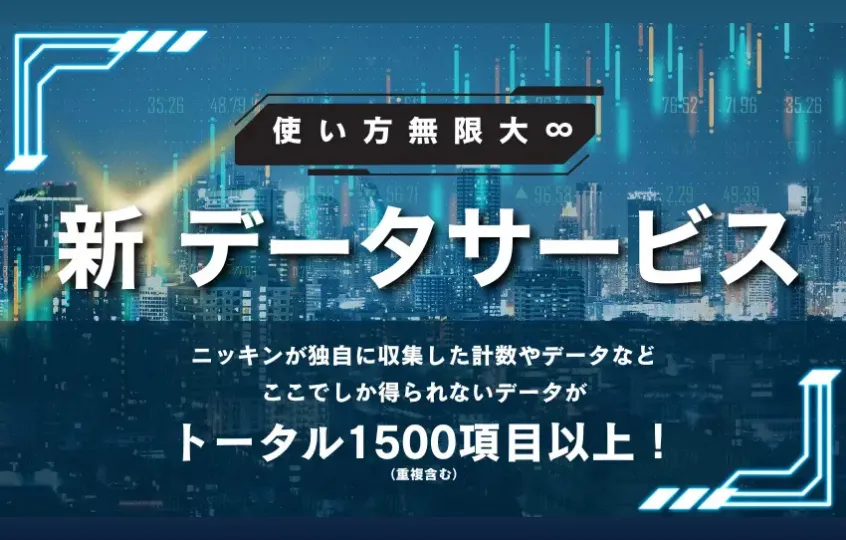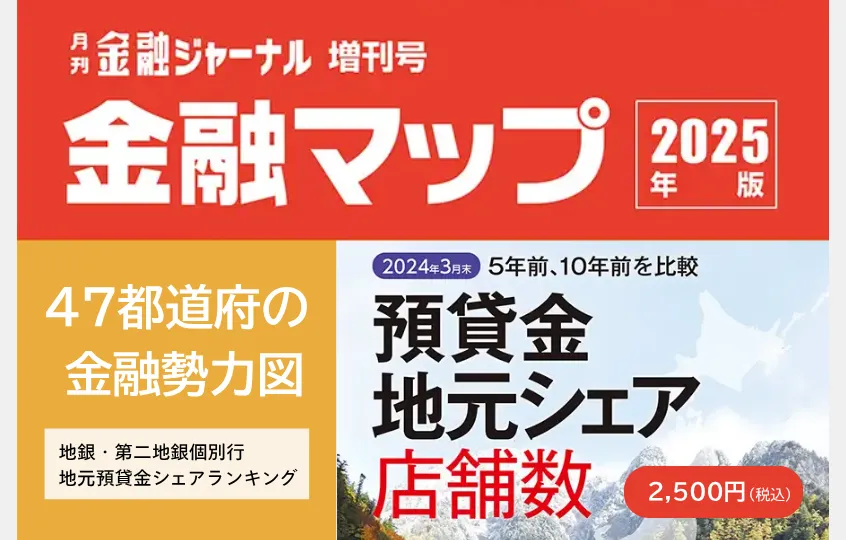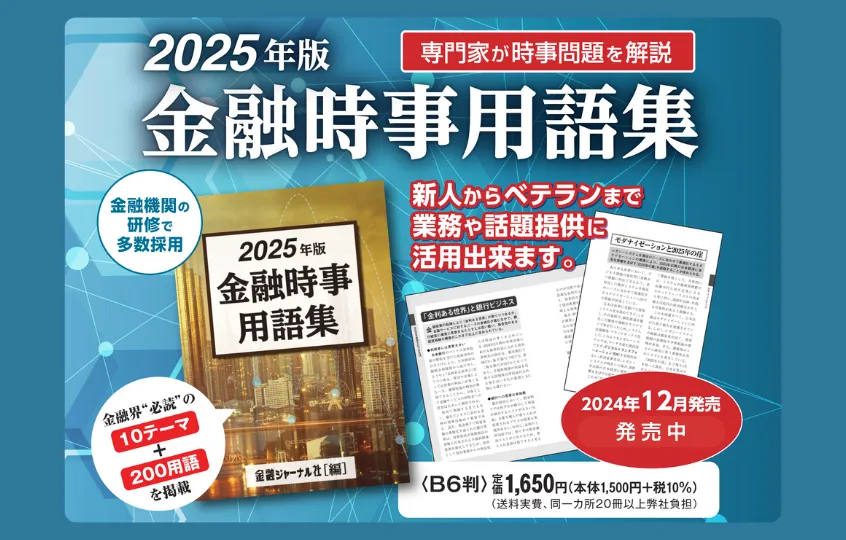保証×進化 イントラスト 家賃債務保証で急成長続く! 介護や医療、養育費などの新市場開拓
2025.06.30 19:53
イントラスト(桑原豊代表取締役)は、2006年に創業、家賃債務保証を始めとする「総合保証サービス」を展開し成長を続けている。2017年12月には、東京証券取引市場第一部(現スタンダード市場)に「その他金融業」として上場し、介護や医療、養育費などの新たな保証分野とマーケットを独自に開拓中だ。2025年3月期には105億円の売り上げを記録するなど進化を続けている。(編集部)
保証賃貸数36万件に増加
イントラストが手掛けるビジネスの大きな柱が家賃債務保証。日本ではマンションやアパート、不動産の賃貸借契約において、管理会社・オーナー(家主)が入居者に対して家賃滞納をカバーする目的で、連帯保証人を求めることが一般的だ。ただ、現代は核家族化が進み、地縁や親族などのつながりも希薄化している。民法改正で連帯保証人に対する事務手間が増えるケースも多く、保証人を確保すること自体が難しくなっている。
そして、入居者が家賃を滞納する事態になった時に、遠い親戚などが連帯保証人となっているケースだと未納分を督促しても未払いが解消されず、滞納が長期化する事例も散見される。管理会社にとって連帯保証人でも回収し切れない事態が生じることはビジネスの継続性、安定性という面でもリスクは大きい。
イントラストはここに着目し、家賃債務の保証事業を展開し、オーナーが被る滞納リスクなどを引き受けている。新規の建設や世帯数の増加などから保証ニーズは右肩上がりで増加。大手管理会社とも連携し新規入居・契約時の保証ニーズにきめ細かく対応してきたことで保証賃貸数は約36万件(2025年3月末時点)まで増加した。最近も新規契約の増加トレンドは継続しており、更新保証料なども増えたことで、家賃債務保証事業の売上高は90億円(同)まで拡大している。

審査や滞納管理を切り出して支援
家賃債務保証では審査業務、契約管理、集金代行、決済機能、滞納管理、未入金案内、調査訪問、法対応支援といった多様な業務を行うことが必要になる。イントラストではこれらの独自ノウハウを切り出し、業務支援できる体制も構築している。

大東建託グループや積水ハウスグループ、レオパレス21を含めて、ほとんどの大手管理会社ではグループ内に保証会社を保有しているが、人手が足りなかったり、多額のシステム投資費用を確保するのが難しいケースも少なくない。
イントラストはこうした保証会社のニーズに合わせて、ソリューション事業として迅速、柔軟に専門サービスを提供しており、2025年3月期の売り上げは10億円を超えている。審査業務では三菱総合研究所と共同開発した重回帰分析に基づく「家賃保証審査モデル」により債務者の潜在的な滞納リスクや、家賃滞納の長期化による法的移管リスクなどを判定できる。
また、SMS送信を活用した「未入金案内」や、審査状況や契約情報を管理する「保証事業基幹システム」の提供などのサービスは好評だ。宮崎銀行の100%子会社「ひなた保証」などの地方銀行グループの保証会社などにも業務支援を行っている。
220以上の病院・介護事業者と契約
家賃債務保証で培った知見を生かし、新分野の保証事業と市場の開拓を積極的に行っている。介護費用保証、医療費用保証、養育費保証、住宅ローン保証などに取り組んでいる。
日本ではサービス付き高齢者向け住宅や介護施設への入居時、病院への入院時には医療費の滞納リスクをカバーするために連帯保証人が求められる。イントラストはそれぞれ介護施設と利用者、病院と入院対象者の間に入り、連帯保証人を引き受けて滞納リスクを保証している。
両分野の保証事業は2014~2015年から取り組んでおり、これまでに272介護事業者、224病院と契約した。医療費用保証については、全国には約8,000の病院施設があり損害保険会社とも提携しながら「病院への導入を加速度的に増加させたい」(山田立郎・執行役員、経営企画室室長)考え。
2018年からは、養育費保証についても取り組んでいる。離婚時の離婚協議書や公正証書で合意された養育費の不払いなどの滞納リスクを保証している。ひとり親世帯の支援となることで行政側の関心は高く、宮崎市や大阪の羽曳野市、河内長野市では保証料の一部を市が負担し、契約手続きの窓口となるケースも出ている。