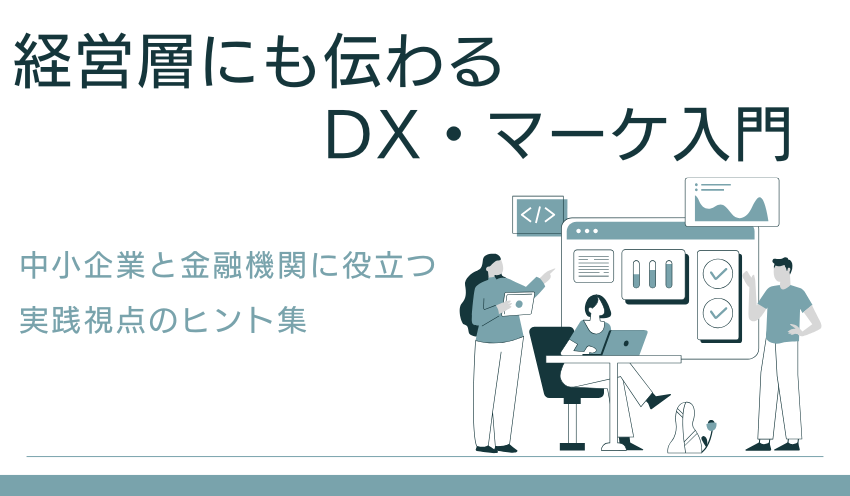「経営戦略として考える『ウェルビーイング』」の前編では、『メンタル不調で休業・退職した労働者は約1割、これからの時代に必要な「ウェルビーイング経営」とは』と題し、「ウェルビーイング(well-being)」や、労働市場における日本の課題を解説した。後編では、ポジティブ心理学の提唱者であるペンシルベニア大学心理学部のマーティン・セリグ マン教授が提唱するPREMA(パーマ)という5つの要素からウェルビーイングをひも解き、ウェルビーイング経営を実現するために必要なこと、日本企業のウェルビーイングの取り組みを紹介する。
▼PERMA(パーマ)の構成要素

P(Positive emotion/ポジティブ感情)
嬉しい、面白い、楽しい、感動、感激、感謝、希望
E(Engagement/エンゲージメント)
没頭、没入、夢中、熱中
R(Relationship/関係性)
援助、協力、意思疎通
M(Meaning/意味・意義)
人生の意義、社会貢献、利他行為、宗教
A(Accomplishment/達成)
達成、成果、自己効力感
これら5つの要素では、従業員エンゲージメントを上げるだけではなく、心をポジティブな 状態にするための取り組みや他者への感謝の気持ちの醸成など、「従業員の感情(心の状態や要因)」について幅広く語られており、ウェルビーイング経営を目指す上で何を重視すべきか理解することができます。
ウェルビーイング経営を実践するためには必要なことは、以下の2つです。
①組織課題の可視化、改善
②個人の行動変容促進のサイクルを回すこと
①組織課題の可視化・改善
ウェルビーイング経営を実践するためには、まず組織の状態、課題を把握する必要があります。従業員サーベイなどを活用し、必要な情報を揃えましょう。「人材版伊藤レポート」による人材戦略においては、①経営戦略と人材戦略の連動②As is‐To be ギャップの定量把握③企業文化への定着―の3つの視点が必要と明記されています。
ウェルビーイング経営の実現のため、例えば、社員のメンタル、フィジカル、エンゲージメント、人間関係、組織関係、仕事内容、社内外ハラスメント、などを把握することが必要です。
離職リスク、高ストレス者などを可視化し、非財務情報(ESGへの取り組み)などもカバーすることです。ウェルビーイング経営を実現するためにも、まずは組織のどこに、どのような課題があるかを可視化しましょう。こうした工夫が、対策の第一歩につながります。
可視化された課題に対して企業ができることは、研修や相談窓口の設置だけではありません。前述のPERMAよりなぞると、例えばM(Meaning/意味・意義)。ビジョンへの浸透度が低い場合、そもそものこの会社で働く意味、意義が薄れてしまいます。それに紐づき、R(Relationship/関係性)、A(Accomplishment/達成)などが連動することで、ビジョンへの浸透度が高まり、良い循環が生まれるようになります。
また、P(Positive emotion/ポジティブ感情)、E(Engagement/エンゲージメント)において、エンゲージメントが高くても、メンタル的なポジティブ感情が低いと、ワーカホリック予備軍を増やしてしまう恐れがあります。長期的な生産性と定着率の高い組織を目指す上では、心身の健康とエンゲージメントのどちらが欠けても成り立ちません。瞬間的ではなく、持続可能なエンゲージメントが高い状態が望ましいです。働き方や働く上での考え方の多様化により、ウェルビーイングの観点を取り入れた人事戦略はこれからさらに必要になってくるでしょう。
②個人の行動変容促進
コロナ禍を経て、今でこそ「メンタルヘルス」という言葉が浸透してきましたが、まだまだメンタルヘルスケアに取り組んでいる人は多くはないのではないでしょうか。
背景には、日本世界的に見て〝非常にレベルが高い〟医療制度があると言われています。日本では誰がどこにいても平等な医療を享受することが可能で、医療費の一部負担こそ求められるものの、月ごとの高額負担を軽減する「高額療養費制度」もあり、比較的安価に医療を受けることが可能です。
一方、公的医療保険が存在しないアメリカでは、非常に高額な医療費がかかってしまいます。ゆえに、極力病院に行かなくてもよいように「予防」意識が徹底されており、「病院を訪れる前段階」の医療サービスが充実しています。このように「予防」に意識が向けられているからこそ、重症化が抑制されているようです。
社員個々人にセルフケアを取り組んでもらうことは、意識の高い人であれば可能ですが、そうでない人にはなかなか難しいでしょう。そのため、会社から個人の行動変容を促すアプローチが必要です。当社では、毎週月曜日全社で集まり、マインドフルネス講座を社員向けに開催しています。リモートワークを推奨しているため、マインドフルネスだけではなくコミュニケーションの機会も兼ねています。
また、運動促進とコミュニケーションを活性化するために、音声でつなぎウォーキングをする企画なども実施。企画内にはゲーミフィケーションをもたせ、社員が楽しみながらセルフケアを行なってもらうようにしています。
行動変容には「無関心期 → 関心期 → 準備期 → 実行期 → 維持期」といった段階があるため、無関心期にどのようにアプローチするかなど、企業は工夫が必要です。
企業のウェルビーイングの取り組み事例
ここまでウェルビーイングについて説明してきましたが、日本企業による実際の取り組み事例を紹介します。
①SOMPOグループ
SOMPOビジネスサービスをはじめSOMPOグループ内の複数企業は「健康経営優良法人2021」などに選ばれています。顧客の安心・安全・健康に資する最高品質のサービスを提供して社会貢献を果たすため、社員・家族の心身の健康を重視するという「SOMPOグループ健康宣言」を発表。具体的には、健康保険組合と連携して個々の社員の健康状態に合わせた取り組みの実施、労働時間の適正化、ウェアラブル端末による健康状態のデータ収集などを行っています。
②味の素
大手食品メーカー・味の素では、ウェルビーイングの取り組みとして「人財に関するグループポリシー」を作成。これにより、従業員一人ひとりが身体と心の健康を維持・推進できる職場環境を作り出しています。
従業員の健康を支援するために全員面談を行い、1年のうち最低1度は保険スタッフや産業医との面談を実施。また、健康状態を可視化し、セルフケアの推進や休業者の職場復帰がスムーズにできるためのサポートなども積極的に行っています。
これらの取り組みにより「健康経営銘柄」に4年連続で認定されました。「健康経営銘柄」は、経済産業省と東京証券取引所が共同で定めており、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業を選定基準として選考しています。
さらに、味の素は経済産業省が実施している健康経営優良法人認定制度の「健康経営優良法人(大規模法人部門)~ホワイト500~」に認定された実績も持っています。認定企業は、従業員の心身の健康状態が悪化すれば生産性が低下し、企業の損失となることを熟慮して、さまざまな施策を講じています。
また、三井住友信託銀行では「ファイナンシャル ウェルビーイング」と称し、お金にまつわるウェルビーイング、即ち安心して健やかに生きていくために、お金についての不安をとりのぞき、お金との健全な向き合い方ができている状態になれるよう、一人ひとりのこれからを考えたトータル・コンサルティングを支援する動きを行っています。
生活や働き方と切っては切れない関係をもつウェルビーイングという概は、企業やサービスに多く取り込まれています。
企業価値の向上に欠かせない組織と個人のあり方。日本企業にはウェルビーイング経営が今まさに求められています。従業員のウェルビーイング度が高いと、企業は大きなメリットを得られます。

株式会社ラフール 会社HP
ウェルビーイング経営を実現する組織改善ツール「ラフールサーベイ」