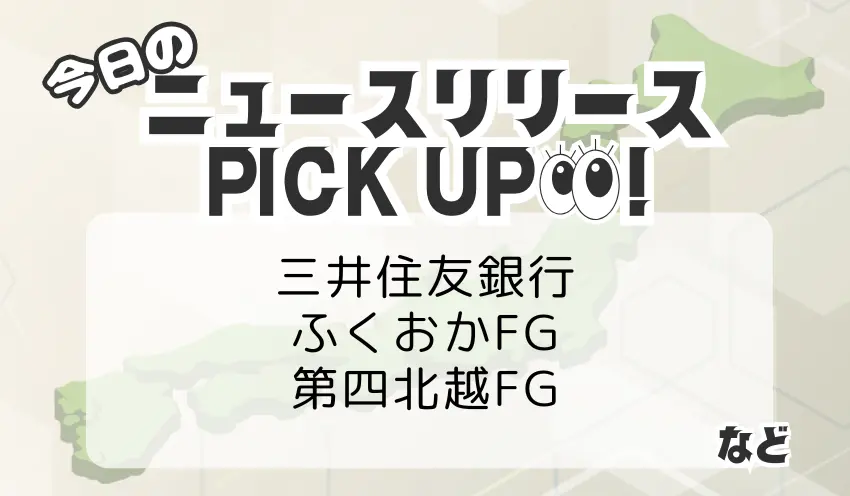さまざまな取引先支援に取り組む金融機関。営業担当者は、取引先の情報を少しでも多く入手し、事業拡大や経営基盤強化を支援している。シリーズ「はじめての製造業~若手バンカーに贈る製造業基礎知識~」は、特許文献をはじめ世界の技術情報を調査分析し、知財・技術情報の総合ソリューションを提供する日本アイアールが製造業の置かれている課題をテーマに営業担当者の取引先に対する悩み解決の糸口を提供する。
バンカーである皆さんが異業種であるクライアントを担当されるときに必要となる業界研究。ところ変われば、使う言葉も使う道具も見ている世界も変わるので、全く勝手が違って戸惑われることもあるでしょう。本連載では、皆さんの業界研究に役立つ、「製造業」関連の知識を提供します。
クラウドによるデータ管理でリモートワークが可能になったり、顧客データをはじめとするビッグデータをAIで分析したり、RPA(Robotic Process Automation: ロボットによる業務自動化)により単純なルーチンワークを自動化したり……。金融業界に生きる皆さんの間で、業務にDX(Digital Transformation:デジタルへの変容)が日々浸透していることを実感したり、実際にそれを推進する立場の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
皆さんが顧客とする製造業でも、DXは大きな課題です。
経済産業省によると、DXの定義は「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」(デジタルガバナンス・コード2.0)ということです。要は〝日々の業務にデジタル技術を取り入れて効率化しましょう〟という話です。新聞、雑誌などでも日常的に報道されていますので、言葉をご存知の方は多いと思います。
しかし、経済産業省が「DXレポート」を公開した2018年から既に5年。このレポートの中で、「老朽化・複雑化・ブラックボックス化した既存システムがDXを本格的に推進する際の妨げになること」を象徴的に示した「2025年の崖」まであと2年になった今も、残念ながら企業のDXへの取り組みは十分とは言えないのが現状です。
~2025年の崖~
既存システムが複雑化・ブラックボックス化しているにもかかわらず、現場サイドの抵抗が大きいことなどを理由に問題が解決できないと、DXが実現できないだけでなく、2025年以降、最大12兆円/年の経済損失が生じる可能性があるとする経済産業省の指摘。 例えば、データをExcelⓇなどの表計算ソフトで担当者のPCにてローカル管理するなどの慣習がすでにあれば、それをクラウド管理に変えて社内全員で共有するなどの方法に切り替えることは、担当者個人からの反発を招く可能性もある。

製造業の世界ではスピーディーな取引が重視されるため、企業間の受発注情報や技術情報の国際取引をデジタルで行うのが常識となっています。グローバルな大企業は、DXを確実に進めないと世界での競争に負けて存続できないため、積極的に取り組んでいます。ところがヒト・モノ・カネのショートしがちな中小企業にとっては、DXに注力することがまだまだ難しい状況と言わざるを得ません。
DXのゴールには、サプライチェーン全体をDXで最適化することも含まれます。
国際取引のない中小企業であったとしても、発注元の大企業からの発注書、図面など、すべての情報がデジタル化されるようになれば、いやおうなしにDX対策に着手しなければならないのです。
次回は、製造業が具体的にどのようにDXに着手しているのかをご紹介します。

・技術者教育研究所HP: https://engineer-education.com/
・日本アイアール企業HP: https://nihon-ir.jp/