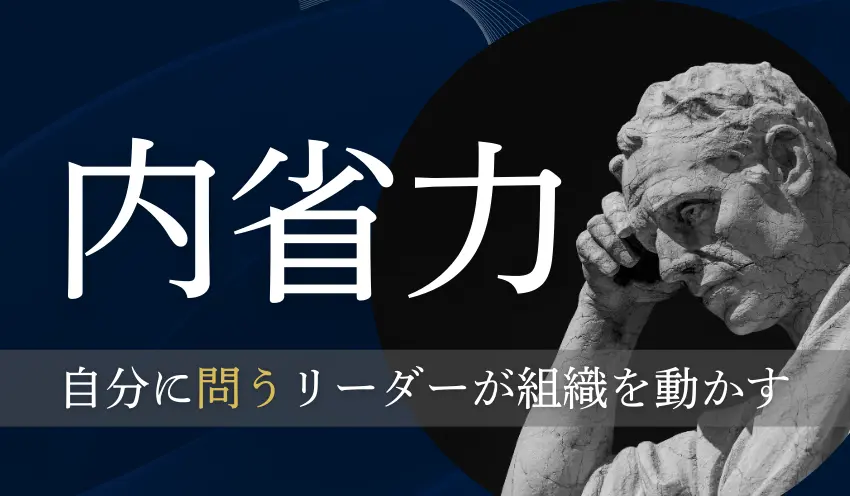「値上げ」――。新聞やテレビでは、毎日のように身の回りのモノ・サービスの価格改定が報じられています。日本では長らくデフレが続き、「物価は上がらない」「価格は昨日と同じ」という社会全体での共通認識が形成されてきました。しかし、ここ数カ月でその“常識”は大きく変わりつつあります。
私たち生活者には、「消費者」としての顔もあれば、「(個人)投資家」としての顔もあります。今、生活者の多くは「消費者」として、スーパーマーケットやガソリンスタンドなどで物価上昇を体感し、家計への影響を実感しています。しかし、その一方で「投資家」として物価上昇に向き合う必要性を感じている方はまだ少ないのではないでしょうか。本来、物価は個人の資産価値に大きく影響を及ぼす重要な要素です。しかし、日本では物価が長期間にわたって安定していたことから、資産形成における物価の重要性が忘れられているように思います。物価が上昇基調に転じれば、これまでの資産形成の手法を見直す必要が出てくる大きな転換点となります。
本連載「資産形成の大転換点」は、インフレ懸念が高まる今、金融機関の皆さまが顧客の資産をお守りする上で参考にしていただけるよう、東京海上アセットマネジメントの執筆陣が物価変動と資産形成について解説していきます。
■不確実性が高まる今こそ物価の重要性に着目
世界的にインフレが進行しており、2022年7月時点の消費者物価指数の前年同月比は、経済協力開発機構(OECD)加盟国で+10.2%、米国で+8.5%となっています。日本はそれより低い水準ではあるものの+2.6%まで上昇しています(図表参照)。日本で物価上昇の兆しが見られる点については、円安の急伸、日本銀行の超金融緩和継続、政府の積極財政のほか、生産年齢人口の減少による賃金の上昇、地政学リスクの顕在化など様々な要因が挙げられます。今後、本連載で解説していきますが、歴史を振り返るとインフレ率は「上昇」「低下」「安定」のサイクルを数十年単位で繰り返してきたことが分かります。現在の日本の物価上昇が一時的なものなのか持続的なものなのかは注視すべき点といえます。

インフレが資産価値に与える影響についても見ていきましょう。仮にインフレ率が年2%で継続した場合、現在の1000万円の実質価値は20年後に約673万円になってしまいます。これは資産の「買うチカラ(購買力)」が3割以上低下することを意味しています。資産を預金で保有している場合、預金金利がインフレ率を上回る状態であれば購買力は低下しませんが、インフレ率が預金金利を上回る状態が続くと購買力は低下してしまいます。
混乱の時代を経験してきた欧州の投資家が長期間にわたって行ってきたように、資産形成の本質は購買力の維持・向上にあります。本連載では、不確実性が高まる今だからこそ、改めて物価の重要性に着目していきます。
(このコラムは「ニッキン投信情報」に掲載されたものを再編集したものです)