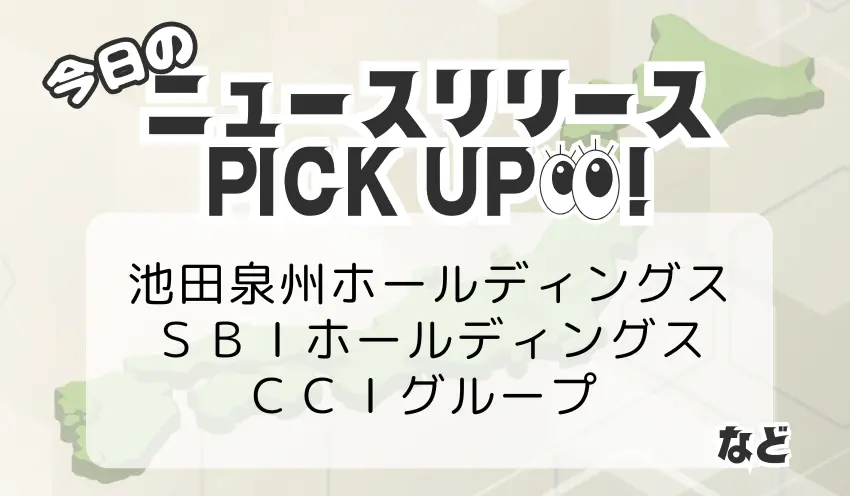日本人と米国人との投資行動や金融活動の違いには、金融制度の違いや税制などの要因によるものもあるが、日本語と英語の違いによるものもあるのではないだろうか。文法や語彙の違いはもちろん、言葉の背後にある現象や人間関係の認識方法そのものの違いもある。日本語化した英語が本来の意味と異なることもあるし、同じ単語も時の流れや文脈によりその意味が変化することもある。本連載「英語で考える金融」では、英語にも日本語にも通じていて、金融分野で活躍しているパトリック・コノリーさん(Patrick E. Connolly)に、普通の米国人が金融に関する用語をどう受け止め、どう日本と異なる面があるのかを聞く。
リターンを期待しない支出はinvestmentとは言わない
YO:「投資」は、英語でinvestmentですが、日本語と英語とでニュアンスの違いがあるのですか?
PEC:「投資」とinvestmentとは、表面的には似ていますが、かなり違うニュアンスがあると思います。「投資」は、漢字でみると、「資本を投下する」、つまり「お金を手放す」ことを焦点にして考えていることを意味しています。一方、investは、もともと祭服を着せるという意味が転じて、現在でも人に権威を与える、という意味を持っています。ベストは胴着という意味で日本語でも使われていますが、investは司教が王様に王冠をかぶせるような語感があります。権限を委ねるわけですから、「お金を手放す」よりも、「お金を託す」のです。つまり、見返り(リターン)を期待してお金を人や投資先に充当するのがinvestmentです。リターンを期待しない支出はinvestmentとは言いません。
YO:確かに日本語ではreturnを「収益」と訳していますが、「戻ってくる」ものですから「見返り」ですね。日本語では、お金を貸すのは「投資」とは言いませんが、英語のinvestmentはお金を貸すことも含むのですか。
お金を貸すのもinvestment
PEC:基本的に見返りを期待してお金を支出することがinvestmentになりますので、見返りを期待するのなら、お金を貸すのもinvestmentに入ります。英語ではinvest in education「教育にお金をかける」ともいいますので、investは将来の見返りに期待した支出一般をいうとも言えるでしょう。日本には「講」や「無尽」という仕組みがあって、「お金を貸す」という場合には、伝統的には、必ずしも見返りを期待せず、元本が返ってくればよい、という考えが強かったのかも知れません。困ったときにそうした相互援助の仕組みからお金を借り、困難を克服したらお金を返す、その時に貸し手に支払う金利は、お金を借りたことに対するお礼のようなものと認識されていたのかもしれないと思います。しかし、現代社会では、お金を貸すのは慈善事業ではありません。お金を貸す人はリターンを期待して貸すという判断をします。リターンを期待する、ということは、別の言葉でいえば、リスクを取る、ということです。お金を貸したら、元本が約束通り返ってこないかもしれません。それがリスクで、そのリスクを取ったことに対する報酬としてリターンがあるのです。預金に預けたり国債を買ったりすると確定的な金利が得られますが、investmentは、それに上乗せしたリターンがあることを前提としています。
YO:「講」などについてまで、よくご存じですね! 確かに「金融」という日本語は「お金が融ける」という漢字で、資金の流通をイメージしているので、元本が返ってくるということを重要だと考えていますが、その場合、金利は決まったものと考えるような傾向があるかも知れませんね。リターンはリスクを取ることへの報酬だ、という考えが日本語には必ずしも定着していないかもしれません。
PEC:リスクとは、望ましくないことが起こる「確率」(probability)です。危険(danger)とは違います。一方、リターンも良いことが起こる確率で、事前に確定しているものではありません。リターンがリスクを上回るように考えるのが健全な投資です。リスクを避けることと管理することとは違います。日本ではリスクはゼロが良い、と言う人がいますが、それはリターンも考えないことと同じです。investmentとは、リターンとリスクの両方を天秤にかけて判断し、自分の財産を管理する行為ですので、「投資」をそう考えるとよいのではないでしょうか。
(このコラムは「ニッキン投信情報」に掲載されたものを再編集したものです)