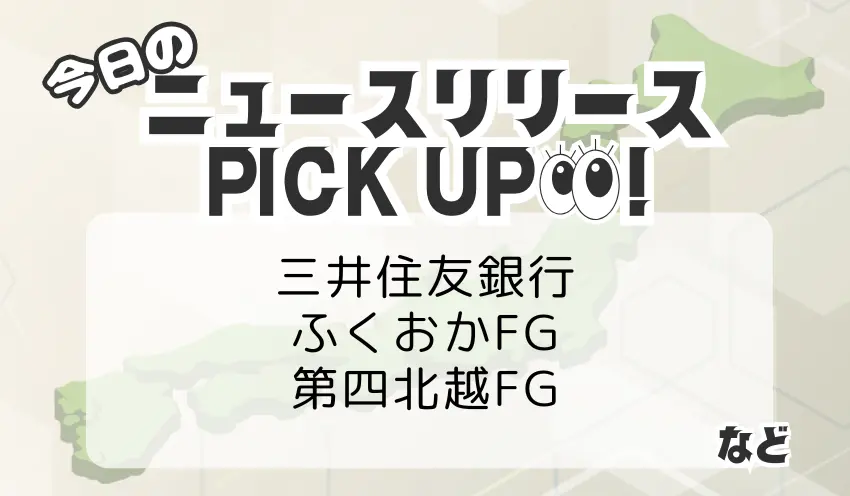持続可能な地域社会の発展に向け、積極的な金融仲介機能の発揮を求められる地域金融機関。取引先の維持・発展に向けた各種支援にも力を入れる。全国の地域金融機関と連携しコンサルティングサービスを展開するみらいコンサルティンググループがコンサルティングの生の現場からすぐに使えるヒント・事例を届ける。初回は、辻口賢執行役員札幌支社長が、2回にわたってシリーズ「コンサルティングのヒント集」を紹介する。
■伴走型コンサルを掲げる金融機関
4月以降、全国の金融機関では続々と中期事業計画が発表されています。従来の銀行業からの脱却を目指すビジョンが数多く打ち出されており、なかでも、地域や企業に寄り添った「伴走型のコンサルティング事業」を掲げるところが多く見受けられます。
■伴走型コンサルを成功させる3つのポイント
伴走型コンサルティングを成功させるためには、対話の定義・ストーリー・本気度のツボを押さえることが大切です。そのためのポイントを以下の3点にまとめていますが、今回は「会話・対話・議論の区分」に的を絞って説明します。
<Point>
|1| 会話・対話・議論を区分する
|2| 言語化 ⇒ 見える化 ⇒ 仕組化 ウェイトはどこか?
|3| 本気度を高める3つのアプローチ

■伴走支援は経営者との〝対話〟から
その前に、そもそもの話ですが、伴走型コンサルティングと一般的なスポット型コンサルティングの違いを簡単にまとめました。コンサルティングファームによって定義は若干異なると思いますが、伴走型コンサルティングの特徴としては長期的なお付き合いを前提とし、安定収益につながる、という点があげられます。まず、入り口として、会話と対話と議論を区分することが大切です。普段、経営者と接する担当の方が、この点を明確に区分できているのか改めて確認してください。何気ない日常の「会話」も重要ですが、その先に進むためには、一つ上のフェーズ、いわゆる「対話」を通じて合意形成する必要があります。
下図は、当社が考えるコンサルティングの3ステップ図です。コンサルティングを進めるにあたって、対話は解決へ至るまでの重要な役割を担っています。お客さまの時間的猶予などで状況が異なるケースはありますが、経営者とじっくりと対話できる能力を磨くことはコンサルティングを行う上で欠かせないものです。

なぜ「対話」が伴走につながるのか。前提条件を説明します。まず、経営者は基本的に問題解決のプロだということです。ですので、議論、いわゆる問題解決モードだとハレーションが生じ、本質的な議論が前に進まなくなる可能性があります。そして、人は本音を語り本心に気づくと本気になるということです。そのためには対話を通じ、互いの感情や認識を共有しあうことで同じ船に乗る仲間であると認識していただくことが大切です。こうしたコミュニケーション手法はコンサルティングスタイルによっても異なります。伴走型は対話が中心です。一方でスポット型は議論が中心で正解を探し求めていくことが大前提となります。

経営者のありたい未来を共創する 未来セッション
パンフレットはこちら