
SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境・社会・ガバナンス)のキーワードで、自然環境や生態系保護の重要性は広く認識される。投資や金融にもこうした観点が求められる。新シリーズ「いきものコミュニケーション」はカエルの研究で博士号を取得し、14万人以上のヒトの会話を分析して、生物のコミュニケーション分析事業も行う”音”の専門家である筆者が、生物とコミュニケーションについて解説する。第1回テーマは「生物多様性」である。
生物多様性とは
いきもののコミュニケーションに関する解説シリーズを始めるにあたり、まず重要なキーワードである生物多様性の話題から取り上げます。
「生物多様性」という語は聞いたことがありますか? 内閣府が1,500人以上に対して実施した世論調査[参考文献1]によると、意味を知っている回答者が約3割で、約4割の回答者が言葉は聞いたことがあるが意味は知らず、残りの3割は聞いたこともないと回答しました。この言葉はあまりしられていないようです。一方で、約8割の回答者は「自然に関心がある」と回答しているので、人々が自然に無関心だというわけではなさそうです。
地球上に見つかっているだけで175万種[2]もいる生物が、それぞれ食べたり食べられたり、お互いに利用し合ったり助け合ったりしながら生きていることを「生物多様性」と呼びます[3]。とくに多様な種類の生き物がいて、それらがお互いに依存しているということが重要です。たとえば、1種類の杉だけが大量に植えられている森は、植物は多くあるが、生物多様性が高いとは言えないわけです。
生物多様性の種類
生物多様性の国際条約では、生物多様性には3つのレベルがあると定義されています。イメージしやすい順番に説明していきます。
1.種の多様性
これが一番わかりやすいでしょう。たくさんの種類の生き物がいるとき、生物多様性が高いと言えます。色々な種が生き残れるということは、それらがうまく依存関係を作って個体数を維持しているといえます。
2.生態系の多様性
より大きな視点でみると、たとえある場所に多様な種がいたとしても、例えば山しかなければ、多様性があるとはいえません。草原や川、海など多くの種類の環境があって、それぞれそこに適した種がいるほど、全体としての生物多様性は高くなります。
3.遺伝子の多様性
今度は小さな視点で見てみましょう。ある環境にたくさんの個体がいたとします。例えば山の中にカブトムシが大量にいたとします。このとき、カブトムシたちの遺伝子が似ていると、仮に数がいたとしても遺伝子の観点では多様性が高いとは言えません。逆に、体のサイズや色など、さまざまなバリエーションが見られるような同じ種でも遺伝子の種類が多いとき、多様性が高いといえます。
これらをまとめると、この3つのレベル全てで生物多様性が高いということは、以下の状態にあると言えます。
- さまざまな種類の自然環境があって(生態系の多様性)
- それぞれの環境に多くの種類の生物が住んでいて(種の多様性)
- 生物それぞれに個性がある(遺伝子の多様性)
生物多様性が高いことで得られる恩恵
生物多様性が高いと、私たちはたくさんの恩恵を受けられます。たとえば、さまざまな食料が手に入ったり、木材や燃料などが手に入ります。それ以外にも、木の根が地中深くまで広がることで土砂崩れが防がれたり、自然の中を散歩したり風景を楽しめるというメリットもあります。こうした恩恵はまとめて「生態系サービス」と呼ばれます。
とくに、医薬品の多くが生物に由来していることも重要です。現在でも微生物を研究することで多くの医薬品が作られています。
生物多様性はなぜ守る必要があるのか?
さまざまな種がお互いに依存しながら生きているため、その依存関係はとても複雑です。そのため、人間に有用な生物がいたとしても、それだけを保護してしまうと依存関係が崩れて問題が起こってしまいます。
たとえば、昔から人々に恐れられていたオオカミが絶滅することで、シカが増えすぎました。これによって、次はシカが植物を食べすぎることで植物の多様性が危機に瀕しています。たとえば、オオカミを再び日本に導入する是非が研究者の間で議論されています[4]。
このように、依存関係が複雑なために、どの種を残してどの種を駆除するという判断をするのがほとんど不可能です。したがって、今の生物多様性の状態をできるだけ保つ必要があるのです。
参考文献
[1]内閣府政府広報室 “生物多様性に関する世論調査”, 2022.
https://survey.gov-online.go.jp/hutai/r04/r04-seibutsutayousei/gairyaku.pdf
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h25/html/hj13020201.html
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/about.html
[4]立命館大学報道プレスリリース “生態系再生のために日本の野山にオオカミを放すべきか?”, 2023.
https://www.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=577620&f=.pdf
ハイラブル株式会社
社長 水本 武志 氏(ミズモト タケシ)
2006年大阪府立工業高等専門学校卒、2013年京都大学大学院 情報学研究科 知能情報学専攻 博士後期課程修了、 博士(情報学)。大学院在席中に日本学術振興会特別研究員、LAAS-CNRS (仏) 滞在。 2013年4月、ホンダ・リサーチ・インスティチュート・ジャパンでリサーチャとして従事。 2016年11月ハイラブル設立、現職。
【関連記事】
シリーズ「会議が見える〜音環境分析でコミュニケーションを豊かにする〜」




-国産牛乳「危機」から一転-7-1024x579.webp)
-国産牛乳「危機」から一転-6-1024x579.webp)
-国産牛乳「危機」から一転-8-1024x579.webp)

-国産牛乳「危機」から一転-5.webp)
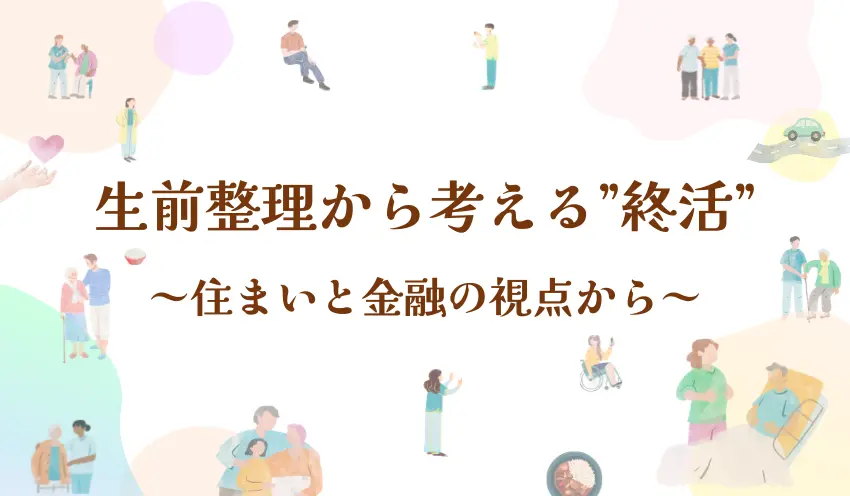
-国産牛乳「危機」から一転-2.webp)