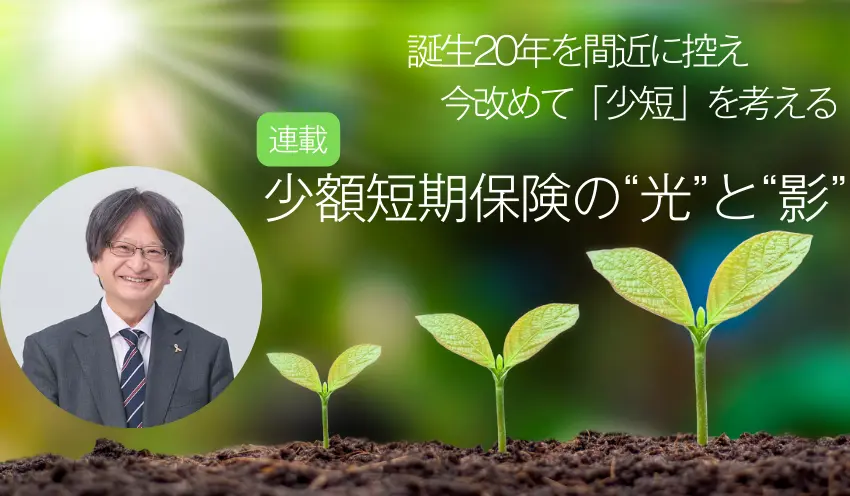
急成長を遂げた少額短期保険。国民の10人にひとりが利用する保険制度になった一方で、経営破綻や行政処分、成長スピードの鈍化など、新たな課題も見えてきた。少額短期保険普及の原動力、これからの可能性、業界が抱える様々な課題などを「光と影」というテーマで解き明かす全12回シリーズ「誕生20年を間近に控え 今改めて『少短』を考える 少額短期保険の“光”と“影”」の1回目。
1.少額短期保険とは何か
「少額短期保険」は、2006年に誕生した新しい保険制度。「少短」の名前のとおり、少額の保障を短期間に限定して提供する仕組みで、生命保険や損害保険に比べて小回りがきくことが特徴だ。
詳細は「保険業法」「政令」「省令」などで、細かく規定されている。例えば、保険金の上限は死亡保険で300万円、医療保険は80万円、損害系は1,000万円など。保険期間は1分野と3分野は1年以内、2分野は2年以内と定められている。保険種類も限定されており積立型や終身型の保険は取り扱いができない。
さらに事業者は「50億規制」と呼ばれる制約に縛られ、年間の収入保険料が50億円を超えることができない。中小規模の事業者でも市場に参入できるチャンスが生まれたとも言えるが「中小規模であり続けなくてはならない」という観点は賛否が分かれる。
いずれにしても少短は、「大手がカバーしきれないニッチな領域を支える仕組み」としてデザインされた新しい保険といえる。
2.少短業界の現状
誕生から19年を経た少短は、すでに一つの業界としての存在感を持っている。事業者数は100社を突破、加入者数も1,000万人規模に達した。収入保険料も着実に積み上がり、業界全体で年間1,500億円規模に迫るまでに成長している。
参入企業を紐解いてみると、共済からの移行組に加え、新規参入も急増している。特に商社、流通、旅行、不動産など大手異業種からの参入が目を惹く。また近年は大手保険会社が子会社として参入するケースも多い。
募集チャンネルも多岐にわたり、生損保代理店が少短を併売するだけでなく、不動産会社、ペットショップなどが、物件仲介や生体販売に併せて保険を案内するスタイルも浸透してきた。基本的に販売拠点を持たない事業者が多いので、必然的にインターネットを介した販売チャネルが主流でもある。
私が少短協会の初代専務理事に就任した際、少短業界の概況を「家財系」「生保系」「ペット系」「費用系」に分類する形が確立した。ちなみに2024年度の収入保険料ベースでは、家財系:62%、生保系:13%、ペット系:15%、費用系:10%となっている。
ペット保険を独立したカテゴリーにしたのは、この比率から頷けることと思う。少短の代表格といえる存在で、飼い主にとっては動物医療費の高額化に対応できる重要な選択肢となっている。こうした「生活者に寄り添う商品」が支持され、業界全体を押し上げてきた。
3.無認可共済という社会問題
少短が制度化される以前、日本には「無認可共済」と呼ばれるグレーゾーンの仕組みが数多く存在していた。共済は本来、組合員の相互扶助を目的にした非営利の仕組みだが、「共済」の解釈が拡大し、実態としては保険と同じような商品を扱いながら、金融庁の監督を受けずに営業している団体が乱立していた。
その象徴的な事件が「オレンジ共済問題」。高利回りをうたって資金を集めながら、実際には選挙資金などに流用して多くの契約者が損失を被った事例。こうした問題を契機に、金融審議会では「消費者保護の観点から、無認可共済を放置すべきではない」との議論が高まった。結果として、一定の基準を満たす小規模な事業者に、合法的な活動の場を与えるために創設されたのが「少額短期保険制度」だった。
なお、本来「無認可共済」という表現は適切ではなく、正しくは「根拠法のない共済」と呼ぶべきだ。法律が整備され少短会社に移行した多くの事業者は、高い志と健全な事業運営をしており、それ自体「違法営業」でも「違反行為」でもなかったからだ。一部の事業者のため「無認可共済」という言葉が市民権を得てしまったことは私としては残念である。
4.誕生の舞台裏
制度誕生の裏側では、既存の生保・損保業界と金融庁の間で激しい綱引きがあった。最大の焦点は「引受限度額」。大手保険会社からすると、少短が高額保障を扱うようになれば、不要な競合が発生する。そのため「保障額は低く抑えるべきだ」という強い意見が出され、結果として前述のように上限額が設定された。
ところがこの「死亡保険300万円」「医療保険80万円」の算定根拠は必ずしも明確には示されていない。2006年11月に保険毎日新聞社から出版された「保険業法Q&A:少額短期保険業のポイント」(保井俊之編著・豊田真由子,白藤文祐著)の中で触れられているが、死亡保険は「葬儀費用」医療保険は「自己負担額」が参考にされたという。経緯を知らない人は死亡500万円、医療100万円などキリの良い金額でないことを不思議に思うだろう。
また、既に活動していた無認可共済団体への経過措置も課題となった。新制度が一律に導入されれば、本則以上の保障を受けている既存契約者が路頭に迷う。そのため一定期間の猶予が与えられ、順次本則への移行が図られた。この「経過措置」は少短を語る上で欠かせない論点であり、結果的に経過措置が17年続いたことは記憶に新しい。この点は別な機会に掘り下げたいと思う。
5.少短が切り拓いたもの
誕生から19年。少短は今や無視できない規模へと成長し、国民にとって新たな保険の選択肢として定着した。大規模なリスクを支えることはできないものの、日常生活のちょっとした不安に寄り添う存在として評価されている。ペットや自転車、スマートフォンや熱中症といった身近なテーマを切り口に、保険がぐっと生活者に近い存在になったことは、少短の大きな功績といえる。
このシリーズ投稿のトップ画面は、木漏れ陽の「光」の中ですくすく育つ3本の新芽のデザイン。新芽が大きくなれば若葉の下に日影もできてくる。私たちはその「影」の部分にも目配りをしながら、しっかりと成長を見守りたいと思う。若葉が大樹になる日を願って。
五十嵐 正明(いがらし まさあき)氏
東京都出身、立教大学卒。外資・国内の生保・損保を経て、2008年 ブロードマインド少短を創業。
2011年 少短協会専務理事に就任。2016年 SBIグループに参画、SBI日本少短代表取締役に就任。
2019年 SBI損保代表取締役に就任。2020年よりSBIインシュアランスグループ取締役も兼任。
2024年 SBI損保社長を退任し「オフィスエム」を創業。
現在は複数社の顧問、アドバイザー、パートナーなども務める。
著書に「保険業界のゲームチェンジャー ミニ保険を作った7人の侍たち」。
Facebook:https://www.facebook.com/iggy50/
Instagram:https://www.instagram.com/office.m_consulting/
Twitter(X):https://x.com/iggy_officem
YouTubeチャンネル:「業績アップTV」https://youtube.com/channel/UCjA3lzwiN15tvA2yftqSVmg?si=roepgDoyqO8KWFZ0
note:「Last One Mile Club by Office M」 https://note.com/iggy555






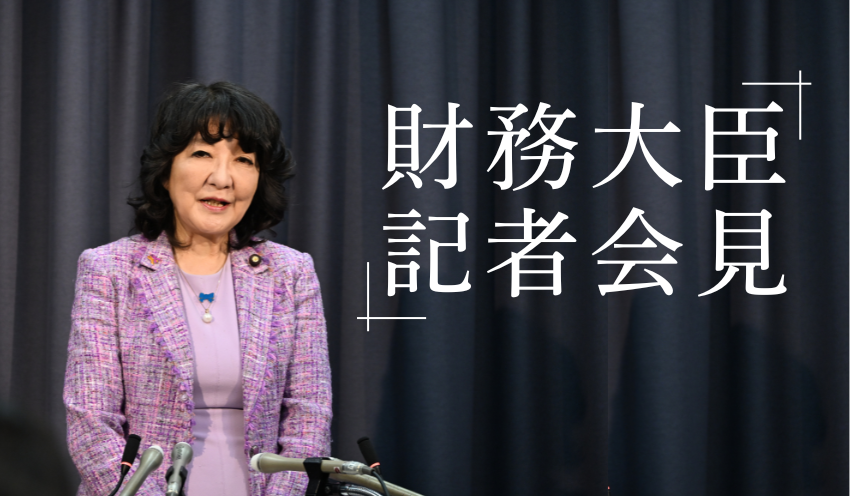

-国産牛乳「危機」から一転-9.webp)