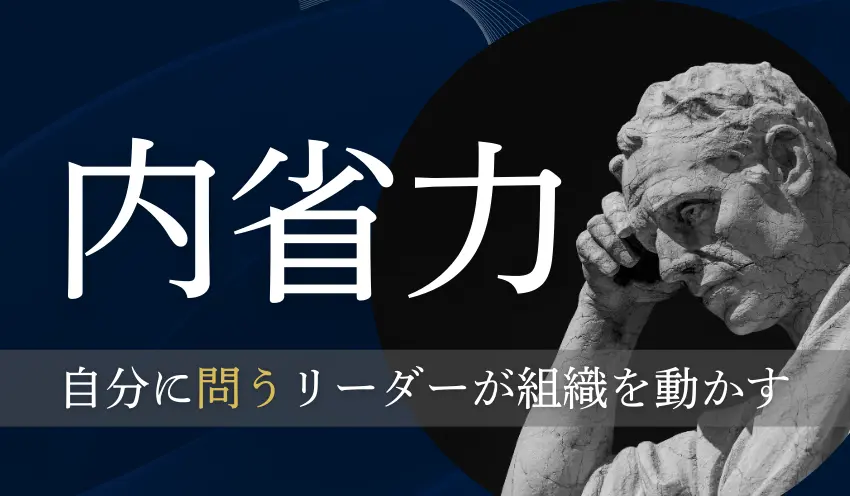予測不能な自然災害や突発的な危機——-いざというときの対応は万全だろうか。地域経済を担う金融機関では取引先のBCP(事業継続計画)策定を進めるため啓発セミナーや策定支援に力を入れている。しかし、スキル・人手・時間がハードルとなり策定が思うように進んでいない状況。シリーズ「中小企業のためのBCP入門~未来の大災害に備え、御社を守る盾を!~」では、BCPの基礎から実践までを、緊急連絡を支援する安否確認システム「安否確認サービス2」を開発販売し、トヨクモ防災タイムズで企業防災やBCP、リスクマネジメントの最新情報を発信するトヨクモが取材やシステム導入支援の経験をもとにBCPやリスクマネジメントの基礎を分かりやすく解説。
もしも明日、あなたの会社が、地震、洪水、あるいはパンデミックに見舞われたら…? オフィスや工場は無事でしょうか?従業員は安全でしょうか?取引先との連絡は取れるでしょうか?
「まさか、うちには関係ない」 そう思っていませんか?
中小企業庁の調査によると、実際にBCP(事業継続計画)を策定している中小企業は、わずか1割程度と言われています。しかし、災害や感染症、サイバー攻撃など、企業を取り巻くリスクは、年々多様化・複雑化しています。
BCPとは、こうした予期せぬ事態に備え、事業の継続、あるいは早期復旧を可能にするための計画です。まさに、企業を守る「盾」と言えるでしょう。
この連載では、中小企業経営者にとって知っておくべきBCPの基礎知識を解説していきます。
第1回目の今回は、「中小企業を取り巻くリスクとBCP導入の現状」について、詳しく見ていきましょう。
あなたの会社は大丈夫? 潜むリスクを知る
企業経営において、「リスク」は常に隣り合わせの存在です。特に、中小企業は経営資源が限られているため、ひとたび大きなリスクに直面すると、事業継続が困難になるケースも少なくありません。
またリスクは、事業活動に影響を与える内容や規模がそれぞれ異なるため、各企業の特徴や地域の災害特性などを考慮して対策を講じることが重要です。
中小企業を取り巻く主なリスク
自然災害:地震、風水害(水害、土砂災害)、台風 、集中豪雨 、雷、雹など、物的被害や従業員の死傷、社会インフラ(交通、ライフライン)の寸断を引き起こし、事業の継続や回復に時間を要する可能性があります。
火災:事業所の焼失、従業員の死傷など、企業に致命的なダメージを与える可能性があります。隣接する企業や住宅への延焼リスクも考慮する必要があります。
感染症の流行・集団食中毒:従業員の集団感染や集団食中毒は、従業員の就業不能を引き起こし、企業活動の停止や低下につながる可能性があります。重症化や死亡のリスク、外部への二次感染の可能性も考慮が必要です。2019年度には、新型コロナウイルス感染症が中小企業にも大きな影響を与えました。感染症流行前と比較して、流行後には感染症を事業継続困難のリスクとして認識する企業の割合が大幅に増加しています。
求人難・人手不足:少子高齢化などの影響により、労働力不足が深刻化しており、人材の確保が困難になる可能性があります。
取引先の廃業や倒産:顧客や取引先の経営状況が悪化し、廃業や倒産した場合、売上の減少や債権回収の困難化を招く可能性があります。
経済環境のリスク:景気変動、物価変動、金利変動、為替変動などが企業の収益に影響を与える可能性があります。特に、原材料価格の高騰は中小企業の経営上の大きな課題となっています。円安による物価高も中小企業の収益悪化の一因となっています。
人為的リスク:企業内暴力、妨害、窃盗、コンピュータ犯罪(サイバー攻撃)などが含まれます。コンピュータ犯罪は、基幹システムに支障が生じた場合、企業活動に一定期間の支障をきたす可能性があります。テロリズムも人為的リスクの一つであり、直接的または間接的に被害を受ける可能性があります。
地政学リスク:国際情勢の不安定化、紛争、貿易摩擦などが、サプライチェーンの混乱や事業活動への影響をもたらす可能性があります。ロシアによるウクライナ侵略やイスラエル・パレスチナを巡る情勢悪化は、その影響が大きくなったと考えられる外部環境変化・地政学リスクとして認識されています。
リスクは、単独で発生するとは限りません。例えば、地震が発生し、その影響で停電が起こり、サプライチェーンが寸断される…といったように、複数のリスクが連鎖的に発生する可能性もあります。
これらのリスクを網羅的に検討し、自社の事業特性や経営資源を踏まえたBCPを策定することが、不測の事態における事業継続と早期復旧のために不可欠です。
導入はわずか1割程度。中小企業のBCPの実態
さまざまなリスクに直面する中小企業にとって、BCPの重要性はますます高まっています。しかし、その導入状況はどうでしょうか?
中小企業庁が作成している中小企業白書で紹介されている帝国データバンクの「事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査 2024年」によると、いずれの企業規模においても、BCP策定率は上昇傾向で推移していますが、大企業が37.1%であるのに対し、中小企業は16.5%にとどまっています。 BCP策定率の推移〜規模別〜(出典:帝国データバンク 事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査2024年 以下同)
BCP策定率の推移〜規模別〜(出典:帝国データバンク 事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査2024年 以下同)
中小企業のBCP策定状況を時系列で見ると、大規模災害の頻発や感染症のまん延など企業を取り巻くリスクが顕在化する中でも、BCPの策定状況に大きな進展が見られないことが、2020年版と2021年版の中小企業白書でも指摘されています。
BCP策定が進まない主な理由としては、以下のような点が挙げられます。

策定に必要なスキル・ノウハウがないことが最も多い理由として挙げられており、BCPの策定は中小企業にとってハードルの高い取り組みと認識されていることが分かります。
なお、これらの状況を踏まえ、中小企業の災害対応能力を高めるため、2019年5月に「中小企業強靱化法」が成立し、事業継続力強化計画の認定を受けた事業者に対し、税制措置や金融支援、補助金採択の優遇措置などが講じられています。この制度は、従来のBCPよりも簡易な申請で済むように設計されており、中小企業による事前対策の強化を目的としています。
中小企業の経営者はこのような制度を活用し、緊急事態においても、被害を最小限に抑え、事業を継続することができるようBCP策定を平時のうちに行いましょう。
備えあれば憂いなし! 今こそBCPを策定しよう
今回は、中小企業を取り巻くリスクとBCP導入の現状について解説しました。
自然災害、感染症、経済状況の変化…企業経営には、様々なリスクが潜んでいます。
BCPを策定している中小企業は、まだ1割程度。 BCPを導入していない企業は、緊急事態が発生した場合、事業の停止や顧客離れ、資金繰り悪化など、深刻な事態に陥る可能性があります。
BCPは、企業の「生存率」を高めるための重要なツールです。
「でも、自社の規模的にBCPって必要なフェーズじゃない…」
そう感じた方もいるかもしれません。
次回は、BCPの必要性について、事例を元に詳しく解説していきます。
 執筆者:坂田健太
執筆者:坂田健太
トヨクモ防災タイムズ 編集長 防災士・RMCA BCPアドバイザー坂田健太
トヨクモ株式会社で災害時の安否確認を自動化する『安否確認サービス2』の導入提案やサポートに従事。現在は、BCP関連のセミナー講師やトヨクモが運営するメディア『トヨクモ防災タイムズ(旧:みんなのBCP)』運営を通して、BCPの重要性や災害対策、企業防災を啓蒙する。