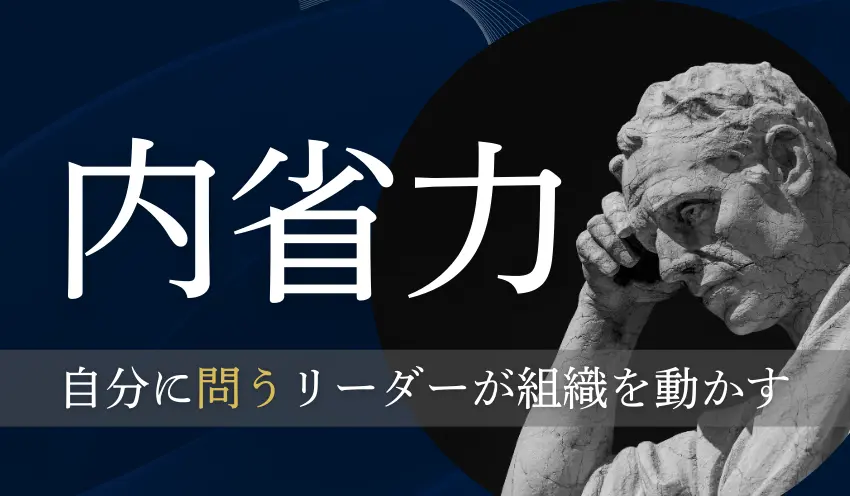新連載「貯蓄から資産形成において、FinTechと生成AIが果たす役割」。日本政府が掲げる「資産所得倍増プラン」は、NISA(少額投資非課税制度)の拡充などを通じて家計の資産運用を促進し、資産形成を身近なものにすることを目的としている。しかし、知識不足や資産形成への漠然とした不安を理由に、多くの人々が依然として資産形成を始められていないのが現状である。
本稿では、FinTech(フィンテック)や生成AI・AIエージェントの活用を通じた資産形成推進策を探り、情報過多の時代における信頼性の高い金融サービスの在り方について考察する。
初回は「資産所得倍増プラン」の概要を整理し、NISAの変遷や施策の進捗状況を振り返る。また、資産形成における重要な課題である「金融版ラストワンマイル問題」についても解説する。
■資産所得倍増プランの概要
日本政府が2022年に発表した「資産所得倍増プラン」は、NISA制度の拡充を中心に、家計の資産形成を促進することを目的としている。具体的な目標として、以下の数値が掲げられた。
・NISA総口座数の倍増(5年間で1700万口座→3400万口座)
・NISA買付額の倍増(28兆円→56兆円)
この取り組みにより、家計の資産形成を促進し、最終的には資産運用収益の向上を目指している。
一方で、資産形成未経験者も多く存在する。その主な理由として、「知識がない」「購入や保有に不安がある」といった点が挙げられている。この課題を解決するため、日本政府はNISA制度を簡素でわかりやすく、使い勝手のよいものにすることや、資産形成に関する知識の普及、安心して資産形成を行える環境整備を進めている。こうした背景から、「資産所得倍増プラン」では、7本柱の取り組みが掲げられ、具体的な施策が推進されている(詳細は後述)。
■NISAの変遷と進捗状況
そのような中、2024年6月末時点で、NISA口座数は2400万口座を突破し、政府が掲げた3400万口座の目標に向けて着実に増加している。また、NISA買付額は45.3兆円に達しており、制度の定着が進んでいることが確認できる。


特に、下の図の通り若年層(20~30代)の口座開設割合は76.9%と高く、資産形成への関心の高まりが見て取れる。一方で、NISA未開設者や資産形成に消極的な層では「証券投資をするつもりがない」と回答した割合が53.8%と過半数を占めており、引き続き資産形成の魅力を伝え、行動を促す施策が求められる。


■7本柱の取り組みに対する見解
日本政府が推進する「資産所得倍増プラン」は、以下の7本柱の取り組みに基づき進められている。
① 家計金融資産を貯蓄から投資にシフトさせる NISA の抜本的拡充や恒久化
② 加入可能年齢の引上げなどiDeCo制度の改革
③ 消費者に対して中立的で信頼できるアドバイスの提供を促すための仕組みの創設
④ 雇用者に対する資産形成の強化
⑤ 安定的な資産形成の重要性を浸透させていくための金融経済教育の充実
⑥ 世界に開かれた国際金融センターの実現
⑦ 顧客本位の業務運営の確保
筆者の現時点での7本柱の取り組みへの見解は以下の通りである。
① NISA制度の拡充により、利用者数は増加傾向にあり、順調に推移している
② iDeCo制度の改革が進行中であり、今後のさらなる拡充が期待される
③及び⑤ 金融経済教育の強化として「金融経済教育推進機構(J-FLEC)」が創設され、進展している
④ 職場NISAの導入など、企業を通じた資産形成支援が拡大中だが、まだ道半ばである
⑥ 登録の簡素化や、フォーラム開催など地道な取り組みを継続中である
⑦ 顧客本位の業務運営に関する共通KPI(評価指標)が発表され、各金融機関の取り組みが可視化されてきている
こうした施策のもと着実に前進しているものの、さらなる普及には「金融版ラストワンマイル問題」の解決が不可欠である。
■金融版ラストワンマイル問題とは?
金融版ラストワンマイル問題とは、特にマス層(純金融資産3,000万円未満)またはアッパーマス層(純金融資産3,000万円以上5,000万円未満)に対する金融サービスの提供における課題を指す。この層全体の総資産額は大きく、日本の金融資産全体の半分以上を占める。そのため、この層が資産形成に積極的に取り組まなければ、「貯蓄から資産形成」への移行は進まない。一方で個々の資産が細分化されており、従来の金融機関にとってはアプローチコストが高く、十分な金融サービスが提供されていない。結果として現在、「ネットでの自己完結」が主流となっている。
さらに、金融サービス内で情報や選択肢が過剰に提供されている中、「ネットでの自己完結」モデルでは顧客が適切な判断を下すための「ナッジ(最後の後押し)」が不足している。
このように、顧客の“最後の一歩”を埋める仕組みが不十分であり、多くの方が最適解にたどり着けていないことが「金融版ラストワンマイル問題」と言える。
次回は「金融版ラストワンマイル問題」の詳細な分析と、その解決策の一助となるFinTechの変遷について解説する。さらに、生成AI・AIエージェントを活用した新たな金融サービスが、どのように家計の資産運用を促進できるのかを探る。
 中村 仁 氏(Jin Nakamura)
中村 仁 氏(Jin Nakamura)
代表取締役社長 CEO
関西大学卒業後、野村證券入社。支店営業後、野村資本市場研究所NY事務所にて米国金融業界の調査及び日本の金融機関への経営提言を行う。
帰国後、野村證券の営業戦略の立案及び世界中の金融業界の調査も行う。
2016年4月にお金のデザインに入社し、2017年3月より代表取締役CEO就任。
2018年7月より400F代表取締役就任。一般社団法人日本金融サービス仲介業協会代表理事会長。