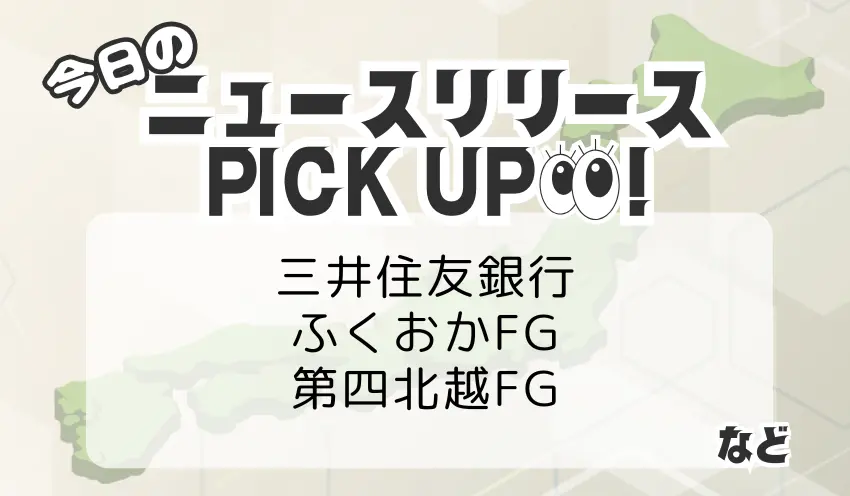1999年から2000年にかけて日本銀行による「ゼロ金利政策」が実施されて以来、日本における金融政策は「金利がない世界」となった。しかしながら、日本銀行が金融政策の正常化を行い「金利のある世界」が再び到来した。金融機関は、今後、取引先との交渉など金利引き上げが大きなテーマとなってくる。シリーズ「金利のある世界~本質の理解と顧客交渉術~」では、メガバンクなどで融資業務に長く携わってきたCMCセミナーの斎藤和男講師が、6回に分けて金利の学び直しとして基本から解説する。初回は、金利がどのような意味を持ってきたのかや、なぜ必要なのかについて。
1.金利とは(二つの意味)
ひとつ目は資金の賃貸・賃借料という意味があります。皆さんがマンションを購入するために毎月給与から積み立てを行ったり、賞与を預けると、金融機関はその預けた金額に対して利息を支払ってくれます。また、金融機関は預かった預金を元手に、企業や個人に対して融資を行います。例えばある企業に対して運転資金を融資します。その使用料として企業は金融機関に利息を支払います。
二つ目は、資金の賃貸・賃借料の元本に対する比率です。例えば、100万円の預金の使用料として(1年間)に1000円が支払われる場合には、金利が0.1%というのがその意味となります。
2.金利の歴史
資金の賃借に伴う金利のやり取りは昔から普及していたわけではありません。ヨーロッパの歴史を見てみると商業や工業が現在のように発達する以前は、事業や日常生活で大きなお金を必要とする場面は極めて少なく、ビジネスなどでの貸借は借り手の資金集めが難しいことから高い金利で貸し付ける高利貸しが多かったようです。そのための資金の貸借に金利を付けることが禁止されていた時代もありました。
しかしながら12世紀以降、商業活動が盛んとなり、規模も大きくなり、その商業活動からも利益を得ることが可能となり、お金を借りて金利を払っても利益が上がるようになりました。
16世紀以降の重商主義の時代となると、資本力にスポットライトが当たり、物価も上昇しました。それまでの経済覇権は、スペインを支えたイタリアやドイツの銀行から英国やオランダなどの商人や銀行たちへと移行しました。王室の信用度が落ちて、融資金利は引き上げられました。当時の短期融資において、その金利水準を左右する要件は主に以下の4つであったといわれています。
① アントワープ等の市場金利水準
② 緊急性を要する資金か否か
③ 借入主体の資金需要の強さ
④ 担保価値等
その金利のレンジは、おおむね10~18%程度で、個人向け融資金利は12~15%程度であったといわれています。その後、金融の中心は英国に移っていきました。
18世紀ごろの英国政府の資金調達の知恵として、国債消化の3つのポイントが挙げられています。
① 発行形態の統一化による流動性の維持
② 利払いを確実にすることによる信頼感の醸成
③ ディスクロージャーの徹底
3.イスラーム金融
現在の世界においても金利の授受を禁じているイスラーム金融について若干補足しておきます。原油価格の高騰を背景に、世界の金融市場で関心が高まった「イスラーム金融」は、金融の世界的サステナビリティやバブル抑制といった観点からもさらに注目を集めています。中近東のほか、マレーシア、インドネシア、ブルネイなど東南アジアの国でも盛んに行われています。
取引原則は主要な「商取引原則」(具体的な商取引の存在が融資の前提)と「リスクシェア原則」(イスラーム銀行と事業者が利益・損失をシェア)によって実践されています。
その本質は、イスラームの教義に則った金融で、「利子の授受」「投機的取引」「不確実な取引」「アルコールや豚肉関連の取引」を禁ずるなど独特のスキームを持っています。
4.金利の必要性
金利がなぜ必要かについては、昔からさまざまな議論が行われてきましたが、現在でも確固とした意見があるわけではありません。
時間を重視する説として、第一に「禁欲説」があります。お金の貸し手は貸出の期間中、自分の消費や投資などを抑えるという苦痛を経験しているから、お金の借り手は貸し手に苦痛の対価として金利を支払う、という説です。
第二の説としては「時差説」です。現在は手元にはないが将来初めて使うことができるようになる100万円よりも、現在手元にありすぐにでも使える100万円の方の価値が高いと考えるのです。お金が使える時点の差を考えた価値の相違が金利になる、ということです。
第三は「流動性選好説」です。さまざまな商取引の代金を決済する際に相手方に最も受け入れられやすい資産である通貨を貸出などによって一次的に手放すと、貸し手はその間、自己の取引の決済ができないなどの不便を被るのでその報酬として金利を支払う、というものです。
時間を重視する説以外では、利子率が高まると貯蓄が増加し、投資が減少することから、金利は貯蓄と投資が均衡するところで決まる「貯蓄・投資説」や、貸付金に対する需要と供給で金利が決まる「貸付資金説」などもあります。そのほか「生産力説」では、事業を行う際にお金を借りることができれば、借りることができないときに比べ事業規模を大きくして、利潤も大きくなります。このため借り手は貸し手に対して、お金を使わせてもらったことに対する代償として、事業で得た利潤の一部を利子として支払う、という考え方です。