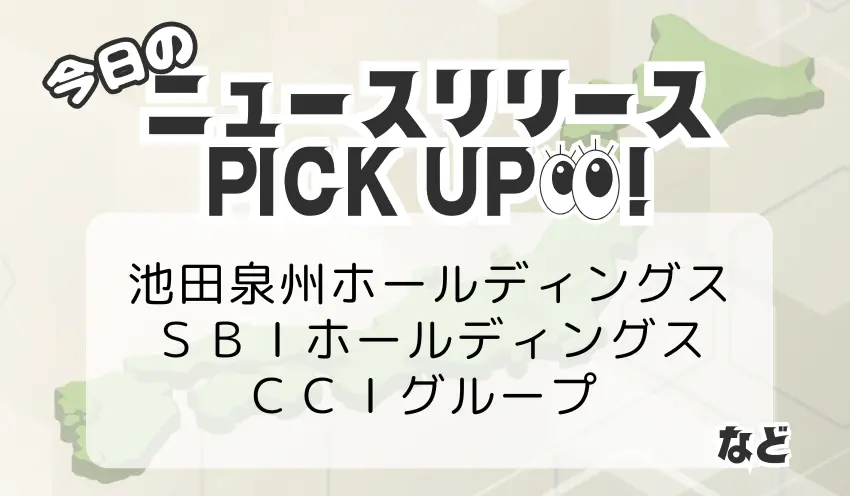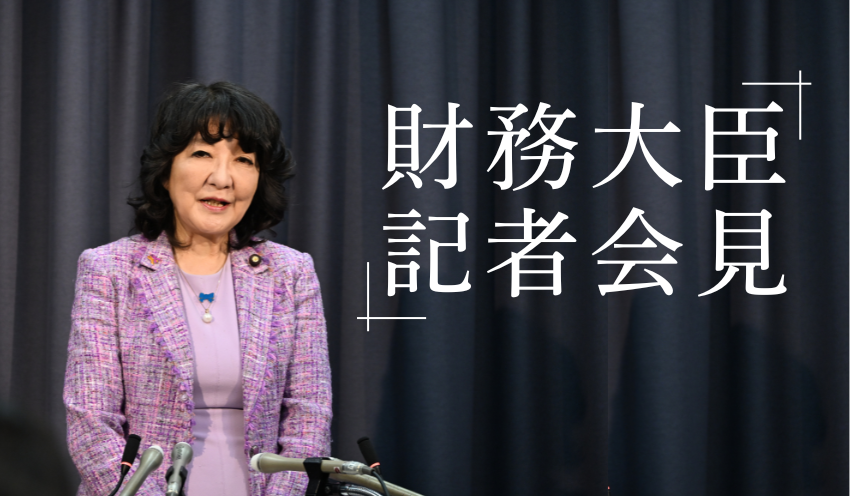昨今深刻化している従業員定着率の低下。厚生労働省の雇用動向調査によると2022年の離職率は15.0%と、前年の13.9%から上昇している。離職の理由は、「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」や「職場の人間関係が好ましくなかった」などの理由が挙げられる。定着率の低下は、生産性の低下、しいては業績の低下につながるほか、優秀な人材を採用できず、採用コストも上昇する。定着率の向上には、労働環境・社内環境の見直しや社内コミュニケーションの促進などが重要といわれる。シリーズ「経営を救う!今こそ見直すべき「社内報」運用」では、大半の企業が実施している〝社内報〟に焦点をあて、5回にわたり、日本の金融機関が直面する行職員定着率の低下、採用難などの課題を解決する社内報運用について解説していく。第1回目となる今回は、課題を紐解きながら、行職員の定着とエンゲージメントの関係性について解説する。
金融機関で従業員定着率の低下が深刻化
国内の金融機関は今、行職員定着率の低下、採用難などの課題に直面しています。厚生労働省が発表した「新規学卒就職者の離職状況」によると、2020年に卒業・就職したのち、3年以内に金融業・保険業を離職した人の割合は、新規高卒就職者で31.7%、新規大卒就職者で26.3%。どちらも2019年と比較すると増加しています。
HR総研と楽天みん就が公開している「2023年卒学生の就職活動動向調査」においても、「就職したくない業界」として15%の学生が「メガバンク、信託銀行」、12%が「地方銀行・信用金庫」と回答しています。
これらのデータから、金融機関では行職員定着率の低下、採用難の課題に直面しており、引き続きこれらの問題が深刻化していくと考えられます。現状のままでは、組織に人がいなくなり、経営自体が困難になっていくことは明白です。
従業員の定着には従業員エンゲージメントが関係している!?
アメリカのコンサルティング会社CEB社(※1)が発表したデータによると、従業員エンゲージメントが高くなると離職確率は87%減少するとしています。さらにアメリカのバンク・オブ・アメリカ社(※2)が発表したデータでは、従業員エンゲージメントスコアが上昇すると離職率は減少することがわかっています。
※1 出典:「Driving Performance and Retention Through Employee Engagement」より。また、現在CEB社はGartner社と統合されています。
※2 出典:「2020 HUMAN CAPITAL MANAGEMENT REPORT 」Bank of Americaより
また厚生労働省の『令和元年版 労働経済の分析』においても、エンゲージメントが高い企業では社員の離職率が低下し、定着率が向上していることも言及されており、これらのデータから従業員定着率や採用難と従業員エンゲージメントは関連していると言えるでしょう。
見直すべき〝社内報〟の重要性!
社内報は、従業員エンゲージメント向上につながる社内コミュニケーションの手段の1つです。社内コミュニケーションを通して組織の目標と価値を明確に共有し、従業員同士の連携を強化、全体の生産性や効率を向上させることで、従業員のエンゲージメントの向上、それに伴う定着率の向上を期待できます。
社内コミュニケーションには社内報のほかにも、会議、Eメール、社内SNS、社内イベント、表彰制度、直接の対話などさまざまな手法があります。なかでもWeb社内報は、すべての従業員に情報をスピーディーに届けることができ、社内に情報を蓄積できる手法です。デジタルネイティブである若手社員がより親近感を得やすいように、画像や動画などの挿入をすることによって、従業員のエンゲージメント向上にもポジティブな影響を与えられます。
第2回では金融機関が直面している課題に沿いながら、社内報の目的や機能について解説します。
▼執筆者略歴
髙橋 新平(たかはし しんぺい)
ourly株式会社 取締役COO
WEB 社内報CMS「ourly」事業責任者。京都芸術大学非常勤講師。新卒でダイキン工業株式会社に入社。技術営業として都内の再開発案件に多数携わる。その後、株式会社ENERGIZEに入社。4年間主にベンチャー、中小企業の事業コンサル、組織コンサル等に従事して独立。2022年4月からourly 株式会社へ執行役員CSOとして参画。2023年4月より現職。