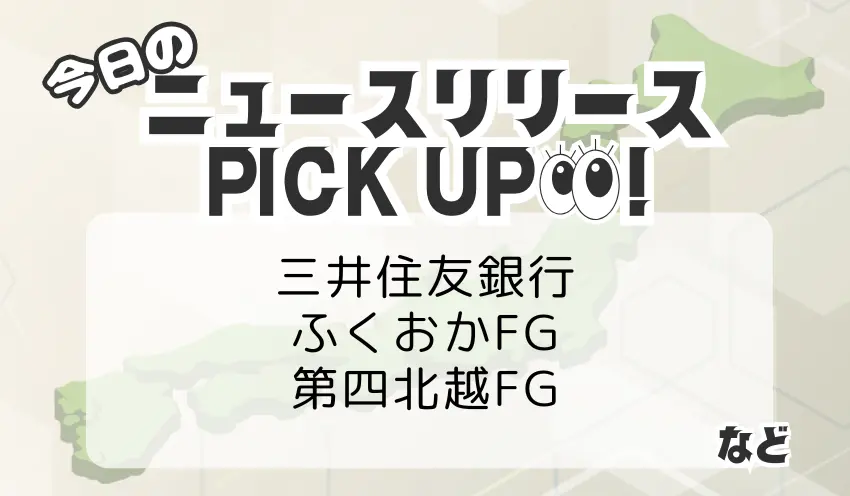高齢化社会が進展している。総務省の人口統計によると2023年(9月15日現在)の65歳以上人口は、3623万人と前年比1万人減少。しかし、総人口に占める割合は、29.1%と前年から0.1ポイント上昇、過去最高となった。介護保険制度における要介護者の数も大幅に増加している。また、家族を介護しながら働く人は2022年に364万6000人と10年前に比べ25.3%増加。介護・看護を理由とした離職者数は年間10万6000人に上っており、経済産業省が試算した介護離職や労働生産性の低下による経済損失は、2030年に9兆1792億円と予想している。老人ホームや相続・贈与、見守りなどの相談室を展開するオヤノコトネットには、親の介護で悩みを持つ40~50代からの相談が増加しているという。シリーズ「悩めるマジョリティ「親介護世代」を知る」では、相談室に寄せられた悩みをもとにした解決事例を紹介する。金融機関の営業担当者が日ごろの活動に生かせる情報だ。本題に入る前に初回は、筆者が懸念する2025年問題について解説する。
急増が懸念される要介護認定者
以前から2025年問題と言われ散々話題になりましたが、果たして2025年はもう目の前、来年なのです。
では2025年問題とは何か?
ご存知の方も多いと思いますが、端的に言えば、終戦直後の1947年~1949年に生まれた団塊の世代は出生数で約800万人と人口のボリュームゾーンですが、その全員が75歳以上の後期高齢者になるのが2025年で、要介護認定者が急増することが懸念されているのです。
現在、要介護認定者は約700万人ですが、65~74歳までの要介護認定率と比べて、75歳を過ぎると一気に認定率が上がることがデータでも示されており、人口の多い団塊の世代が全員75歳の後期高齢者を迎えるとなると我が国の社会保障制度も抜本的な改革を求められることになるでしょう。
さらに、その子世代、団塊ジュニアがちょうど50歳前後になり、親や家族の介護・看護のために離職した、介護離職の問題もさらに顕在化する可能性が出てきます。
現在、年間約10万6000人(令和4年(2022年)就業構造基本調査より)と言われる介護離職者だけでなく、ビジネスケアラーと言われる、親を介護しながら仕事を続ける人たちが300万人を超えることで日本経済に大きな影響を与えかねないと言われているのです。
しかしながら、ここはひとつのビジネスチャンスでもあります。
団塊世代が後期高齢者となり、団塊ジュニアが親の財産を相続する件数はこれから大きく伸びると言われ、まさに、50兆円市場ともいわれている相続に関係するマーケットが盛り上がっていることは言うまでもありません。
まさに、大相続時代が到来しているのです。
特に、家族信託はブームのようになってきており、テレビや雑誌、ウェブで見かけない日は少なくなりました。
かつてNHKがクローズアップ現代で取り上げたことも影響していますが、ウェブで「家族信託」と検索するだけで、家族信託のコンサルティング会社から信託銀行、司法書士事務所など多くの事業者のウェブページが露出します。
ただ、私の知る限り「家族信託」というキーワードでリスティング広告を打ったり、セミナーを開催したりしても実際に顧客として獲得できる率は高くはないようです。ある司法書士に訊いたところ、リスティング広告は投資に対してリターンが合わないので止めたと言っていました。
確かに「家族信託」というワードを聞いたことがある人は増えていますが、詳しく内容について知っている人は多くないようです。
それどころか、まだまだ「親が認知症になると資産が凍結される」ことを知っている子世代も決して多くはなく、その点は個人的にも心配しているところです。
また、その「資産が凍結される」ことを知って、ウェブサイトで検索してヒットした専門家にすぐに相談するという人も少ないようです。先ほども話したように、多くの専門家がヒットしますので、そのなかから信頼できる相談相手を見つけるというのも一苦労です。
今の時代、ウェブ経由の情報に警戒心をもつ方が急増しているということを感じます。
今後のシニア向けのマーケティングにおいてはこのことを理解した上でお客さまを呼び込むことがポイントになりそうです。