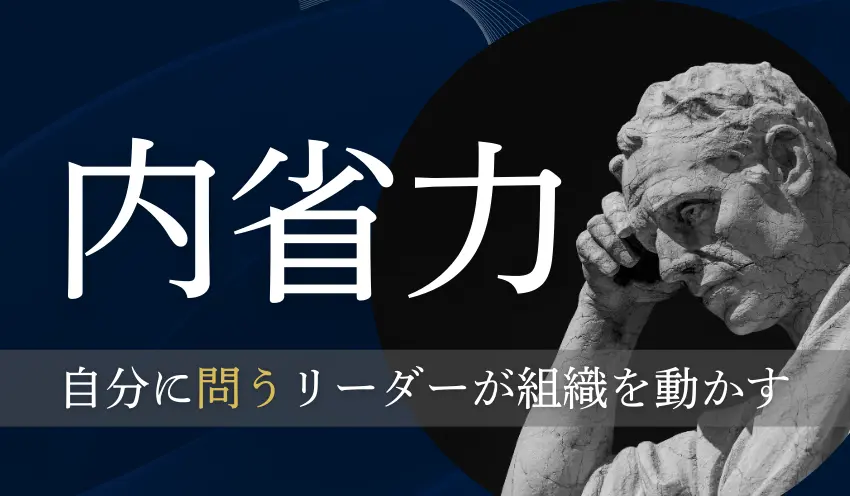コロナ禍の資金繰りを支えた無利子・無担保(ゼロゼロ)融資。4月には5万社超(民間金融機関分)が返済開始時期を迎えている。一方、企業の倒産件数は増加傾向を続けており、帝国データバンクによると2023年の企業倒産件数は8497件で前年比33.3%の増加。そのうち、粉飾決算による〝コンプラ違反倒産〟は79件(同23.1%増)となっており、ゼロゼロ融資の返済開始により粉飾発覚するケースが増えているという。シリーズ「決算に潜む粉飾の痕跡~ゾーンに入ったベテラン審査役の着眼点~」では、金融機関向けに取引先の資金繰り予想クラウドサービスを提供する竹橋経営コンサルティングの企業審査に精通したコンサルタントが〝粉飾〟をテーマに金融機関の審査・営業部門向けにポイントを解説する。今回は「粉飾決算を行う経営者の心理」がテーマ。
粉飾決算を行う経営者の心理
これまで我々が見てきた粉飾決算の実例を振り返り、その経営者の心理を想像してみると、初めは「これくらいなら」という軽い気持ちで手を出してしまうことが多いと感じます。
一時的な業績悪化による赤字を避けるために、どの経営者も最初は「今期だけ」のつもりで利益調整を行い、次の期は何とかして業績を回復させようと考えています。ところが、次の期も業績が回復しないと、再び粉飾せざるを得なくなります。次第に歯止めが利かなくなり、粉飾額も風船のように膨らみ続け、最終的には破綻します。最近の動きでは、堀正工業の粉飾倒産を思い出す方も多いのではないでしょうか。
中小企業の決算では、会計監査によるチェックが入るわけではなく、黒字に粉飾して税金を納める場合、税務署からのお咎めもありません。このため、融資を継続してもらう必要がある企業には、粉飾の誘惑が絶えず付きまとうといっても過言ではありません。このような状況下で、企業との面談頻度が少なく、上辺だけの付き合いになっていると、経営者としては数字で嘘がつきやすくなってしまうのです。
この状況を改善させるためには、経営者に「粉飾しても意味がない」という思いにさせる、金融機関からの「牽制」が有効です。そのためには、行員一人一人が高い志しを持って経営者との深い対話を重ね、「担当の○○さんには嘘をつけないな」と思わせることが必要です。
粉飾決算の背景には金融機関にも責任の一端が
企業を支援するなかで常に感じていることですが、金融機関が決算書の細かい指摘や重箱の隅をつつくような会話をしたり、「赤字決算では融資できません」と冷めた対応をしていると、経営者は数字をいじりたくなります。決算書の見栄えを良くすれば、融資申込時の審査もスムーズに通るからです。しかし、一度数字で嘘をついてしまうと、必ずや再び嘘を上塗りすることになり、最後は悪い結末を迎えます。
金融機関では、粉飾が発覚したときに鬼の首を取ったように企業を責めることがあるのではないでしょうか。
しかし、粉飾決算の下地が作られる背景には「金融機関にも責任の一端がある」ことを認識する必要があると思います。期中の業況も把握せずに、年に1度、決算書だけを見てすべてわかった気になっていないでしょうか。このような現在の与信管理のあり方全体を見直していく必要があるはずです。
是非、今回の連載を通して、金融機関として真の中小企業の理解者になるとともに、与信管理の高度化を目指していただきたいと思います。
▼▼▼▼
竹橋経営コンサルティングについて
当社のメンバーは政府系金融機関出身者等で構成されています。同機関在籍時に培った企業審査のノウハウや、自社で開発した資金繰り予想システムを活用して、企業の経営改善支援を行っています。当社の資金繰り予想システムを活用すれば、1年間の資金繰り予想を自動で作成することができます。金融機関のユーザー様にも資金繰り予想システムを提供しており、融資先との対話、企業審査、経営指導にご活用いただいています。また当社では、資金繰り予想を活用した経営者との対話方法や企業審査の研修も行っています。
 古尾谷 未央 氏(フルオヤ ミオウ)
古尾谷 未央 氏(フルオヤ ミオウ)
有限会社竹橋経営コンサルティング代表取締役
公益財団法人日本生産性本部認定経営コンサルタント
大学卒業後、日本政策金融公庫へ入庫。
10年の在籍で融資、審査、債権管理など中小企業金融に関する幅広い業務を経験。
その後、公益財団法人日本生産性本部を経て独立。
金融機関向けに取引先の資金繰りを予想するシステムICAROS-Vを開発。
それにあわせて金融機関と一緒に取引先企業の改善支援も行っている。
一般社団法人全国地方銀行協会にて資金繰りに関する研修実績あり。
著書
『融資業務変革の基点』金融財政事情研究会、『借りない資金繰り』同友館、
『新米社長チワワvs政府系金融機関』同友館、通信講座「資金繰り完全理解」ビジネス教育出版社