
団塊の世代が全て75歳以上になる2025年まで、残り1年となった。各都道府県では地域の医療提供体制が目指すべき姿として、政府が掲げる「地域医療構想」の推進に向けた動きが拡大。医療機関は少子高齢化に伴う医療需要の変化や労働力人口の減少を見据え、より再編統合による機能分化や連携が求められている。一方、地域経済を支援する金融機関にとっても、地域活力の維持・発展のために医療介護分野の支援は必要不可欠と言える。シリーズ「金融機関が地域医療を支える! ~熱い想いを持つバンカーの話~」では、金融の枠を越えて医療業界を支える医療介護担当者を紹介。地域医療への金融機関の関わり方について、各担当者の取り組みを通して、あるべき姿を考える。
新型コロナウイルス感染症との闘いの収束
年末年始にかけて、皆さまはいかがお過ごしでしたでしょうか。クリスマスや忘年会をご家族、友人、会社仲間との親交で楽しまれた方、お正月には故郷へ帰省されご親族や旧友と新年を祝われた方も多かったのではないでしょうか。
世界的なパンデミックとなった新型コロナウイルス感染症の脅威から外出自粛が図られた2020年春以降、多くの方は移動を制限され、家族や友人に会う機会も減っていたものと思います。新型コロナウイルス感染症の5類移行後は、対面交流の機会が増え、日常を取り戻しつつあることを嬉しく思うものです。
この間、通常診療に加えて、新型コロナウイルス感染症に奮闘してこられました医療従事者の皆様の信念と行動に、尊敬の念を示します。誠にありがとうございます。
転機を迎える医療機関経営
さて、地域医療を支える医療機関の経営は、正に帰路に立たされています。3年の長きにわたる新型コロナウイルス感染症との闘いが収束を迎える中、国から医療機関に交付されていた病床確保料等の行政支援(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金)が減額されていく一方で、ポストコロナの医療提供を維持するための体制構築にかかる費用・支出は増加しています。支援の縮小とコストの増加が、経営状況を圧迫する要因となっているわけです。
また、医療機関が医療サービスの対価として受け取る診療報酬は2年に1度の改定であるため、収益増につながる価格転嫁が機動的ではありません。ウクライナ情勢を機に起こった資材高騰や水道・光熱費等の上昇は、医療機関にとっては他業界よりも経営に直結する問題となっています。
医療・介護業界に迫る「2025年問題」と「2040年問題」
日本の人口が減少局面に転じる中、団塊の世代が全て75歳となる2025年には75歳以上の人口が全人口の約18%となります。さらに、2040年には65歳以上の人口が全人口の約35%になると推計されています。2025年以降、人口減による各地域での患者数の減少や医療機関に従事する医師や看護師等の不足は、地域の永続的な医療提供体制の維持にとっては大きな不安要素となります。
こうした中で各都道府県に求められているのが、地域の医療提供体制にとって将来あるべき姿である「地域医療構想」を医療計画の一部として新たに策定することです。構想区域ごとに各医療機能の将来の必要量を含め、その地域にふさわしいバランスの取れた医療機能の分化と連携を適切に推進することが、2014年の医療法改正により定められました。厚生労働省の「医療施設調査」によると、2022年10月1日時点で全国の医療施設は180,193施設。特に病院は8,156施設ありますが、医療機関を取り巻く環境は大変厳しいものとなっています。
シリーズについて
私が在籍する株式会社日本経営は、医療機関・介護施設に対して事業構想や事業計画の立案、経営改善や事業再生、働き方改革に関係する業務プロセスや人事評価制度構築のご支援等のコンサルティング業務を行っております。「現場主義」をモットーに、地域の医療と介護を支える経営者に寄り添いながら、永続的な経営が図れるようご支援をさせていただいております。
このシリーズを通して業務で得た知見や金融機関との連携事例を分かりやすくご紹介し、皆さまの業務の一助となれば幸いです。次回は、「医療機関に対する金融機関の取り組みと課題」についてご説明します。
 新沼 寿雄 氏(にいぬま ひさお)
新沼 寿雄 氏(にいぬま ひさお)
戦略コンサルティング事業部 副主幹
株式会社日本経営
国内大手証券会社ホールセール部門での勤務を経て日本経営入社。主に医療機関の事業構想、戦略策定、利益改善、再生支援業務を担当。コンサルタントとして現場改善の業務に多数従事。他方で地方銀行への出向経験もあり、金融機関との連携や協業に関して社内で中心的な役割を担う。ご相談等はこちらまで→hisao.niinuma@nkgr.co.jp
▼コーポレートサイト▼
株式会社日本経営




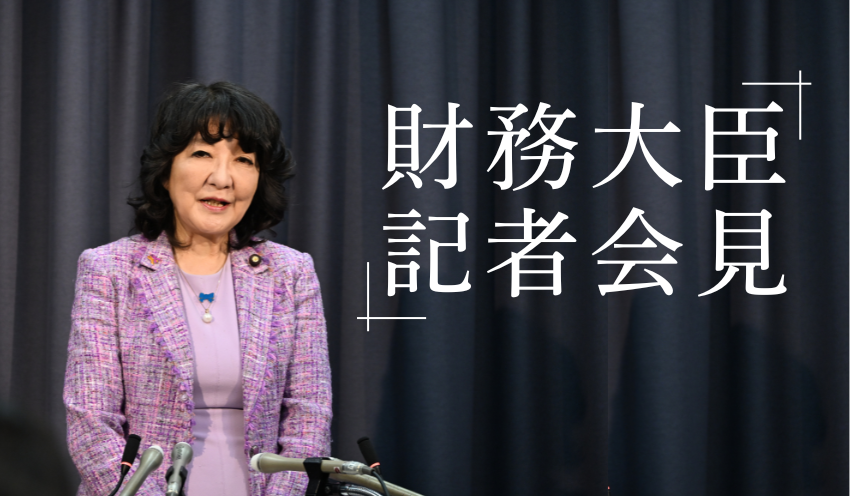

-国産牛乳「危機」から一転-9.webp)