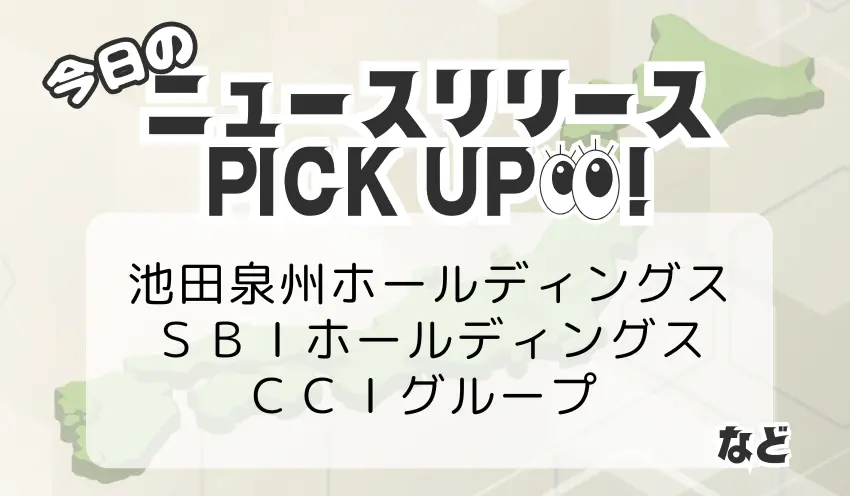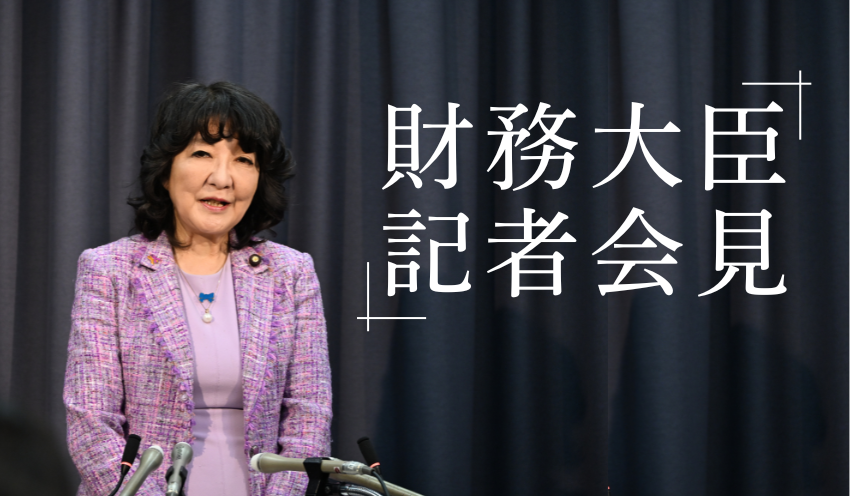人手不足が慢性化する日本経済。人手不足を要因に業績が悪化し倒産するケースも増えている。経営者にとっては事業を継続するうえで深刻な問題となりつつある。今回からはじまるシリーズ「銀行から始まる!地域企業のためのスキルシェア入門」では、外部のプロ人材や副業人材を活用して地域活性化につなげるプロシェアリングサービスを展開するサーキュレーションの福田悠社長が金融機関の営業担当者向けに経営者の悩みを解決に導く手法を紹介する。
2018年に金融庁が金融機関に人材業を解禁してはや5年。内閣府は2019年度から始まった「先導的人材マッチング事業」のなかで、地域金融機関について「日常的に地域企業と関わり、その経営課題を明らかにする主体である」と注目しています。
こうした政府の期待を背景に、近年、企業への人材紹介や人材マッチングなどの手法を使って社長のお悩みを解決する取り組みを始めている金融機関が増加しています。なかでも、雇用や派遣に代わる新たな人材活用手法として、副業やフリーランスが業務委託で仕事を受ける「スキルシェア」の注目が高まっています。フルタイムで地方に転職や移住はできなくても、今すぐ企業に必要なスキルを持つ人材をマッチングできるのが魅力です。効果は絶大である一方で難易度が高いのも現実です。
シリーズ「銀行から始まる!地域企業のためのスキルシェア入門」では、どうすれば企業の社長のお悩みに対して人材活用で成果を出せるのか、実際の事例やデータを用いて解説します。
中小企業の約65%で人が足りていない
今、日本全体が慢性的な人手不足に陥っています。日本商工会議所が2022年に実施したアンケート調査によれば、中小企業の約65%が人手不足と回答しました。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で事業運営が滞った結果、一時は人手不足が改善されたように思われましたが、日常生活が戻るにつれて、コロナ前同様の高水準に戻ってきています。
 ※日本・東京商工会議所「人手不足の状況および新卒採用・インターンシップの実施状況に関する調査」 調査結果から引用
※日本・東京商工会議所「人手不足の状況および新卒採用・インターンシップの実施状況に関する調査」 調査結果から引用
ここでいう「人手不足」とは、いわゆるマンパワー、労働力としての人員不足を主にさしています。しかしそれ以前に、こうした人手不足を補うような生産性の高い人材や業務改善が可能な人材がそもそも不足しているからこそ、人手不足の状況はなかなか1社だけでは改善できないという背景も考えられます。
地域銀行は大手人材会社よりも身近に社長の悩みを聞いている
こうした人手不足の悩みを一番身近に相談されているのは誰でしょうか?
それは、大手人材会社……とは限りません。媒体掲載料やコンサルティング料、さらに成約手数料を払って人材を採用できる企業は全体の一部です。
さらに、今や人材サービスも非常に多岐にわたっています。企業も欲しい人材ごとにハローワークや学校推薦、媒体利用、人材コンサルティング、ヘッドハンティングなど選択肢が増えているため、継続的に人材の悩みに対応できる唯一無二の人材会社は存在しないと言っていいでしょう。
一方で、ほとんどの企業には必ず担当する銀行員がいます。場合によっては何十年、何代も続く企業の財務情報や事業経緯を把握し、社長からも信頼を得ている唯一無二の存在です。銀行員だからこそ、社長の想いを汲み取り、カネだけではなくヒトに関する悩みも解決できる可能性があるのです。
具体的に、なぜ銀行員こそが人材活用のプロになるべきなのか、3つの理由をご紹介します。
①銀行員は誰よりも多くの企業の財務情報を持っている
人材活用の課題は、元はといえば事業成長や継続に必要だからこそ、手段として現れてくるものです。顧客の経営状況をPLやBSでほぼ正確に把握し、日々与信判断や融資業務を行っている銀行員は、経営状況を良くするための根拠となる財務情報を元に、より本質的な議論が社長とできるはずです。
②銀行員は誰よりも企業と長く、強い関係性を築き続けている
銀行は企業設立から廃業まで付き合う言わば「運命共同体」。メインバンクを変えられない限りはずっと関係性を保つことになります。創業からの経緯を知る立場として、社長からの信頼の大きさは非常に大きく、人材会社などの民間他社が簡単に取って代われるものではありません。
③銀行員は誰よりも社長に寄り添える
銀行員のカウンターパートは常に経営者や経営に近い場所です。これが意味するのは、銀行員は誰よりも社長の「やりたいこと」、事業を通して実現したい未来を知り、寄り添うことができる立場にあるということです。人材活用の課題の優先順位は、企業の描きたい未来から逆算できます。銀行員には、人材会社よりも社長との接点も多く、信頼されている土台があるからこそ、企業の未来から課題を抽出できる有利な点があるのです。
課題は「候補者を見る目」と「プロジェクトを見る目」
このように、銀行員には地域企業の事業成長を支援し、その手段の一つとして人材活用という側面からアドバイスを行うことができる可能性を秘めています。
しかし、本業でカネに特化してきたからこそ、すぐにプロになるのが難しい点はあります。それは、「候補者を見る目」と「プロジェクトを見る目」です。
具体的には、人材マッチングにおいて要とも言える、「企業のニーズや社風に合わせて候補者のスキルやスタンスを見極める経験」、そして特に、短期間で高い成果を求めるのに向いているスキルシェアを紹介する際には「紹介後、人材と企業がうまく業務を進められているか察知し、適切なフォローを行う経験」はこれまでの業務ではあまりなかったはずです。
極論をいえば、逆にこうした課題さえクリアできれば、銀行員は人材会社よりも上流で企業の経営課題を定義し、必要な金融・人材支援を行う唯一無二のパートナーとして、地域経済の活性化にさらに大きな影響を持つことができるでしょう。
今後の連載では、スキルシェア企業のノウハウやデータを元に、どのような経営課題でスキルシェアが役立つのか、失敗しないためのポイントなどを解説していきます。
株式会社サーキュレーション代表取締役社長 福田 悠 中央大学理工学部を卒業後、大手総合人材サービス企業へ入社。製造業を中心とした約600社の人材採用を支援。大手法人顧客専属部門を経て、同社初となる社内ベンチャーの立ち上げに携わる。2014年、サーキュレーションの創業に参画。中小企業や製造業大手顧客を担当しながら、地方金融機関とのアライアンス、地方7拠点の設立を主導。オープンイノベーションコンサルタントのプロフェッショナルとしてレガシーマーケットの変革を志してきた。
中央大学理工学部を卒業後、大手総合人材サービス企業へ入社。製造業を中心とした約600社の人材採用を支援。大手法人顧客専属部門を経て、同社初となる社内ベンチャーの立ち上げに携わる。2014年、サーキュレーションの創業に参画。中小企業や製造業大手顧客を担当しながら、地方金融機関とのアライアンス、地方7拠点の設立を主導。オープンイノベーションコンサルタントのプロフェッショナルとしてレガシーマーケットの変革を志してきた。