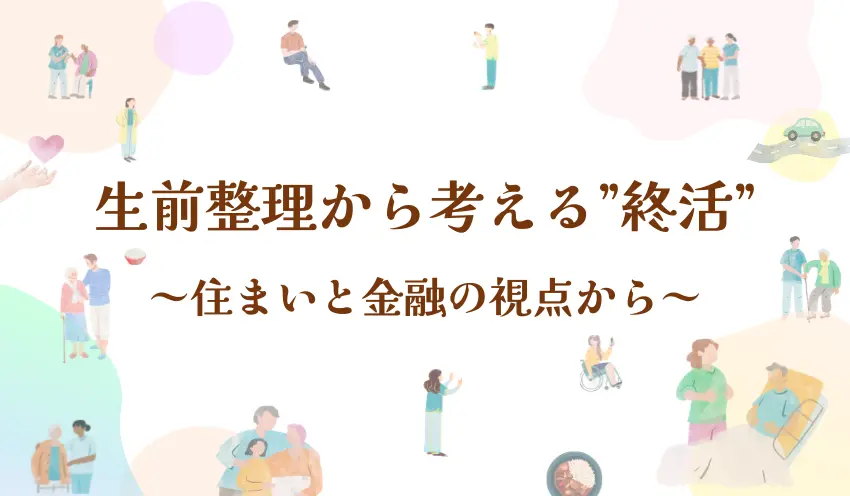
少子高齢化が進むなか、「終活」は一人ひとりの課題にとどまらず、地域全体で考えていくべき大きなテーマになりつつある。
とりわけ、土地や建物といった不動産資産の整理は専門的な知識が求められ、相続や金融とも深く関わってくる。
今回の連載では、住まい・高齢者住宅の分野で実績を持ち、地域の終活支援にも取り組む長谷工グループのカシコシュ社が寄稿する。
現場での課題や支援の実例、金融機関との連携の可能性などを紹介し、地域金融機関や関係者にとって役立つヒントをお届けしていく。
~早めの「住まいの棚卸し」で資産と家族を守る~
■「空き家」を放置するとどうなるのか?
「空き家」の放置は、次のような深刻なリスクを伴います。
・資産価値の急落や資産の凍結
・管理・維持の長期化とそれに伴うコスト増
・特定空家や管理不全空家に指定される(固定資産税が最大で6倍になることも)
・不法侵入や犯罪の温床
・老朽化による倒壊・火災
・名義未変更による権利関係の複雑化
・景観の悪化と地域への悪影響
■「空き家」の放置原因でよく見られるケース
CASE_1
〈一人暮らしの高齢者にとって広すぎる家〉
かつて家族で暮らした戸建てに高齢者が単身で居住。2階は使わず、庭の手入れも困難。
↓↓↓
固定資産税や水道光熱費が生活を圧迫。体力低下で片付けもできず、やがて「ごみ屋敷予備軍」に⇒身内も遠ざかり⇒孤立化⇒「空き家」
CASE_2
〈家族間での対話不足〉
「義兄弟・姉妹夫婦や娘婿に話しづらい」「相続で揉めたくない」といった不安から対話を避ける。
↓↓↓
結果として施設入所後や認知症の進行により意思決定ができず、資産が凍結、家は放置状態に。
■空き家対策の第一歩は早めの「住まいの棚卸し」
「まだ大丈夫」「子どもに迷惑をかけたくない」と家族間での話し合いを後回しにすることで、結果として住まいが空き家となるリスクが高まります。
家族で早めに話し合い、住まいの状況と将来を整理する「住まいの棚卸し」が、空き家対策の最初の一歩となります。
■「住まいの棚卸し」の進行を妨げる障壁
・心理的ハードル⇒「親子で財産の話は切り出しにくい」「義理の家族に遠慮する」
・相続の煩雑さ⇒名義変更、相続税、固定資産税などに専門知識が必要
・金銭的制約⇒年金収入だけで生活する高齢者は、住み替えを検討する余裕がない
こうした理由から対策の機会が先延ばしとなり、結果として空き家問題が深刻化しています。
総務省の統計(2023年)によれば、日本の空き家は約900万戸。その多くが、相続の未手続きや単身高齢者の施設入居や死去によって発生しています。
■「住まいの棚卸し」に必要な3つのプロセス
1)物の整理:不要品の処分・リユース活用
2)心の整理:家族間でライフプランや想いを共有
3)情報の整理:相続・不動産評価・契約関係、公的制度の把握
↓↓↓
専門家(金融・不動産・ライフプランナー等)と連携することで、感情面・法務面・経済面のリスクを大幅に軽減できます。
■今すぐできる「住まいの棚卸し」3つのアクション
1)情報の整理:不動産の評価額、固定資産税、契約書類の確認
2)生活コストの把握:維持費と将来の収入をシミュレーション
3)選択肢の検討:リフォーム、賃貸、売却、施設入居などの条件を比較・検討
■まとめ
「住まいの棚卸し」は、単なる“片付け”ではありません。
資産の価値を再認識し、将来の安心につなげる「人生の棚卸し」です。
空き家を作らず、家族の安心を守るために──。
今から始めることが、次の世代への最大の思いやりかもしれません。
■次回予告
第2回:「住まいの棚卸し」・家族構成の変化と「家族との対話」 ~人生の選択を支える“対話”と“情報整理”~ についてお届けします。
ぜひご期待ください。
【参考データ】
総務省「住宅・土地統計調査(2023)」
国土交通省「空き家対策に関するガイドライン」
著者プロフィール
大武 敏朗(おおたけ・としろう)
株式会社カシコシュ(長谷工グループ) 代表取締役社長
株式会社長谷工コーポレーションにて現場監督を経験後、
長谷工グループ内での新規事業開発に従事。
住まいと暮らしに関わる社会課題の解決を目指し、リユース事業の立ち上げを主導。
現在は、空き家対策・生前整理・高齢者支援を中心とした事業を展開している。
空き家対策の相談に対しては、片付けや整理収納のアドバイス、
宅配収納サービスや写真デジタル化・データ化サービスなどを提案。
片付けから始まり、リフォーム、売却、住み替えまで、
適切な事業者との連携を通じて一貫した支援を行っている。
高齢化社会の進展に伴い、遺品整理や生前整理の需要が高まる中、
業界の質やコンプライアンスにも注目し、消費者が安心して利用できる「住まいの総合プラットフォーム:くらしのちゃんねる」の構築を進めている。



-国産牛乳「危機」から一転-2.webp)
-国産牛乳「危機」から一転-1.webp)
