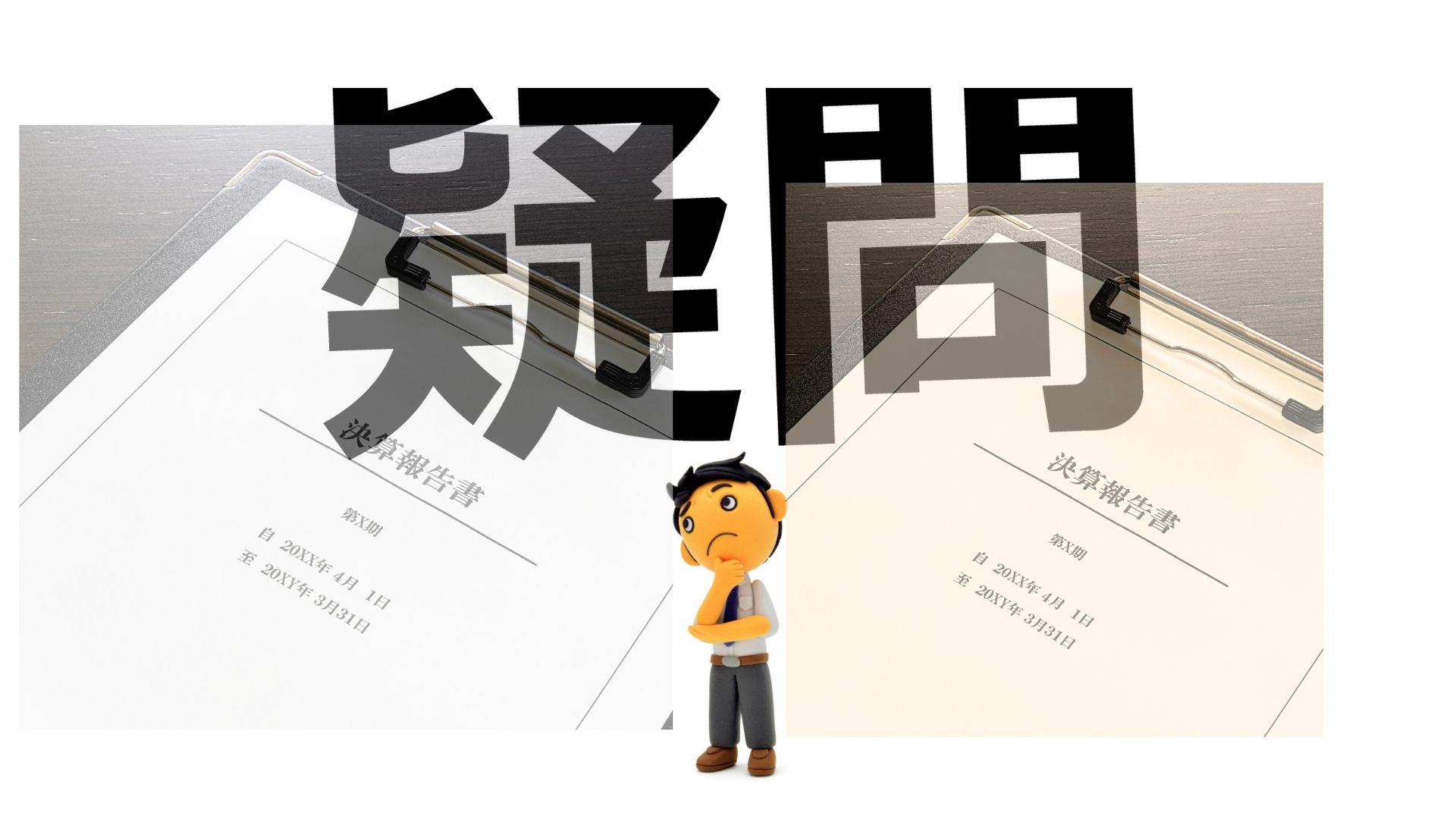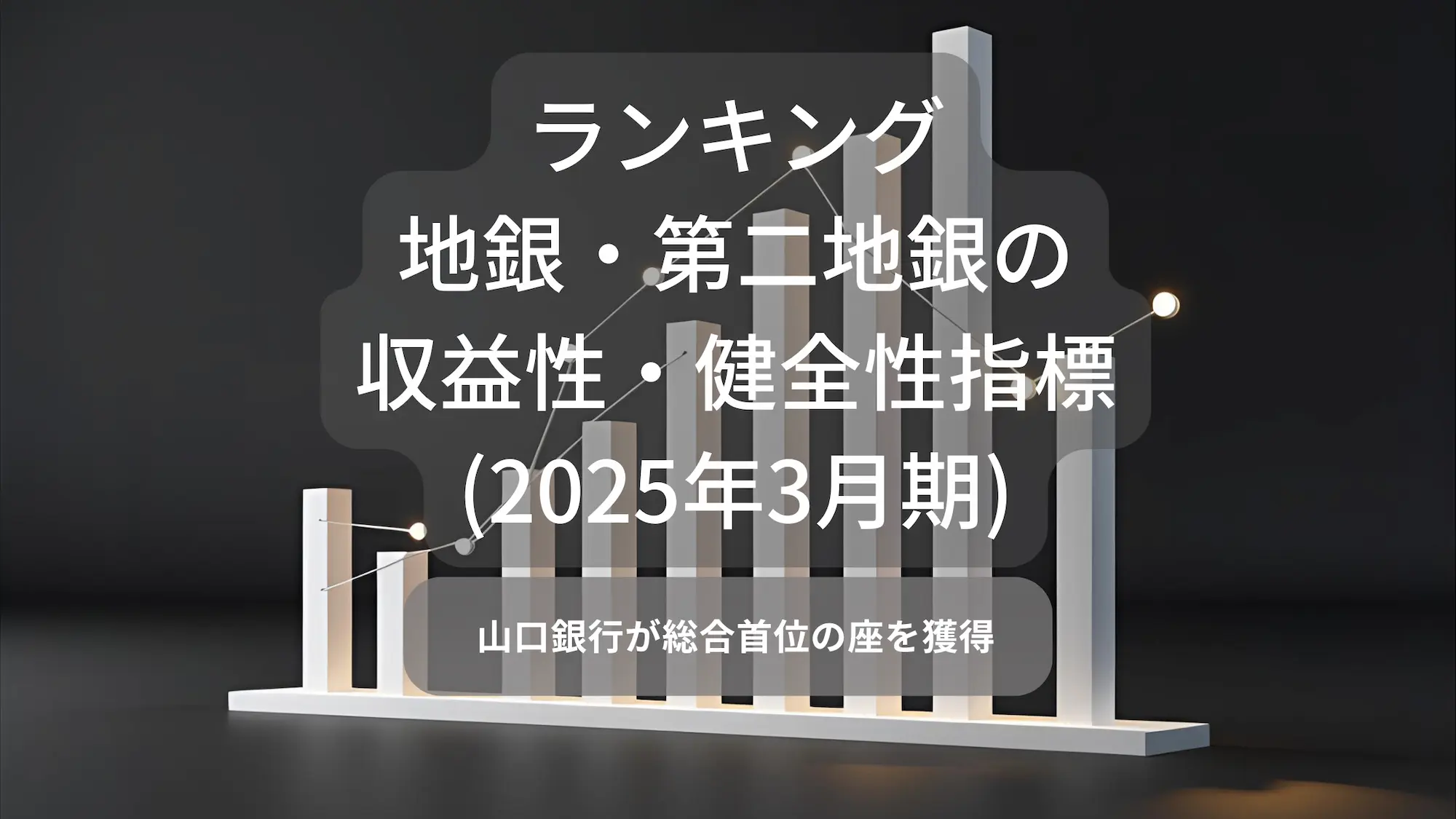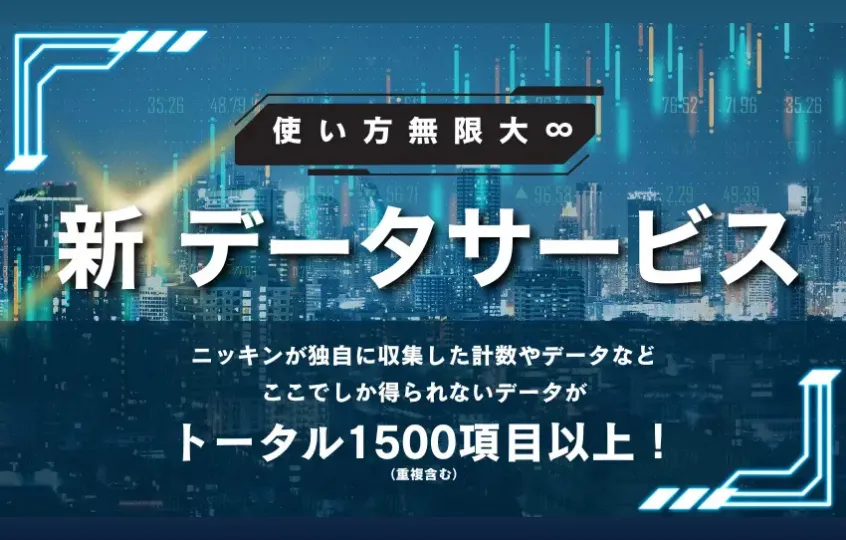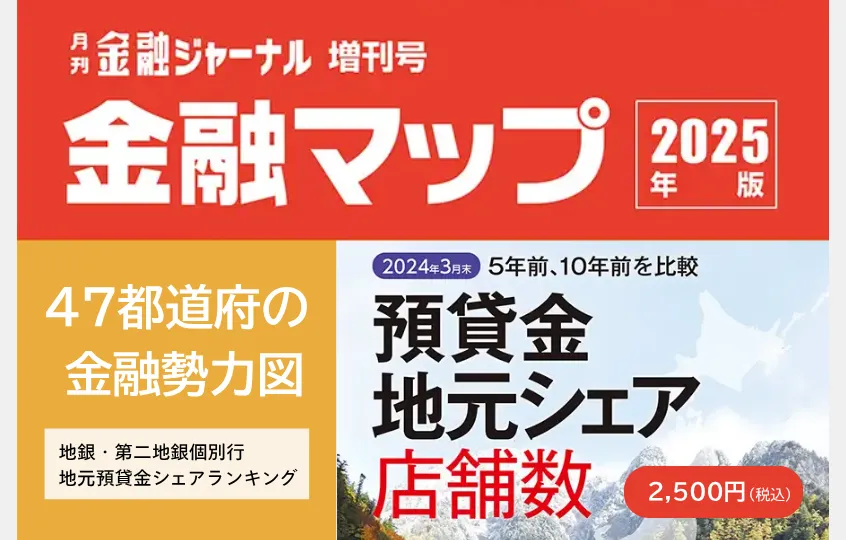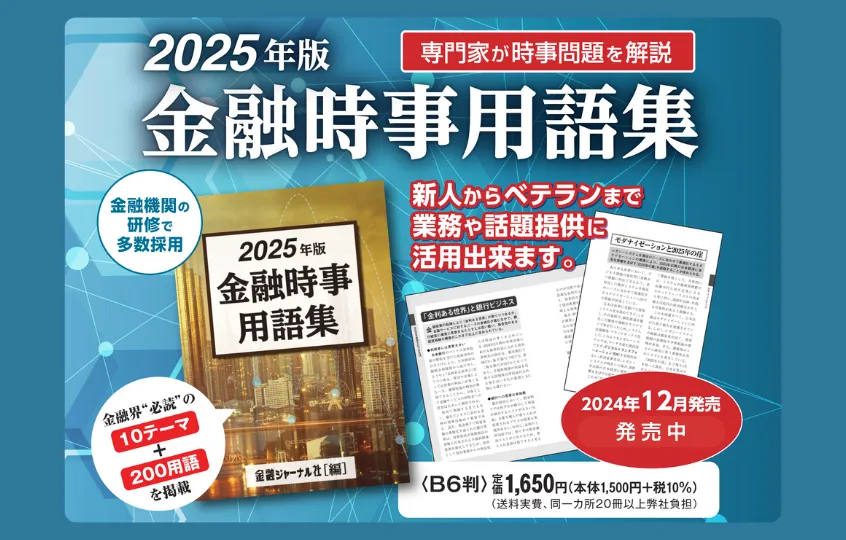ありあけキャピタル 田中克典「銀行に欠けていた株主ガバナンス」~ROE低下の根源~
2025.09.26 19:50
ありあけキャピタルは2020年に設立し、2021年から金融セクターに特化したファンドを立ち上げ、現在地方銀行を中心として投資している。ありあけキャピタルは、ともすると“地方銀行の再編論者”と見られがちだが、我々の本意は「企業価値向上に向けて、株主としてガバナンスを果たしていく」ことである。今回は我々の考える銀行セクターにおける株主ガバナンスの在り方について考えてみる。
カタリストは何だ?
地方銀行や銀行のガバナンスに問題意識を持ち始めたのは、2010年代に前職ゴールドマン・サックスで金融アナリストをしていた頃だ。
当時は低金利環境が長期化し、銀行株は極めて厳しい状況にあった。PBRはメガバンクですら1倍を大きく割り込み、地方銀行は0.5倍を下回るケースも多かった。海外機関投資家から見向きされない状況に陥っていた。
「We know it’s cheap enough. What’s the catalyst? (安いのは十分に分かっている。じゃあ、カタリストは何だ)」。
当時のフィードバックで最も多かったのがこの問いかけだ。株式市場は銀行株を割安と評価しつつも、カタリスト(=市場で再評価される契機)不足の “バリュートラップ”に陥っているという懸念が支配していた。
私自身は逆にカタリストさえあれば、銀行セクターには企業価値向上の可能性と投資妙味があると考えた。「企業価値を上げるカタリストを作れるファンドが必要である」。これが、私が、このファンドを設立した動機の1つになっている。
ROEは資本の回復能力
日本の銀行株は、なぜここまで割安になったのか。リーマン・ショック後の日米の金融機関を比較し「米国金融機関の危機後の回復は、日本の金融機関よりもなぜ早かったのか」という疑問を持った。その答えは、ROE(自己資本利益率)の高さにあった。
具体的に説明すると、金融機関は危機局面では配当見送りや報酬抑制で利益の社外流出を止める。仮にROE10%の金融機関が利益の社外流出を止めると、資本は1年で10%回復するが、ROE3%の金融機関は3%しか資本が回復しない。これを3年間続けると30%(10%×3)と9%(3%×3)という明確な差になる。
前者は米国金融機関、後者は日本の銀行だ。
つまり、金融セクターにおいては、「ROEは資本の回復能力」と定義することが出来る。「ROE...
この記事は会員限定です。
ログインまたはお申し込みください。
.webp)